入局希望者へ
後期研修医募集
後期臨床修練医を募集しています。研修医から希望を聴取し、可能な限り研修医の希望を尊重し、将来の専門医取得まで見据えたプログラムを形成します。
1. 診療科の特徴
1) 循環器内科
循環器内科は、循環器疾患の臨床、教育、研究を担当している。病床数は腎臓内科と併せて一般病棟32床、ICU10床、循環器科指導医は12名、専門修練医(後期研修医該当)は5〜6名、研修医2〜3名で、全員が協力、分担し診療を行っている。心エコーグループ、心カテ・インターベンショングループ、不整脈グループのローテートを行い、さらには腎臓内科へのローテートも行い、循環器および腎臓全般を研修する。希望により心臓血管外科へのローテーションが簡便に行える。
循環器疾患全般の診療を行っており、非侵襲的な診断、動脈硬化危険因子の管理、心不全や不整脈の薬物・非薬物療法、待機的な血管インターベンションまで広く行っている。循環器疾患は、急性増悪をきたし緊急処置を要する患者が多く、急性心筋梗塞、急性心不全、不整脈などの急患も多く、24時間体制で救急診療を行っている。
心臓・大血管・末梢血管のエコー診断を幅広く行い、動脈硬化危険因子の管理を積極的に行っている。虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)に対しては、心臓カテーテル検査はもちろん、経皮的冠動脈形成術(PCI/ステント留置術)をIVUSガイド下に安全に行っており、成功率98%で、薬剤溶出性ステントの導入により再狭窄率も約10%に低下している。症例数の増加に伴い、ロータブレーターの認定施設となり、石灰化の強い症例に施行している。また、不整脈患者に対しては、頻脈性不整脈患者に対するカテーテルアブレーション(軽皮的心筋焼灼術)や植込み型除細動器(ICD)、徐脈性不整脈に対する恒久的ペースメーカ植込み術を行っている。心機能を保つ上で有利な心室中隔ペーシング(右室心尖部ペーシングに比べて)は日本においては当院から始まった。ペースメーカの電池交換は外来での日帰り手術を行っている。ICD、ペースメーカ植込み術は九州地区大学病院では最も症例数が多い。心機能が低下した心不全症例に対する心臓再同期療法(CRT-D)も行っている。神経調節性失神のチルト診断および治療においても当科は日本のパイオニアである。
また、心臓血管外科との連携も緊密にしており、定期的に術前・術後カンファレンスを開き、冠動脈3枝病変や弁膜症といった外科手術症例も増加している。
| 診療実績(2014年) | |
|---|---|
| 心エコー(含む経食道および負荷心エコー) | 7626例 |
| 心臓カテーテル検査 | 763例 |
| 経皮的冠動脈インターベンション | 212例 |
| 末梢血管治療、経皮的弁バルーン形成術 | 57例 |
| 恒久的ペースメーカ植え込み術(含む電池交換) | 77例 |
| ICD植え込み術(含むCRT-D) | 44例 |
| 電気生理学的検査(含む心筋焼灼術) | 96例 |
| 植込み型心電計ILR植え込み術 | 10例 |
2) 腎臓内科
腎臓内科は、腎疾患の臨床、教育、研究を担当している。病床数は循環器科と併せて一般病床32床、ICU10床、腎臓内科指導医は5名、専門修練医(後期研修医に該当)1〜2名、研修医2〜3名で、全員が協力、分担し診療を行っている。循環器内科(心エコー、心カテ・インターベンション、不整脈)へのローテーションを行い、腎臓・循環器全般を研修する。希望により救急部へのローテーションが簡便に行える。
腎疾患全般の診療を行っており、一次性および膠原病などを中心とした二次性の糸球体/間質性腎炎に対してエコー下腎生検等の検査を施行している。組織診断を行い臨床診断/症状をふまえて治療している。また、慢性および急性腎不全の精査加療を行っている。腎不全の原疾患を検査するとともに血液透析および腹膜透析の導入や内シャント作成術などのバスキュラーアクセスの作成や腹膜透析のテンコフカテーテル留置術を行っている。
腎センターには13台の血液透析装置および3台の血漿交換装置があり、他科に入院している維持透析患者も含めて血液浄化を行っている。透析導入の症例数は九州地区大学病院の中ではトップレベルを保っている。膠原病などの自己免疫疾患のほかTTP・薬物中毒や肝不全などの疾患に対しての吸着療法や血漿交換療法などの血液浄化を行っている。急性腎不全を含め緊急の血液浄化や除水などが必要な事態も多く、24時間体制で救急診療を行っている。
| 診療実績(2014年) | |
|---|---|
| 腎生検 | 88例 |
| 血液浄化療法回数 | 3390例 |
| 透析導入数(腹膜透析) | 78(8)例 |
| 手術数 | 113例 |
| シャント造影/ PTA | 108例 |
2. 研修プログラム体系図
- 募集人数:10人(各年次につき)
- 研修スケジュール
- 給与、健康保険等:常勤医師、私学共済健康保険あり、 卒業年度によって若干差異があるも、年収800〜1000万円前後(外勤先給与含む)
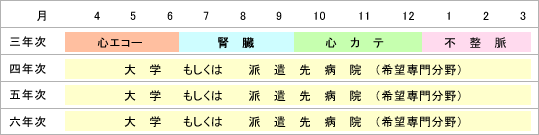
3. 専門医取得プログラム体系・専門医取得状況
取得認定医・専門医制度
全員が取得可能なもの: 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
新・内科専門医
その他(subspecialty): 日本循環器学会認定循環器専門医
日本腎臓学会腎臓専門医
日本透析医学会透析専門医 など
認定内科医・総合内科専門医取得までのプログラム体系
<2004年(平成16年)以後の医師国家試験合格者>
認定内科医
初期臨床研修2年間(そのうち、内科臨床研修6ヶ月以上)+教育病院または教育関連病院での「内科後期臨床研修1年間(12ヶ月)以上」=計3年間以上(第2内科学ではいずれも取得可能です)。
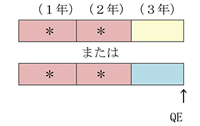
*=必修化された初期臨床研修
■=教育病院(大学病院・内科臨床大学院含む)での内科後期臨床研修
■=教育関連病院での内科後期臨床研修
QE=認定内科医資格認定試験(Qualifying Examination)
総合内科専門医
認定内科医資格取得後、
A. 教育病院1年以上含む、合計3年間以上の内科臨床研修(第2内科学での研修は主にこれにあたります)。
B.教育病院1年未満を含む、合計5年間以上の内科臨床研修(本人の希望があれば第2内科学ではこちらも可能です)。
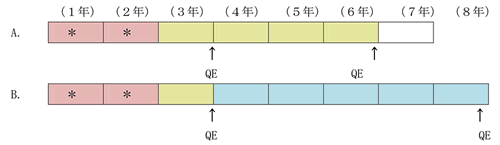
*=必修化された初期臨床研修
■=教育病院(大学病院・内科臨床大学院含む)での内科後期臨床研修
■=教育関連病院での研修/教育病院から派遣された無認定病院での研修
(第2内科学からの派遣証明書が必要です)
QE=認定内科医/総合内科専門医資格認定試験(Qualifying Examination)
<2015年(平成27年)以後の医師国家試験合格者:新・制度>
新・内科専門医
新・制度は2015年(平成27年)から初期臨床研修を始める方を対象に行われる予定です。
・従来の認定内科医(3年研修)資格以上に、内科全般の研修実績を重視し、初期研修を含め、5年の内科研修が必要となります(第2内科学での研修では、派遣病院含め、新・内科専門医取得が可能です)。
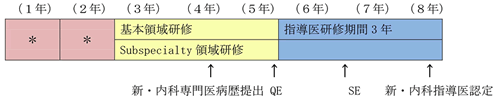
*=必修化された初期臨床研修
■=教育病院(大学病院・内科臨床大学院含む)での内科後期臨床研修
■=指導医研修期間/サブスペシャルティ研修期間
QE=新・内科専門医筆記試験(Qualifying Examination)
SE=サブスペシャルティ専門医試験(Subspecialty Examination)
| 医局員の取得状況 | |
|---|---|
| 医学博士 56 | 日本内科学会認定内科医 60 |
| 日本内科学会指導医 23 | 日本内科学会総合内科専門医 36 |
| 日本循環器学会循環器専門医 32 | 日本医師会認定産業医 29 |
| 日本腎臓学会腎臓専門医 5 | 日本腎臓学会腎臓指導医 2 |
| 日本透析医学会透析専門医 6 | 日本アフェレシス学会認定専門医 |
| 日本透析医学会透析指導医 3 | 植込み型除細動器研修修了認定 |
| ペーシングによる心不全治療研修修了認定 | 米国心臓学会特別正会員 (FACC) |
| 日本心臓病学会特別正会員 (FJCC) | 日本心血管インターベンション認定医 |
| 日本心血管インターベンション指導医 | 日本超音波医学会指導医 |
| 他多数 | |
4. 施設認定(第2内科学関連)
| 日本内科学会認定医制度教育病院 | 日本循環器学会循環器専門医研修施設 |
| 植え込み型除細動器(ICD)認定施設 | 両室ペーシング(CRT)認定施設 |
| 日本老年医学会認定施設 | 日本アフェレシス学会認定施設 |
| 日本腎臓学会認定医研修施設 | 日本透析医学会認定施設 |
| 日本心血管インターベンション治療学会研修施設 | ロータブレーター認定施設 |
| 日本不整脈学会 日本心電学会認定不整脈専門医研修施設 |
5. 当診療科での修練のメリット
1) 循環器内科
循環器疾患の適切な診断、治療計画を作成できるようにするとともに、基本的な循環器救急に対応できるようにすることを目標とする。腎臓診療や救急部とのローテーションが円滑に行え幅広く勉強できる。
主として病棟で指導医のもと主治医として患者を受け持ち、循環器疾患に関する診療技術と知識を学ぶ。心エコー検査や心臓核医学検査、320列MDCT(平成27年4月導入)、MRIをはじめとする非侵襲的な検査法から、心臓カテーテル検査、電気生理学的検査、ペースメーカ・ICD植え込み術の技術、知識の習得が可能である。平成9年からCPA患者の受け入れを開始し、平成16年には救急病院の指定を受けたことから、当院救急部からの依頼による急性心不全、急性心筋梗塞、心室細動・頻拍など循環器疾患患者も増加している。近年腎機能低下や透析症例の冠動脈疾患患者が増加しており、当科では腎臓内科と同じ診療科であることから、このような合併症を持つ循環器疾患症例の経験を多く積むことができる。
当科では、研修後に臨床系の大学院教育を行っており、後期研修の後に循環器診療を続けながら大学院に入学し、臨床研究を行い学位取得も可能である。また、基礎医学系の大学院教育も行っており基礎研究による学位取得も可能である。さらに、北九州内外の関連病院で循環器・腎臓・救急・一般内科の臨床を継続することも可能である。
2) 腎臓内科
慢性および急性腎炎(糸球体/間質性)の精査/加療について実際携わり、修得していく。一次性および膠原病などを中心とした二次性の糸球体/間質性腎炎に対してエコー下腎生検等の手技を実際に行ない、腎生検カンファにおいて組織診断を修得していくとともに、実際に治療に携わっていく。
慢性および急性腎不全の加療を行う。血液透析および腹膜透析の導入や内シャント作成術などのバスキュラーアクセスの作成や腹膜透析のテンコフカテーテル留置術を修得するとともに、水曜日の腎センターカンファおよび金曜日の腎グループカンファに参加し腎不全患者の加療を行う。また、腎センターには13台の血液透析装置および1台の血漿交換装置、3台の緩徐式血液濾過装置があり、腎センターカンファに参加するとともに、他科に入院している維持透析患者の血液浄化に携わっていく。さらに、膠原病などの自己免疫疾患のほかTTP・薬物中毒や肝不全などの疾患に対しての吸着療法や血漿交換療法をおこなっていく。二次性高血圧症の精査など行ない、高血圧症患者の検査/加療をおこなっていく。
当科では、研修後に臨床系の大学院教育を行っており、後期研修の後に腎臓診療を続けながら大学院に入学し、臨床研究を行い学位取得も可能である。また、基礎医学系の大学院教育も行っており基礎研究による学位取得も可能である。さらに、北九州内外の関連病院で腎臓・循環器・救急・一般内科の臨床を継続することも可能である。
| 指導責任者・指導医 | |
|---|---|
| 指導責任者 | 尾辻 豊 循環器内科、腎臓内科診療科長、第2内科学教授 |
| 指導医 | 田村雅仁診療教授、腎臓内科副診療科長、腎センター部長(腎疾患/血液浄化)、安部治彦不整脈先端治療学教授(不整脈、失神)、園田信成准教授、循環器内科副診療科長(虚血性心疾患、冠動脈インターベンション)、荒木優講師(虚血性心疾患、心臓リハビリテーション)、津田有輝講師(虚血性心疾患、心血管画像診断)、萩ノ沢泰司講師(不整脈)、岩瀧麻衣講師(心不全/心エコー)、村岡秀崇講師(虚血性心疾患)、大江学治助教(不整脈)、穴井玲央助教(虚血性心疾患)、宮本哲講師(腎疾患/血液浄化)、坂東健一郎助教(腎疾患/血液浄化)、中野陽子助教(腎疾患/血液浄化) |
連 絡 先
担 当 者: 尾上 武志(第2内科学 循環器内科、腎臓内科 医局長)
郵便番号: 807-8555
住 所: 北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
電話番号: 093-691-7250
FAX番号: 093-691-6913
E-mail:
学校法人 産業医科大学
〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号 TEL:093-603-1611(代表)
関連施設
第2内科学では、近隣の医療機関や全国の労災病院に常勤医師を、また産業医を派遣しております。
1. 常勤医師派遣先
労災病院
| 病院名 | 科 | ホームページアドレス |
|---|---|---|
| 旭労災病院 | 循環器科 | http://www.asahih.rofuku.go.jp |
| 九州労災病院 | 循環器科 | http://www.kyushuh.rofuku.go.jp |
| 熊本労災病院 | 循環器科 | http://www.kumamotoh.rofuku.go.jp |
| 九州労災病院門司メディカルセンター | 循環器科 | http://www.mojih.rofuku.go.jp |
その他病院
| 病院名 | 科 | ホームページアドレス |
|---|---|---|
| 町立芦屋中央病院 | 循環器科・腎臓内科 | http://www.ashiya-central-hospital.jp |
| 板橋中央総合病院 | 循環器科 | http://www.ims-itabashi.jp/ |
| 小波瀬病院 | 循環器内科 | http://www.youmeikai.jp/obase-top/ |
| かめざき内科クリニック | 循環器科 | http://www.km-clnc.jp |
| 北九州市立八幡病院 | 循環器科 | >http://www.yahatahp.jp |
| 九州病院 | 総合診療科 | http://kyusyu.jcho.go.jp |
| 地方独立行政法人くらて病院 | 循環器科・腎臓内科 | http://kurate-hp.com/ |
| 古賀中央病院 | 循環器科 | http://www.koga-c-hp.or.jp/ |
| 済生会熊本病院 | 循環器内科 | http://sk-kumamoto.jp/ |
| 済生会八幡総合病院 | 循環器科 | http://www.yahata.saiseikai.or.jp/ |
| しばた循環器内科クリニック | 循環器科 | http://kiyokoclinic.com/ |
| 杉村病院 | 循環器内科 | http://sugimurakai.jp/ |
| 製鉄記念八幡病院 | 循環器内科 | http://www.ns.yawata-mhp.or.jp/ |
| 田川市立病院 | 循環器内科 | http://hospital.city.tagawa.fukuoka.jp/ |
| 富永病院 | 循環器科 | http://www.tominaga.or.jp/ |
| 西田内科クリニック | 腎臓内科 | |
| 社会保険直方病院 | 循環器科・腎臓内科 | >http://nogata-hp.jp/ |
| 新王子病院 | 腎臓内科 | http://www.ouji-byouin.jp/ |
| 萩原中央病院 | 循環器科 | http://www.hagiwara.or.jp |
| ひびきクリニック | 腎臓内科 | |
| 水巻クリニック | 腎臓内科 | |
| 行橋クリニック | 腎臓内科 | http://www.myclinic.ne.jp/yuku_cl/pc/ |
| 芳野病院 | 腎臓内科 | http://www.yoshino-hp.com/ |
2. 産業医派遣先
| 施設名 | ホームページアドレス |
|---|---|
| 九州健康総合センター | http://www.kyuken.or.jp |
| 新日鐵住金和歌山製鐵所 | |
| 北九州市産業医 | |
| 日立製作所ソフトウェア事業部健康管理センター | |
| 日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 | |
| NTT西日本九州健康管理センター | |
| JR東海総合病院内東海旅客鉄道(株)健康管理センター | |
| 東京ガス株式会社 | |
| (財)福岡労働衛生研究所 | >http://www.rek.or.jp |
| 下関水産振興協会 | |
| 西日本産業衛生会 | http://www.nishieikai.or.jp/ |
カンファレンスのご案内
循環器系
循環器内科・心臓血管外科 合同カンファレンス
循環器疾患の手術適応や術後検討を主題に、毎週木曜日午後6時に8A病棟カンファレンスルームで行なわれます。
循環器内科カンファレンス
研修医の臨床教育的指導を主体とした循環器内科入院症例検討会。毎週木曜日午後に8A病棟カンファレンスルームで行なわれます。
心エコーカンファレンス
特徴的な心エコー症例を毎回提示し、尾辻先生の指導の下、ミニレクチャーを交えたケースカンファレンス。毎週火曜日午後6時から大学病院2階カンファレンスルームで行われます。
リサーチセミナー
大学院生を中心に、現在進行しているリサーチの紹介カンファレンス。毎週月曜日午後6時半から第2内科学カンファレンスルーム(1237号室)で行われます。
文献の抄読会は、各専門領域のグループにて随時開催されています。
腎臓内科
当科では下記のカンファレンスを行っています。
症例検討会では入院中の患者様のカンファレンスを行っています。御紹介元の医療機関の先生の御参加も歓迎いたしますので、御連絡下さい。
月曜日:循環器腎臓内科症例検討会、病棟回診
水曜日:腎センター症例検討会
木曜日:腎臓内科研究カンファレンス、腎生検病理検討会
金曜日:腎臓内科症例検討会、病棟回診
常勤医師・非常勤医師募集
当院は日本腎臓学会と日本透析医学会の指定教育機関です。専門医研修を御希望される先生がございましたら御相談下さい。
当科での研修により取得可能な資格には下記のものがあります。
日本腎臓学会 腎臓専門医、腎臓指導医
日本透析医学会 透析専門医、透析指導医
日本内科学会 認定内科医、総合内科専門医
医学博士