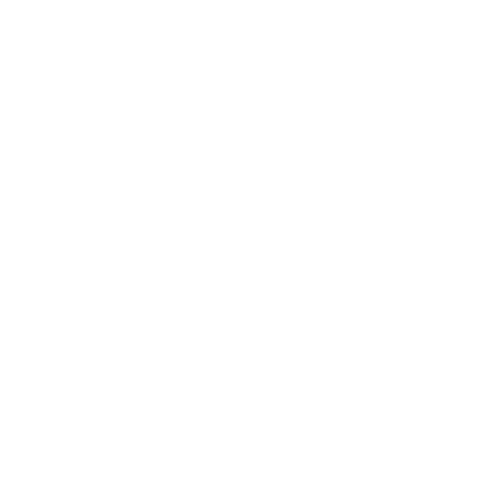研修プログラム
内科診療を適切に行うために、免疫疾患(膠原病・リウマチ・アレルギー疾患)・感染症、内分泌・糖尿病・代謝疾患、血液・腫瘍疾患の病態についての理解を深め、医学的根拠と、問題点に立脚した系統的な思考過程を介して患者を全人的に捉えるとともに、患者および家族との良好な人間関係の確立に配慮しつつ、内科全般を総合診療し、プライマリケア医療を習得する。また、それぞれの疾患を的確に診断し治療する能力を身につけ、高度先進医療も理解することができる。 |
| ユニット |
的確な診断に到達し適切な指導を行うために、診断に必要な医療情報を得ることの必要性を理解し、患者、家族との信頼関係の構築に配慮した医療面接および療養指導の能力を身につける。
1. 面接で聴取すべき事項を列挙できる。(想起) 2. プライバシーの守れる環境(場所)を準備できる。(態度) 3. 患者に不安を与えないように接することができる。(態度) 4. 病状、現病歴、既往歴、家族歴などの情報を的確に聴取できる。(技能) 5. 診断やその後の指導に必要な生活歴を詳細に聴取できる。(技能) 6. 患者・家族がともに満足できる医療を行うためのインフォームドコンセントが実施できる。(態度) 7. 個々の生活環境を配慮した適切な療養指導ができる。(技能)
病態を把握し適切な診断に到達するために、全身にわたる身体診察を系統的に実施することの重要性を理解し、基本的な診察技能と患者に配慮する態度を身につける。
1. 疾患ごとに重要な診察項目を列挙できる。(解釈) 2. バイタルサインの測定ができる。(技能) 3. 皮膚所見(皮疹、皮膚硬化、壊死等)、粘膜症状(舌炎、口腔乾燥)について記載できる。(技能) 4. 骨、関節、筋肉系の炎症所見、変形、筋力、運動制限の程度について記載できる。(技能) 5. 心、肺、脈管系の異常(脈の左右差、心、肺、血管雑音、血管炎の有無)を指摘できる。(技能) 6. 腹部所見の異常(肝脾腫、リンパ節腫大、急性腹症など)を指摘できる。(技能) 7. 眼底所見の異常(血管炎、虹彩毛様体炎、網膜炎、視神経炎など)を指摘できる。(技能) 8. 貧血および出血傾向を指摘できる。(技能) 9. リンパ節の腫大について(位置、大きさ、圧痛、可動性、硬度など)記載できる。(技能) 10. 甲状腺の触診ができる。(技能) 11. ホルモン異常に伴う特異的な身体所見(中心性肥満、粘液水腫など)について説明できる。(解釈) 12. 眼底鏡を使用した網膜の評価ができる。(技能) 13. 診察中の患者の全身状態や心情に配慮できる。(態度)
医療面接、身体診察から得られた情報をもとに的確な診断に到達するために、基本的臨床検査の意義を理解し、問題点に立脚した系統的な思考過程を介して患者の全体像を捉える能力と患者に配慮する態度を身につける。
1. 基本的な検査項目を列挙できる。(想起) 2. 血液型判定、血液交差適合試験が実施できる。(技能) 3. 心電図検査が実施できる。(技能) 4. 超音波検査が実施できる。(技能) 5. 肺機能検査の結果を判断できる。(技能) 6. 動脈血ガス分析、骨髄検査、髄液検査、関節液検査が実施できる。(技能) 7. 単純X線検査、造影X線検査、CT検査、MRI検査、シンチグラムなどの各種画像診断検査の結果を判断できる。(技能) 8. 感染症の鑑別に必要な検体の採取、保存、簡単な検査(グラム染色等)を実施できる。(技能) 9. 病理組織標本(皮膚、口唇腺、肺、腎等)の所見から鑑別すべき疾患について説明できる。(解釈) 10. 血算や凝固検査による血液異常から鑑別診断とその重症度の判断ができる。 (技能) 11. 末梢血、骨髄血、リンパ節や各臓器検体の塗沫標本の作製、染色と顕微鏡での観察ができる。(技能) 12. 内分泌疾患に対して各種負荷試験を実施できる。(技能) 13. 内分泌疾患についてシンチグラム、血管造影、静脈サンプリングなどの意義を説明できる。(解釈) 14. 糖負荷試験が実施できる。(技能) 15. 簡易血糖測定器を適切に使用できる。(技能) 16. 糖尿病性慢性合併症の評価ができる。(技能) 17. 検査中の患者の全身状態や心情に配慮できる。(態度) 18. 検査結果を本人および家族にわかりやすく説明できる。(態度)
検査および治療を適切に行うために、必要な基本的手技の重要性を理解し、患者の状態にも配慮した手技の適応決定と的確に実施する能力を身につける。
1. 採血(静脈血、動脈血)ができる。(技能) 2. 注射(皮内、皮下、筋肉、静脈)ができる。(技能) 3. 血管の確保(末梢および中心静脈)ができる。(技能) 4. 輸液、輸血が実施できる。(技能) 5. 骨髄、腰椎、関節穿刺が実施できる。(技能) 6. 胃管の挿入ができる。(技能) 7. 導尿ができる。(技能) 8. パルスオキシメーターの装着ができる。(技能) 9. 局所麻酔法が実施できる。(技能) 10. 創部消毒とガーゼ交換が実施できる。(技能) 11. 処置中の患者の状態への配慮ができる。(態度) 12. 救急蘇生法を実施できる。(技能) 13. 人工心肺、人工腎臓、人工膵臓の原理や適応について説明できる。(解釈)
問題点に立脚した系統的な治療計画を実践するために、基本的治療法の適応を理解し、患者の状態に配慮した治療法を身につける。
免疫、感染疾患の診療を適切に行うために、アレルギー性疾患、全身自己免疫疾患(膠原病・リウマチ性疾患)、免疫不全症、感染症の病因と病態を理解し、患者の状態にも配慮した診断・治療の基本的能力を習得する。
1. 発熱、全身倦怠感や関節痛などの全身症状や所見の評価ができる。(技能) 2. 全身の多臓器障害がもたらす症状と所見について説明できる。(解釈) 3. 感染症の鑑別に必要な検体の採取、保存、簡単な検査(グラム染色等)の実施ができる。(技能) 4. 真菌、サイトメガロウイルスやカリニによる日和見感染のDNA、抗原診断ができる。(技能) 5. 各種病原体による感染の予防対策を実践できる。(技能) 6. 血算、生化学検査、血清学的検査(特に各種自己抗体など)などを駆使した膠原病・リウマチ性疾患の診断、 並びに、重症度(疾患活動性)や障害臓器などの判定ができる。(技能)
9. 病理組織標本(皮膚、口唇腺、肺、腎等)の評価ができる。(技能)
内分泌、代謝疾患および生活習慣病の診療を適切に行うために、ホルモンおよび代謝異常の病態についての理解を深め、患者の状態にも配慮した診断・治療の基本的能力を身につける。
1. 主要な内分泌疾患を列挙できる。(想起) 2. 各種負荷試験を用いたホルモン動態の評価ができる。(技能) 3. 甲状腺、副腎や下垂体ホルモン異常の鑑別診断について説明できる。(解釈) 4. 内分泌性緊急症(急性副腎不全、甲状腺クリーゼ等)への適切な対応ができる。(技能) 5. 適切なホルモン補充療法と療養指導ができる。(技能) 6. 内分泌疾患におけるシンチグラム、血管造影、静脈サンプリングの所見について説明できる。(解釈) 7. 肥満(単純性肥満及び内分泌性肥満)の鑑別診断と生活指導および治療が適切に行える。(技能) 8. 骨粗鬆症の診断、治療及び予防が適切に行える。(技能) 9. 糖負荷試験によるインスリン分泌能およびインスリン抵抗性の評価ができる。(技能) 10. 糖尿病の病型分類について説明できる。(解釈) 11. 糖尿病性慢性合併症の評価ができる。(技能) 12. 糖尿病性(高血糖性)昏睡の治療ができる。(技能) 13. 個々の生活環境を考慮した糖尿病の食事療法と運動療法の指導ができる。(技能) 14. 個々の病態を考慮した糖尿病の薬物療法が選択できる。(技能) 15. 患者の病態と生活状況を考慮したインスリン療法を実施できる。(技能) 16. 糖尿病の患者教育(糖尿病教室など)に参画できる。(技能) 17. 患者の理解度や心理状態に配慮した治療法を選択できる。(態度) 18. 低血糖(インスリノーマ等)の鑑別診断と治療ができる。(技能) 19. 病状や治療内容について、本人および家族にわかりやすく説明できる。(態度)
【 特徴1 】 個別指導医制:研修医は以下のような2名の指導医による徹底した指導体制のもとで研修する。
各症例は上記カンファレンスにて毎週数回議論され、チーム医療を基本に、迅速かつ的確な判断の上に診断、治療にあたる。 【 特徴2 】 プライマリケア医療の重視:ローテート方式臨床研修あるいは総合診療方式に従い、臨床研修プログラムが組まれているが臨床研修終了後も大学病院での修練を基本としたプログラムが組まれており、大学専門修練医としてプライマリケア医療の能力を修得した上でのより高度な知識、技術の修得をめざす。 【 特徴3 】 全身疾患の診療と高度先進医療の実践:第1内科学講座の教育責任科目は内分泌・代謝疾患・糖尿病、血液・腫瘍疾患、膠原病・リウマチ・アレルギー・感染疾患であり、全身性内科疾患を通じて、医学的根拠と、問題点に立脚した系統的な思考過程を介して患者の全体像を捉えることにより内科全般について総合的に診療すると同時に、難治性疾患の診療を通して高度先進医療技術を習得した医師の養成をも念頭においている。
産業医科大学病院での研修
■病棟医長回診 ベッドサイドにて病棟医長に1週間の要約を行い、内科診療における基本的診療が適切になされているか討論する。 ■回診前総合カンファレンス 新入院患者に関して、患者紹介レポートを指導医の指導の下に作成し、教授を中心とするカンファレンスの場で発表し、診断、治療などに関して十分に討論する。又、その他受け持ち入院患者に関しては、Weekly summaryを作成し、1週間の経過を呈示し、診療方針を討論する。第1内科学講座の全ての医師が参加しており、病態の把握、診断や治療に関して系統的、多角的な総合討論がなされる。更に、カンファレンスを通じて、症例の系統だった捉え方、ならびに適切なプレゼンテーションの仕方を習得する。 ■教授病棟回診 教授がベッドサイドで直接指導する。 ■各専門分野別カンファレンス 病院内外の各分野の専門医が参加し、研修医が症例を呈示し、病態、診断、治療方針などについて活発な討論がなされ、医療の基本的な事項から専門的な事項まで習得できる。 ■個別指導医制 各研修医に指導医がつき、基本的態度、姿勢、知識、診療能力等、医療実践全般に必要とされる事項を指導する。 ■卒後研修(臨床研修基本事項) 週に1回、講義、VTR学習、症例検討、ロールプレイ等の形式で以下のことに関して指導を受け、これらの医師に必要な基本的事項を習得できる。
■リサーチカンファレンス 第1内科学講座の臨床研究を含む研究内容の発表や学会予行を行うリサーチカンファレンスにも参加できる。 ■大学院講義 臨床/研究において学外の著名な専門講師を招き、聴講および討論会を行う。大学院講義であるが研修医も自由に聴講できる。 ■糖尿病教室 集団教育のポイントを習得する。 ■移植前カンファレンス 骨髄移植等の移植症例がある場合、多種の医療従事者と円滑にチーム医療を行うために随時行っており、チーム医療の進め方を学習できる。
※研修が半分終了した時点で研修の自己評価、指導医評価が行われ、 結果はフィードバックされる。 ※研修終了時に指導医や研修プログラムの評価を研修医が行い、 次年度のプログラムに反映する。 ※該当症例があれば指導医の下で学会発表や英文・和文論文作成を行う。
産業医科大学医学部 第1内科学講座 医局長 花見 健太郎 電話;093-603-1611 内線2422 FAX;093-691-9334 E-mail:hanami@med.uoeh-u.ac.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||