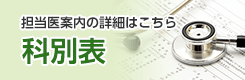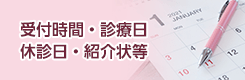包括同意について
書面による同意を行わない軽微な検査・処置・投薬等について
当院では、「書面で同意をいただく診療項目」と「口頭又は掲示で説明と同意確認をさせていただく診療行為」に分けて対応しております。以下の検査・処置・投薬等は、医師の立ち会いを必要としないものもあり、患者さんの心身へのご負担も一般的に少ないものです。診療を円滑に進めるために、これらの診療行為については、説明と同意確認を口頭又は掲示で対応しております。
(1)一般項目
各種問診、視診、身体診察、体温測定、身⾧測定、体重測定、血圧測定、栄養指導、食事の決定、カメラ等による患部撮影等(主として体表)、ピクトグラムの使用など
(2)検査・モニター等
血液学検査(血液等の採取)、尿・糞便等検査、免疫学的検査(B型肝炎、C型肝炎、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)検査等)、微生物学的検査(痰・唾液等の採取)、骨塩定量検査、病理・細胞診検査、生理機能検査(心電図検査、脈波検査、肺機能検査、脳波検査、超音波検査、筋電図検査等)、X線一般撮影検査、X線透視撮影検査、造影剤を用いないCT・MRI検査、経皮酸素飽和度測定検査、動脈圧測定検査、モニター(心電図、呼気換気、動脈圧、BISモニター(脳波を元に麻酔薬の効果を推定するモニター)、筋弛緩モニター等)、皮内反応検査、パッチテスト、鼻咽腔・喉頭ファイバー等、尿流量測定検査、残尿測定、肛門鏡検査、新生児ビリルビン濃度測定、体内埋め込み型デバイスの確認・点検、高次脳機能検査、針刺し事故等の血液・体液暴露があった場合の暴露源患者の感染症検査など
(3)処置
静脈血採血、動脈血採血、静脈留置針挿入 、ヒールカット採血、痰等の吸引、胃管カテーテル挿入・管理、イレウス管挿入・管理、尿道留置カテーテル挿入・管理 、口腔ケア等の処置、創傷処置(洗浄・薬剤充填)、抜糸、縫合、ドレーン抜去、浣腸、各種チューブの管理および洗浄、弾性ストッキング着用、下肢への圧迫ポンプ装着、簡単な歯科処置、液体窒素療法、光線療法、軟部腫瘍(ガングリオン)穿刺、処置時に行う一時的な身体固定など
(4)投薬、投与
通常の投薬、注射、末梢静脈内留置針挿入(点滴路の確保) 、皮下注射、持続皮下留置針挿入、胃瘻・腸瘻・胃管への注入(経腸栄養剤等)、酸素療法、非侵襲的陽圧換気、ネーザルハイフロー等、 個別同意を必要とする製剤以外の院内製剤、髄腔内薬剤投与、腱鞘内注射など
(5)医薬品・医療機器等の適応外使用
医薬品及び医療機器等は、医薬品医療機器等法に基づき厚生労働省で承認された方法で使用することが求められます。しかし、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用すること(適応外使用等という)もあります。
この場合、産業医科大学若松病院では医療の質・安全管理部で情報を把握し、産業医科大学病院薬事委員会、産業医科大学病院倫理委員会、医療の質・安全管理部定例会議等と適宜連携をとり、当院の規程に則り、使用の必要性や、有効性・安全性等の面から問題がないかを評価します。 リスクの高い治療については産業医科大学病院倫理委員会で審議し、承認した上で使用する取り決めとしています。
医薬品適応外使用は、国の副作用被害を補助する制度(医薬品副作用被害救済制度)の対象外となる可能性があるのでご承知おき下さい。
(6)休日リハビリテーションにおける自主訓練について
早期リハビリテーションの推進、および患者サービスの向上の一環として、通常診療のリハビリテーション(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が実施)以外に、患者さんによる自主訓練を実施しています。
休日リハビリテーションにおける自主訓練では、自主訓練の場所や物品を提供し、平日に担当療法士が指導した訓練メニューを、患者さん自身が行います。対象者は、整形手術後の安定した方などで、診療科の担当医師やリハビリテーション科医師によって選定されます。患者さんにおかれましては、自己責任のもと、安全に留意して取り組んでいただきますようお願いいたします。
上記の診療行為は、一定以上の経験を有する医師・歯科医師・看護師・技師等によって行われ、一般的な医学的基準から考えて安全と考えられるものですが、それでも臓器および組織の損傷・精神的(心理的)動揺・出血・しびれ・アナフィラキシー・その他予期せぬ併発症・有害事象を伴うことがあり得ます。このような併発症・有害事象等は、極めて頻度が低いものの、行為者の技量に関わらず、一定の割合で生じることがあります。また、他の医療行為によるものと同様に、症状が自覚的で現在の医学では評価が困難であったり、症状等の持続期間が予測困難で、中には症状が固定して永続するものもあります。
このような場合は、併発症・有害事象の治療は通常の保険診療として行われます。あらかじめご理解いただきますようお願いいたします。
特殊な処置等がありますので、<項目名>をクリックして個別にご覧ください。内容や併発症・有害事象を含めましてご不明な点がございましたら、担当医師や看護師・薬剤師・技師等にお申し出ください。
教育へのご参加に関する包括同意について
診療を受けられる患者の皆様へ -教育へのご参加に関する包括同意について-
1 はじめに
2 包括同意とは
3 診療に伴い発生する情報や試料等とは
4 診療に伴い発生する情報や試料等の利用に関する個人情報保護について
5 同意撤回の自由について
6 同意撤回などの相談窓口
1 はじめに
産業医科大学若松病院では、患者第一の医療を行うことを理念として、患者さんに最良の医療を提供できるように日々努力しております。また、臨床研修・実習及び生涯教育の充実を図り、産業医をはじめ全ての分野における人間愛に徹した優れた医療人を育てることを基本方針として、医療水準の向上と社会貢献のために取り組んでいます。このような医療人を育成するための教育を充実させるために、診療に伴い発生する情報や試料等を教育に使用させていただくことにつきまして、医療機関と教育機関としての当院の役割をご理解いただき、ご参加のほどよろしくお願いいたします。
2 包括同意とは
包括同意とは、医療人を育成するための教育を充実させるために、診療に伴い発生する情報や試料等を使用させていただくことに対して、あらかじめ同意をお願いするものです。不同意の意思表示がない場合には同意したものとみなし、教育の充実と発展のために、診療に伴い発生する情報や試料等を使用させていただきます。
3 診療に伴い発生する情報や試料等とは
・診療上必要な X 線写真、CT、MRI、PET などの放射線診療画像、内視鏡、カメラ等で 撮影された患部の写真や動画 ※
※動画とは、様々な医療機器において記録・保管される動画データのこと。
・心電図、超音波検査などの生理機能検査結果
・血液、尿などの検査検体と検査結果
・診断のために採取した組織(内視鏡や生検など)
・手術で摘出した組織・臓器など
・診療経過記録
・その他:診療のために必要と思われる情報や試料
4 診療に伴い発生する情報や試料等の利用に関する個人情報保護について
診療に伴い発生する情報や試料等に含まれる個人情報は匿名化して取り扱い、外部に漏れないように最大限の配慮をいたします。個人が特定されることはありませんのでご安心ください。
当院では、「産業医科大学若松病院における個人情報保護に関する基本方針」に従い個人情報を厳重に取り扱います。 個人情報保護に関する基本方針については<こちら>をご覧ください。
5 同意撤回の自由について
原則としてご本人からの申し出により、包括同意はいつでも撤回することができます。同意を撤回した場合であっても診療上の不利益を受けることは決してありません。ただし同意撤回の意思表示より以前に使用した教育資料につきましては、対応できない場合がございますので予めご了承ください。
6 同意撤回などの相談窓口
教育へのご参加に関する包括同意に関してご不明な点や疑義がある場合、同意撤回(または包括同意に不同意)の申し出につきましては、患者相談窓口までご相談ください。
連絡先:産業医科大学若松病院 患者相談窓口
2021 年 8 月 産業医科大学若松病院長