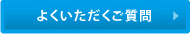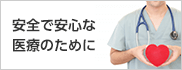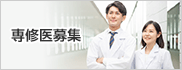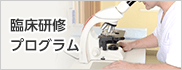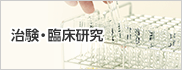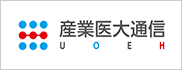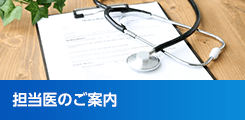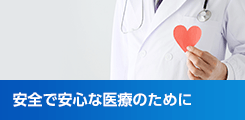リハビリテーション科
| 医学部の当講座ホームページはこちらへ |
概 要
当科では、リハビリテーション科専門医が病気や障害の診断・治療を行います。治療対象となるのは病気および病気により生じた日常生活や社会生活上の問題などであり、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理師、義肢装具士、医療ソーシャルワーカーと共同して、訓練、指導、助言、調整などを行います。
対象疾患と治療の特色
対象となる病気は、脳卒中、外傷性脳損傷、神経筋疾患、ポリオ、スモン、切断、脊髄損傷、骨関節疾患など、多岐にわたります。これらの病気により生じる障害、すなわち歩行障害、日常生活動作制限、言語障害、嚥下障害、高次脳機能障害(記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害)なども治療対象となります。治療のためには2〜4週間入院して、専門医が集中的な高いレベルの診察、検査、治療を行い、経験豊富なリハビリテーション部スタッフが適切な訓練を行います。より長期間訓練が必要な場合は、近隣の回復期リハビリテーション病院に転床してリハビリテーション訓練を継続します。
専門的治療の特徴
臨床研究経験の豊富なリハビリテーション科専門医が診療を担当し、教授、准教授、講師の診察、回診、カンファレンスを行い、質の高いリハビリテーション医療を実践します。検査としては、最先端の装置を用いてMRI、脳血流シンチ、神経生理学的検査(筋電図、脳波、誘発電位)、嚥下機能検査(嚥下造影、嚥下内視鏡)、歩行解析、筋力測定を行い、診断や障害判定を行います。脳卒中では通常の訓練のほかに、ロボットを用いた歩行訓練または上肢機能訓練、経頭蓋直流電気刺激や磁気刺激を用いた片麻痺改善、痙縮に対するボツリヌス治療、嚥下障害に対する専門的検査と治療を行います。高次脳機能障害に関しては福岡県拠点機関に指定されており、高次脳機能障害支援コーディネイターが受診の窓口となり、専門的な神経心理検査と障害判定を行います。また、自動車運転シミュレーション等を用いて自動車運転評価を行います。ポリオ患者にはポストポリオ症候群の診断やカーボン製超軽量装具の作製、切断者には最新の義足作製などを行います。また、産業医学の観点から障害者の就労支援・両立支援にも取り組んでいます。
外来診療区分
|
時間帯 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|
午 前 |
紹介、初診 |
紹介、初診 再診(予約) |
紹介、初診 再診(予約) |
紹介、初診 |
紹介、初診 再診(予約) |
|
午 後 |
再診(予約) * |
* |
* |
再診(予約) * |
* |
スタッフ紹介
教授
佐伯 覚(サエキ
サトル):診療科長
- 専門分野
脳卒中、神経筋疾患(ポリオ等)、産業医学・産業疫学、医学統計
- 学会認定医等
-
- 日本リハビリテーション医学会認定臨床医・リハビリテーション科専門医・指導医、日本脳卒中学会専門医・指導医、日本医師会認定産業医
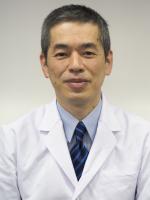
准教授
松嶋 康之(マツシマ
ヤスユキ):副診療科長
- 専門分野
リハビリテーション医学全般、脳卒中、神経筋疾患(ポリオ等)、摂食嚥下障害、産業医学、ボツリヌス治療
- 学会認定医等
-
- 日本リハビリテーション医学会認定臨床医・リハビリテーション科専門医・指導医、日本医師会認定産業医、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、労働衛生コンサルタント(保健衛生)

講師
伊藤 英明(イトウ
ヒデアキ):医局長
- 専門分野
脳卒中、産業医学、生化学的研究
- 学会認定医等
-
- 日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医・指導医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)

助教
堀 諒子(ホリ
リョウコ):外来医長
- 専門分野
リハビリテーション医学全般、脳卒中、高次脳機能障害
- 学会認定医等
-
- 日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
助教
尾﨑 文(オザキ アヤ)
- 専門分野
リハビリテーション医学全般、脳卒中、脊髄損傷
- 学会認定医等
-
- 日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
助教
田島 浩之(タシマ ヒロユキ):病棟医長
- 専門分野
リハビリテーション医学全般、脳卒中
- 学会認定医等
- 日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
- 認知症サポート医
助教
田中 亮(タナカ リョウ)
- 専門分野
リハビリテーション医学全般、脳卒中、嚥下、血友病
- 学会認定医等
-
日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
| 外来直通電話 093-691-7333 病棟直通電話 093-691-7350 |
(更新日:令和7年12月1日)