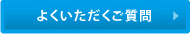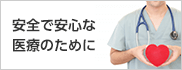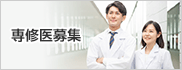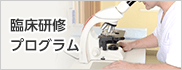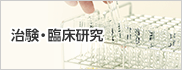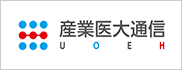事業効果
医療連携アドバイザーを養成したことによる効果
●業務改善は、職員の業務負担軽減につながる:
部門間の連携に関する問題の解決では、かかわるすべての部門が業務軽減となることはまれである。話し合いの中で、全体の流れや問題の根底となる原因を把握し、改善策を検討する。これには、かかわるすべての部門が改善策による業務内容や業務量増減の変化を理解したうえで、全体最適とするために互いに業務の折り合いをつけることとなる。このように、話し合いを重ねることで、部門(部分)最適を考えると共に、全体(病院・患者)最適を考える認識の変化となり、このことが業務改善をさらに進めていく要因となったと考える。2012年度から2024年度までに141件程度の業務改善を実施した。特に医師の業務が効率的になることにより、費用対効果の面だけでなく、医師の指示を受ける部門においても、医師の業務が軽減されることで、医師からより早くに効率的な指示が期待できるため、今後も積極的に医師の業務改善を医師の参画下に行うことが、ひいては職員の業務負担軽減につながると考える。
●相談しやすい環境の構築:
部門間の連携に関する問題解決に参加する医療連携アドバイザーは、自部門や他部門の現状や悩みを言語化して話し合うことができている。そのことが、親近感や仲間意識が生まれ、何か問題があった時にはすぐに相談でき連携が取りやすい環境となり、ひいては働きやすい環境へとつながると考える。

医療連携アドバイザー活動が病院運営に与える影響
●日本医療機能評価機構による病院機能評価:
2014年12月16日~17日に実施された病院機能評価の結果報告で、医療連携アドバイザー教育プログラムの取り組みが、【患者中心の医療の推進】の項目の「医療サービスの質改善に継続的に取り組んでいる」で、「S:秀でている」の評価であった。評価された点は、「2011年~2013年にかけて、文部科学省に採択された“医療連携アドバイザー養成プログラム”の取り組みを行い、他の部門や職種との連携を高めるために、各部門をまたぐ問題・課題の解決推進者の養成を行ったこと。
さらに、2014年以降も医療連携推進チームと名称を変更して次期医療連携アドバイザーの養成や同時に業務改善を実施すると共に、医療サービスの質改善に継続的に取り組んでいる。」という点であった。
2019年12月16日~18日に行われた病院機能評価で【継続的質改善のための取り組み】の項目の「業務の質改善に継続的に取り組んでいる」で「A:適切に行われている」と評価された。「連携アドバイザー要請プログラム」をさらに発展させ、「医療連携推進チーム」として「働き続けたい病院No.1」を目標に掲げ、各部門に任命された「医療連携アドバイザー」を中心に、課題ごとに担当する多職種チームを定め3か月で解決する方針で活動し、その成果を病院ホームページや通信レターとして病院内外に公評している点、医療法に基づく各種立入検査に適切に対応している点が評価された。病院機能評価は5年ごとの更新であり、今後も医療連携アドバイザー活動を継続することは、病院運営の改善に有用であると考える。
●医療法の改正でうたわれた「医療機関の勤務環境改善」とのつながり:
2014年6月に成立した「医療介護総合確保推進法」における医療法の改正により、同年10月1日以降、医療機関(医療法では「病院又は診療所の管理者」と規定)は、「医療スタッフの安全と健康は、患者の安全と健康を守る」という共通認識を医療機関で共有し、幅広いスタッフが参加する形で、PDCAサイクルにより計画的に医療従事者の勤務環境の改善に取り組む仕組み(医療勤務環境改善マネジメントシステム)を導入することが求められた。
また、医療勤務環境改善マネジメントシステムは、恒常的に医療従事者の勤務環境の改善や向上が図られるプロセスの実施を目指すものである。このことは医療連携アドバイザーの目指すビジョンである「働き続けたい病院NO1」の実現と活動方針の「一貫した患者支援を実現する連携」につながるものと考えられる。
今後、病院はPDCAサイクルを活用して計画的に勤務環境改善に向けた取り組みを行うための仕組み作りがよりいっそう推奨されるようになることから、これらの動きと合わせて院内の体制づくりに役立つと考える。
2015年に厚生労働省の「医療従年者の勤務環境改善の取組事例」として、いきいき働く医療機関サポートWeb(通称「いきサポ」※1)に本事業の医療連携アドバイザー(多職種連携の問題を改善する人)の育成プログラム開発と養成・実施で掲載された。
※1「いきサポ」トップページ( https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/)
●病院の理念の追加:
病院の理念
1.患者第一の医療を行います
2.科学的根拠に基づく安全かつ質の高い医療を提供します
3.人間愛に徹した優れた産業医と医療人を育てます
4.職種・職位・部門の垣根なく高い倫理観を持って互いの意見を尊重し、患者と職員の安全・安心に努めます
2020年に多職種、職位の上下関係なく、職員それぞれが節度を持ちながら相手と接し、率直なコミュニケーションを図れる環境をつくる事が目的で、今回新しい病院の理念として上記4が追加された。医療連携アドバイザー活動も職員が生き生きとして働き続ける職場にするために、部門間の問題解決をしている。
|
【お問い合わせ先】
医療連携アドバイザー |

|