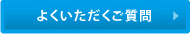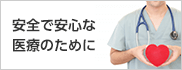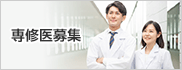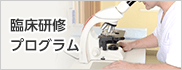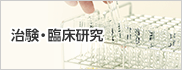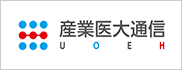リハビリテーション科(専修医)
1 診療科の特徴
当科では、リハビリテーション科専門医が脳卒中、外傷性脳損傷、脊髄損傷、切断、ポリオ後症候群などの疾患の評価、診断、治療を専門的に行っています。産業医科大学設立の趣旨に基づき、産業医学と関連が深いリハビリテーション医学の領域として「障害者の職場復帰」に重点をおいて取り組んでいることも当科の特徴のひとつです。
現在、同門会会員は100名を超え、わが国において最も規模が大きい講座のひとつと言えます。今後も当講座が我が国のリハビリテーション医学の中で主体的な役割を担い、社会的使命を果せるようにしたいと考えています。
2 専門医取得状況
- 日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医 8名
- 日本脳卒中学会専門医 3名
また、現在までに約75名の同門会会員がリハビリテーション科専門医となり、全国の大学、労災病院、地域リハビリテーション病院、企業(産業医として)に勤務しています。
3 研究活動
最新のロボット工学技術を取り入れた歩行支援ロボットやArm
Trainer,経頭蓋磁気刺激や直流電気刺激による訓練方法の開発、障害者の職場復帰、外傷性脳損傷の高次脳機能障害リハビリテーション、自動車運転適性評価、嚥下障害のリハビリテーション、懸垂式歩行器、カーボン装具,神経筋エコーや筋電図などの臨床神経生理研究など最新の臨床研究に取り組んでいます。
基礎研究においても、認知神経科学、臨床運動生理学などの領域に力を入れています。
4 関連学会
日本リハビリテーション医学会、日本脳卒中学会、日本義肢装具学会、日本脊髄障害医学会、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会、日本高次脳機能障害学会、日本職業災害医学会、日本臨床神経生理学会など
5 当診療科での修練のメリット
研修を通して、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医の受験資格を大部分クリアすることができます。
当科のように多数のリハビリテーション科専門医が常勤している施設はまれであり、リハビリテーション科専門医になるために必要な幅広い領域に関して手厚い指導を受けることができます。
臨床業務だけでなく、学会発表や論文の作成を通して論理的・科学的な思考を身につけることができます。
参考
・指導責任者・指導医
-
指導責任者:佐伯覚
指導医:松嶋康之、越智光宏、加藤徳明、伊藤英明、白石純一郎、蜂須賀明子、杉本香苗
(指導責任者、指導医は全てリハビリテーション科専門医)
・修練スケジュール
-
リハビリテーション科入院患者を主治医として受け持ち、専門医の指導のもとで対象疾患の診断・検査・治療、障害の診断とリハビリテーション課題立案、リハビリテーション処方作成、リハビリテーション・チームの管理運営、自宅・社会・職業復帰の手法を研修します。
義肢装具外来や高次脳機能外来、嚥下外来、ボツリヌス治療外来などの専門外来の見学、参加を行い、専門的な知識・経験を得ます。
神経生理学的検査(筋電図、誘発電位)、嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査、歩行解析などの臨床検査に参加し手技を身につけます。
・取得認定医・専門医制度
-
日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科専門医
(平成30年11月現在全国で2375名)
連 絡 先
- 担 当 者:松嶋 康之(教室幹事)
- 郵便番号:807-8555
- 住 所:北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
- 電話番号:093-691-7266
- FAX番号:093-691-3529
- E-mail:reha@mbox.med.uoeh-u.ac.jp