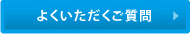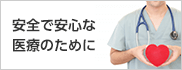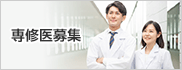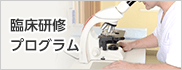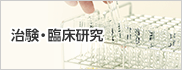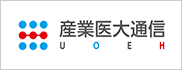小児科(専修医)
1 診療科の特徴
新生児期(症例によっては胎児期)から小児期全般(慢性疾患においては成人まで)のほぼ全ての内科疾患の研修ができる。外来研修では、一般的な感染症から各専門外来、救急救命などを体験できる。病棟研修では、NICUを含めた大学病院としての高度な診療に触れられる。
2 専門医取得状況
- 助教以上は全員日本小児科学会専門医(9名)、専修医も現在3名取得済み
- 日本血液学会専門医(指導医)1名
- 日本血液学会専門医 1名
- 日本神経学会専門医 1名
-
日本内分泌学会内分泌代謝専門医(教育責任者)1名
3 研究活動
【血液・腫瘍】
- 先天性出血性疾患(特に血友病)の基礎研究とQOL改善のための複数診療科に渡る包括的な診療
- 後天性出血性疾患(特に小児の播種性血管内凝固症候群およびビタミンK欠乏性出血症)の機序・治療・予防に関する研究
- 小児がん(急性白血病、小児悪性固形腫瘍)治療に関する全国規模のグループスタディや細胞レベルでの遺伝子発現の変化や変異の解析
- 新生児の輸血基準の検討
【神経】
- 種々の神経、筋疾患における臨床診断および遺伝子異常の解析
- 難治性てんかんにおける外科的治療
- 重度心身障害児の呼吸、栄養の確立指導
- 事象関連電位を用いた高次脳機能に関する研究
- 電気生理的手法を用いた小児の消化管運動の解析
【内分泌・糖尿病・肥満】
- 種々の内分泌・代謝疾患における遺伝子異常の解析
- 生活習慣病、脂肪細胞代謝に関わる臨床的および基礎的研究
- 脳内摂食関連ペプチド発現の発達や疾患での変動に関する研究
- 活性酸素・活性窒素種による酸化ストレスの研究
- 他に、消化器肝臓疾患、腎臓疾患、アレルギー疾患、心臓疾患にそれぞれの専門医が診療と研究にあたっている。
関連学会
日本小児科学会、日本産婦人科・新生児血液学会、日本新生児学会、日本小児血液学会、日本未熟児新生児学会、日本川崎病研究会、日本血液学会、日本血栓止血学会、日本臨床血液学会、日本輸血学会、日本ビタミン学会、日本小児神経学会、臨床神経生理学会、日本てんかん学会、日本小児救急学会、日本小児内分泌学会、日本小児栄養消化器病学会、日本小児脂質研究会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会、日本肥満学会、日本過酸化脂質フリ-ラジカル学会、九州学校保健学会など
当診療科での修練のメリット
救急から慢性疾患の小児科学各分野にわたって最先端で高度な医療に接することができ、小児科専門医のみならずサブスペシャリティーとしての専門医取得が出来る体制にある。また、大学院生として、小児科診療に関わりながら博士号取得も可能である。
参考
・指導責任者・指導医
-
指導責任者:白幡 聡
指導医:下野昌幸、土橋一重、山本幸代、酒井道生、宮地良介、佐藤哲司、高橋大二郎、久保和泰
・修練スケジュール
-
1年目は主に大学、小児科一般病棟での研修。
2年目以降は上記に加え、大学NICUおよび周辺の関連施設での研修。
・取得認定医・専門医制度
- 小児科専門医、日本血液学会専門医、日本神経学会専門医、日本内分泌学会専門医、日本周産期・新生児医学会専門医などの取得が可能
連 絡 先
- 担 当 者:土橋 一重
- 郵便番号:807-8555
- 住 所:北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
- 電話番号:093-691-7254
- FAX番号:093-691-9338
- E-mail:kdobashi@med.uoeh-u.ac.jp