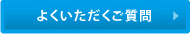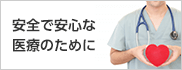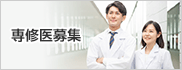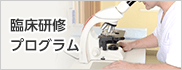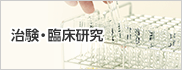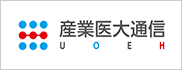膀胱がん
泌尿器科ホームページはこちらへ
病気について
膀胱がんは、尿をためる臓器である膀胱の粘膜(尿路上皮)より発生する悪性腫瘍です。症状としては痛みなどの排尿症状を伴わない血尿が特徴的で、喫煙者が非喫煙者に比べて4倍膀胱がんになりやすいとされています。多発および再発する確率が高いこと、また排尿は日常生活の質に直接関わるため、泌尿器科診療において重要な病気のひとつです。
診断について
膀胱がんが疑われる場合にもっとも重要な検査は膀胱を直接観察する内視鏡検査です。当科を受診される方は基本的に全員に受けてもらう検査となっています。その他、尿の細胞検査、尿路造影検査、進行程度に応じてCT・MRI・骨シンチ検査などの画像検査を追加し、病気の広がりや転移の有無を判断します。
手術療法
外科的治療
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)
膀胱がんの確定診断と治療を兼ねてまず行われる手術で、内視鏡治療になります。
切除した腫瘍の深達度(腫瘍の根の深さ)によって早期がんであるのか進行がんであるのか判断します。早期がんである場合には、再発抑制を目指す補助療法として後述する膀胱内注入療法を行います。
膀胱全摘除術(鏡視下治療)
TURBT後、進行がんの診断となった場合、膀胱全摘除術(男性は前立腺と尿道の合併切除、女性は子宮と卵巣および膣壁の合併切除)の拡大手術を行い、根治を目指します。非常に大きな規模の手術ですので、当科では2019年9月よりロボット(ダビンチ)支援下の手術を中心として行い、できるだけ患者さんの負担軽減に努めています。
尿路変向術
尿をためる臓器である膀胱を全摘出した場合、尿を体外へ排出する通り道を作らなければなりません。膀胱全摘除術を行う患者さんは同時に尿路変向術も行います。当科では、病気の状態および患者さんの生活観に応じて回腸導管(小腸の一部を尿路ストーマとして体外へだします)、代用膀胱(小腸の一部を膀胱のような袋状の形に作り、尿路ストーマを作らず尿道から直接排尿します)、尿管皮膚ろう(腸を利用せず、直接尿管をストーマとして体外へだします)のいずれかの方法で尿路排出経路を作っています。これらの尿路変向術においても当院ではロボット支援手術を積極的に行い、体の中だけで完結する手術を達成することで、通常よりも早い術後回復につなげることができています。
内視鏡的治療
該当なし
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
前述の膀胱全摘除術は非常に大きな規模の手術ですので、持病や年齢や体の状態によっては手術が困難な場合があります。その場合の代替治療として、当科では放射線科と合同で動注化学放射線療法(血管内カテーテル治療で膀胱がんを栄養する血管へ抗がん剤の注入と膀胱への放射線照射を併用する治療法)も積極的に行っています。
薬物療法
抗がん剤
他臓器への転移や膀胱全摘除術後の再発がある場合は、抗がん剤による全身化学療法を行います。転移のある症例の場合、抗がん剤の投与が従来の標準治療となります。当院では主にシスプラチン(カルボプラチン)という白金製剤を中心に数種類の抗がん剤を投与します(GC療法:ゲムシタビン・シスプラチン/ Dose-dense MVAC療法:メソトレキセート・ビンクリスチン・ドキソルビシン・シスプラチン)。
なお、膀胱全摘除術の治療効果を高めるために、手術の前や手術の後にこれらの抗がん剤による補助化学療法を行うこともあります。
ホルモン(内分泌)薬
該当なし
分子標的薬
該当なし
免疫チェックポイント阻害薬
近年、免疫の働きを利用しがん細胞を排除する「がん免疫療法」が話題となっており、免疫チェックポイント阻害薬もその一つです。この治療法は様々な癌腫でその有効性が期待され、膀胱がんにおいて3種類の薬剤が保険適用となっています。抗がん剤の化学療法の効果を持続させるアベルマブ維持療法、抗がん剤の化学療法後進行した場合の二次治療ペムブロリズマブ療法、手術後の再発抑制効果のあるニボルマブ補助療法を当院では早期に導入し豊富な診療経験を有しています。
その他
膀胱内注入療法(早期がん)
TURBTを行って早期がんの診断となった患者さんに、膀胱内の再発抑制を目指す補助療法として外来通院で行っています。当科では抗がん剤(エピルビシン)や、特に再発リスクが高い場合には結核の予防薬として知られるBCGを注入する方法を広く行っています。
抗体薬物複合体±免疫チェックポイント阻害薬(進行がん)
前述の抗がん剤による化学療法および免疫チェックポイント阻害薬に対して抵抗性となり進行した場合、新たながん治療薬である抗体薬物複合体(ADC)のエンホルツマブ・ベドチン(パドセブ)が2021年11月保険適用となりました。当院では積極的にこの薬物治療をおこない、西日本でも有数の診療実績を有しています。さらに、2024年9月にこのエンホルツマブ・ベドチン と免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブ併用療法が登場し、手術できないまたは転移のある未治療患者さん(従来の抗がん剤による一次化学療法と同じ位置づけ)に保険適用となりました。当院ではいち早くこの新規薬物療法を導入し診療をおこなっています。
放射線療法
膀胱温存療法
他臓器への転移がなく根治治療の適応があるものの年齢や体の状態によって手術が難しい場合、又は手術を希望されない場合の治療選択肢として膀胱温存療法があります。
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)で可能な限り腫瘍を切除した後に、放射線治療とシスプラチン等の抗がん剤治療を同時に行う化学放射線療法を行います。これは膀胱を温存し根治を目指す体への負担が少ない治療法です。
抗がん剤の投与法として、より高い治療効果を目指して動注化学療法を行う場合があります。動注は、膀胱がんを栄養する血管にカテーテルを直接挿入し、高濃度の抗がん剤を腫瘍に投与します。さらに、当院では、放射線治療の治療効果を高める目的の温熱療法の併用が選択可能です。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
治療した膀胱や骨盤リンパ節の再発、または少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合 (オリゴ転移) に、薬物療法に加えて救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、肺や肝臓の転移、腹部・縦隔・頸部リンパ節転移、骨転移などが対象となります。治療した腫瘍の高い制御効果が期待できます。
脳転移に対する放射線治療
脳転移を生じた場合に放射線治療が有効です。当院では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いた定位放射線治療(ピンポイント照射)が可能です。患者さんに負担の少ない短い治療時間で、脳転移の高い制御効果が期待できます。
緩和的放射線治療
膀胱温存療法が適応とならない場合や他の臓器へ転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。膀胱がんからの血尿や排尿障害の改善、骨転移に伴う疼痛の鎮痛といった症状緩和に有効です。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。通院が困難な方は、放射線治療科で入院治療も対応させて頂きます。
温熱療法 (ハイパーサーミア)
当科では、膀胱がんに対して放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。パッド内の液体を還流させ、皮膚表面の熱感や痛みを抑えます。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
当科ではこれまで非常に多くの患者さんの治療を行ってきました。その実績を踏まえて、患者さんの状態に合わせた最適な治療を提示できるよう努めていきます。
産業医科大学 医学部 泌尿器科学講座
産業医科大学病院 放射線治療科
https://www.radiationoncol.com/