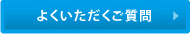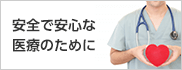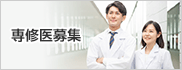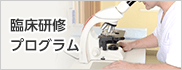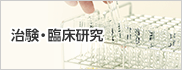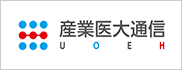白血病
血液内科ホームページはこちらへ
病気について
治療が急速に進歩し、薬(化学療法)だけで治るがんの一つで、白血病は治る病気となりました。血液中には白血球・赤血球・血小板という血球があり、白血病は骨髄にいる造血幹細胞(血液を作る元となる細胞)もしくは、それから少し成熟した前駆細胞(血液の前段階の細胞)ががん化したと考えられています。がん化した白血病細胞は骨髄で分裂し、そのうち血液として循環血液でも増え、正常の血液を作れなくし、貧血・白血球減少・血小板減少で、動悸・倦怠感・発熱・感染・出血などの体の不調が出現します。がん細胞は他の臓器に入り込み(転移・浸潤)、その臓器の症状を起こします。白血病は病気の性質によって、進行が早く症状の強い急性骨髄性白血病・急性リンパ性白血病と進行が遅く症状の出にくい慢性骨髄性白血病・慢性リンパ性白血病に分けられますが、正確には数十種類の白血病があり、それぞれ治療や予後が違います。原因として、放射能被ばくはもちろん、化学物質への暴露、特殊なウイルス感染が知られています。日本の推定罹患率は推定人口10万人あたり10人前後で、男女差なく小児期から若年成人にも発症しますが、最近は高齢化に伴い高齢者の白血病が増えつつあります。
また、白血病細胞が増える前で骨髄細胞の異常が目立つ状態を骨髄異形成症候群と言います。特に70歳以降の高齢者に多く、造血(血液をつくること)ができなくなり、白血病と同様に、貧血・白血球減少・血小板減少で、動悸・倦怠感・発熱・感染・出血などが出現します。
診断について
最も重要な検査はおしりの骨(腸骨)からの骨髄診断です。採られた骨髄は染色の上、顕微鏡検査が実施されます。さらに、染色体・遺伝子検査やフローサイトメトリー法という採取した腫瘍細胞にレーザー光を当てて、腫瘍細胞の性質を解析します。これら多角的解析によって、確定診断を行っていくことが重要です。特に、九州ではHTLV-Iウイルス感染にて発症する成人T細胞性白血病・リンパ腫の患者さんが多く存在し、組織や血液のHTLV-Iの検査が必要な場合があります。一方、末梢血や骨髄検査のほか、画像として超音波(エコー)検査、CT、MRIが用いられます。また、治療後には骨髄検査で、遺伝子検査やフローサイトメトリー法が再度行われ、体内に残った少数の白血病(微小残存病変:MRD)の有無を測定することで、治療の方針を決定できるようになりました。MRD陽性・陰性は寛解判定や移植適応に極めて重要です。
外科的手術
該当なし
内視鏡的治療
該当なし
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
該当なし
薬物療法
抗がん薬
発症時、腫瘍(白血病)細胞は少なくとも患者体内に1兆個は存在すると考えられています。腫瘍細胞を限りなくゼロに近づける必要があります。基本は抗がん薬による多剤併用強力治療で、病初期に寛解導入療法としてシタラビン、アントラサイクリン、ビンカアルカロイド・L-アスパラやシクロホスファミドなど多くの種類の抗がん薬によって腫瘍量を早期に1000分の1以下に減少させることが重要です。これに成功すると、正常な血液は回復し病状は改善します。これを寛解と言います。寛解後は、地固め療法、強化維持療法を順次行っていき、腫瘍細胞の根絶を目指します。
支持療法として、無菌管理、赤血球や血小板の輸血、抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、G-CSF製剤などの感染症やその他の内臓臓器合併症への対策が数段効果的となり、強い抗がん療法を行っても重い合併症を起こさず、十分量の抗がん薬が投与できるようになっています。
ホルモン(内分泌)薬
該当なし
分子標的薬
がん治療における創薬として、白血病に特徴的な分子を標的とした有名なものに、BCR・ABL融合遺伝子陽性の慢性骨髄性白血病や急性リンパ性白血病に対するBCR・ABL特異的チロシンリン酸化酵素阻害薬(イマチニブ・ダサチニブ・ニロチニブ・ボスチニブ・ポナチニブ・アシミニブ)や急性前骨髄球性白血病に対するレチノイン酸(活性化したビタミンA)があり、内服薬(飲み薬)であり飲むことよって80から90%の患者さんが寛解となります。ただし、これらはBCR・ABLなどの標的となる特異的な異常を持った白血病にしか効きません。最近、新たな標的としてFLT3遺伝子変異陽性の白血病に対してはFLT3阻害薬であるギルテリチニブ・キザルチニブ内服が使えます。また、慢性リンパ性白血病には経口薬のイブルチニブや点滴薬ベンダムスチンが有効です。近年、急性骨髄性白血病に対して、内服薬であるベネトクラクスが使用できるようになりました。
一方、高齢者が多い骨髄異形成症候群に対しては、抗がん薬治療よりもむしろ造血を回復させる分子標的薬であるエリスロポエチンやアザシチジンの注射やレナリドマイド内服が有効です。しかし、若い方では白血病と同じ抗がん薬を使うこともあります。
免疫チェックポイント阻害薬
該当なし
造血幹細胞移植
他の人から移植を行う同種造血幹細胞移植として、骨髄移植、現在では他に末梢血幹細胞移植や臍帯血移植も行われています。血縁間(患者と血のつながったドナー)以外に、非血縁間(患者と血のつながっていない他人)に関してはバンクが整備され、血液内科には幹細胞専任のスタッフや移植認定医が従事しており、コーデイネートが可能です。
原理は患者の病気になった造血幹細胞を取り除き、健康なドナーから提供された造血幹細胞に入れ替えることです。抗がん薬や分子標的薬をしても腫瘍細胞が残ってしまった時、同種造血幹細胞移植の適応となります。しかし、腫瘍細胞が多すぎる場合は移植をしてもすぐに再発することが判っており残存する腫瘍は少ない場合とされています。しかし、同種移植を受けると拒絶反応であるGVHD反応が皮膚、胃腸や肝臓に生じ、また、病気の造血幹細胞を取り除くために大量の抗がん薬や放射線照射を必要とします。このため、同種造血幹細胞移植は生命に関わるハイリスク治療と位置づけられています。さらに、高齢者白血病の予後は不良で打開するために、移植に関してもミニ移植という患者への負担を軽減し高齢者でも実施可能な移植方法があります。
血縁間移植でのドナーは、両親からの白血球型式であるHLAが遺伝するため兄弟姉妹が最適です。しかし、兄弟姉妹間でHLAが一致する確率は25%(兄弟姉妹間の赤血球型ABOの一致率を同じ)です。このため、骨髄や臍帯血バンクやHLAが合わない血縁ドナーからも可能な移植方法が登場しています。
放射線治療
移植前全身照射
移植を行う前の処置として全身への放射線照射(全身照射)を行います。全身照射は、全身の腫瘍細胞を減少させると同時に、免疫抑制状態とすることでドナーからの造血幹細胞を受け入れやすくする効果があります。移植の直前に1~3日間かけて行います。
緩和的放射線治療
白血病の脳など中枢神経への再発、脾臓浸潤に伴う脾腫、また白血病細胞が腫瘤を形成している場合などで、症状緩和・生活の質の改善を目的とした緩和的放射線治療を行います。緩和的放射線治療では、照射する放射線の線量が少なく副作用はごく軽微です。
放射線治療科外来では治療内容を専門医からより詳しくご説明しています。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
当科では15名程度の血液内科の化学療法や移植を専門とする医師が常勤医として勤務しています。移植コーディネーターもいます。そのため、チーム医療や専門性の高い治療が入院・外来で可能となっています。
産業医科大学病院 血液内科
https://can-enter.sakura.ne.jp/kagakuryoho/%e8%a8%ba%e7%99%82
産業医科大学病院 放射線治療科