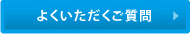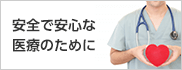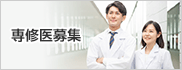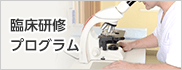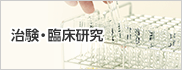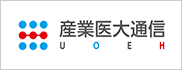多発性骨髄腫
血液内科ホームページはこちらへ
病気について
免疫グロブリンである抗体を作る細胞を形質細胞と言い、形質細胞は骨髄にいて、これらががん化することが多発性骨髄腫です。多発性骨髄腫は70から80歳代の高齢者に多く、高齢化に伴い増加しています。多発性骨髄腫の推定罹患率は10万人中5人程度であり、年齢と共に増加する傾向にあり、男女差はありません。免疫グロブリンは2本のH鎖と2本のL鎖から構成され、一般的に抗体として知られています。H(ヘビー)鎖にはγ・α・μ・δ・εが、L(ライト)鎖にはκ・λがあり、IgG・IgA・IgM・IgD・IgEとなります。
多発性骨髄腫は骨髄で増えるため骨髄が障害され、血液が作れなくなり、貧血になります。さらに、がん化した形質細胞は異常な抗体(M蛋白)をつくり血中に放出します。これらは本来の抗体として働かず、異常蛋白として腎臓(遠位尿細管や集合管)に円柱(塊)を作り、腎の障害や神経でも同様に障害します。80%に骨融解(骨が溶ける)も生じ、高カルシウム血症・骨粗鬆・骨折を呈します。しかし、無症候性と言って全く症状のない場合は、骨髄腫と診断しても治療せず様子を外来でみることもあります。
一方、多発性骨髄腫ではない健常人でも1%に少量のM蛋白が陽性で、70歳以上では3%、80歳以上では10%にみられ、良性M蛋白血症;monoclonal
gammopathy
of
undetermined
significance
(MGUS)と呼ばれます。但し、将来20から30%は多発性骨髄腫に移行し注意が必要です。
診断について
採血で貧血を中心とした異常がみられ、過粘稠度症候群と言う血液の粘稠度が上がり、赤血球の連銭形成(連なった様子)がみられます。骨髄検査では異常な形質細胞がみられ、電気泳動・免疫電気泳動・免疫固定法で、異常なM蛋白がみられます。尿ではBence
Jones蛋白がみられます。L(ライト)鎖であるBence
Jones蛋白は尿中に検出され、酢酸にてPH3~4、56度で沈澱し、100度で再溶解する特徴があります。X線・MRI・PETやCTでは骨の解ける骨融解がみられ、脊髄障害などが圧迫による神経障害も起こります。
10%にコンゴ赤染色に染まる物質の沈着するアミロイドーシスが合併しλタイプに多いです。
治療について(手術療法)
該当なし
内視鏡的治療
該当なし
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
該当なし
薬物療法
抗がん薬
分子標的薬が世界的な標準治療で、従来の抗がん薬は分子標的薬が使えない方や高齢者などに対して、MP療法(メルファラン、プレドニン)またはCP療法(シクロホスファミド、プレドニン)があります。プレドニン・メルファラン・シクロホスファミドには経口・注射の両方があります。
ホルモン(内分泌)薬
該当なし
分子標的薬
治療は症状がある方が対象となり、無症状の場合治療をせず経過をみることが勧められています。標準治療としては、分子標的薬をステロイドホルモンとともに使用する寛解導入療法を行います。薬には、免疫調整薬(レナリドマイド、サリドマイド、ポマリドマイド)・プロテアゾーム阻害薬(ボルテゾミブ・カルフィゾミブ・イキサゾミブ)・抗体製剤(ダラツズマブ・イサツキシマブ・エルラナタマブ・エロツズマブ)があります。免疫調整薬のすべてとイキサゾミブは経口で、その他は注射薬です。外来および入院で使うことができます。近年では、薬の併用が高い治療効果を示しています。特に二重特異性抗体の有効性は期待されています。
支持療法として、骨病変や高カルシウム血症があれば、骨の吸収を防ぐゾレドロン酸やデノスマブが併用されます。他、赤血球や血小板の輸血、抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、G-CSF製剤などの感染症やその他の内臓合併症への対策がなされ、重い合併症を起こさず、十分量の薬が投与できるようになっています。
類縁疾患として、原発性マクログロブリン血症・全身性アミロイドーシス・POEMS症候群があり、多発性骨髄腫に準じて治療されます。
免疫チェックポイント阻害薬
該当なし
造血幹細胞移植
腫瘍の制御に成功した後、自家末梢血幹細胞移植が適応されます。患者自身の造血幹細胞(血液の元となる細胞)を末梢静脈血から採取し、凍結保存します。採取は血液内科の幹細胞専任のスタッフや移植認定医が従事します。
採取できたら、患者には無菌室に入室して頂き、前処置と言われるメルファランの大量療法がおこなわれます。前処置後に、保存しておいた末梢血造血幹細胞が患者に戻されます。その後、血球が元に戻るまで、患者は無菌管理されます。ただし、これら強い抗がん剤治療が行われるため、神経系・循環系を含め内臓機能に重い負担となるので、内臓機能に問題がない方が対象となる治療法です。
放射線治療
多発性骨髄腫における放射線治療は、症状緩和のための緩和的な放射線治療が主体となります。骨病変により引き起こされる疼痛や神経症状の改善や、骨折を予防する目的に行います。治療効果は高く、鎮痛効果や病変の増大抑制を高率に得られます。緩和的放射線治療で用いる放射線量は少なく、副作用はごく軽微です。
骨髄腫の病変が1か所の骨のみに限局している孤立性形質細胞腫や、骨以外の場所に発生した髄外形質細胞腫では、根治的な放射線治療を行います。治療効果は高く、90%以上の確率で治療した病変の制御が可能です。
放射線治療科外来では上記治療の内容を専門医からより詳しくご説明しています。
セカンドオピニオンの受け入れ
(
可
)
患者さんにメッセージ
当科では15名程度の血液内科の化学療法や移植を専門とする医師が常勤医として勤務しています。移植コーディネーターもいます。そのため、チーム医療や専門性の高い治療が外来・入院で可能となっています。
産業医科大学病院 血液内科
https://can-enter.sakura.ne.jp/kagakuryoho/%e8%a8%ba%e7%99%82
産業医科大学病院 放射線治療科
https://www.radiationoncol.com/