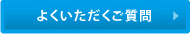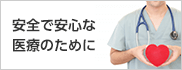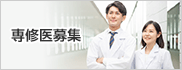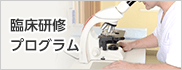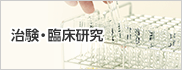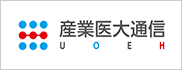悪性リンパ腫
血液内科ホームページはこちらへ
病気について
白血球の一部であるリンパ球が悪性化する病気で、年間発症率は10万人当たり20人程度で、血液腫瘍では最も多い。リンパ球は体の免疫を担う最も重要な細胞で、B細胞・T細胞・NK細胞に分類されます。ほとんどが徐々に大きくなるリンパ節の腫れに気づかれて診断に至ります。リンパ節の腫れ以外には、発熱・体重減少・寝汗が30%程度の方にみられます。悪性リンパ腫には多彩な種類がありますが、ホジキンリンパ腫と非ホジキンリンパ腫の2つに大別され、日本では後者が80から90%を占めます。
さらに、非ホジキンリンパ腫にはB細胞性、T細胞性と少ないですがNK細胞性があります。病気は、全身のリンパ節を中心に広がりますが、リンパ節以外にもしばしばみられ、胃腸・肺・肝臓・皮膚・神経など全身の臓器にも発生します。ステージはリンパ節の病変が横隔膜の上下どちらか一方にかたまっている場合は限局期とし、横隔膜上下に広がっている場合やリンパ節以外の臓器に広がっている場合を進行期とします。多く種類の悪性リンパ腫があるために、患者さんごとに治療なしで年単位に経過観察できるものや胃ピロリ菌を除菌で良いものから、週や月単位で急激に進行するものまで様々です。原因として、一部のリンパ腫にピロリ菌やウイルス感染や長期わたる炎症・免疫不全が証明されるケースがあります。
診断について
悪性リンパ腫を診断するうえで、最も重要な検査は組織診断です。そのためには、リンパ節生検が行われます。採られた組織は当院では病理診断科によって染色の上、顕微鏡検査が実施されます。さらに、血液内科では末梢血や骨髄血の検鏡、染色体・遺伝子検査やフローサイトメトリー法という腫瘍細胞にレーザー光を当てて、腫瘍細胞の性質を解析します。これら血液内科医と病理医の多角的解析によって、確定診断を行っていくことが重要です。特に、九州ではHTLV-Iウイルス感染にて発症する成人T細胞性白血病・リンパ腫(ATLL)の患者さんが多く存在し、組織や血液のHTLV-Iの検査が必要な場合があります。
一方、病気の広がりを見るには、末梢血や骨髄検査のほか、画像として超音波(エコー)検査、CT、MRIが用いられ、最近ではPET検査が有用性です。悪性リンパ腫は他の癌と比べてPET陽性率が高く、ステージ判定や治療有効性判定にも広く利用されています。
手術療法
該当なし
内視鏡的治療
該当なし
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
該当なし
薬物療法
抗がん薬
悪性リンパ腫の治療成績は年々確実に向上しています。通常、悪性リンパ腫は抗がん剤治療がよく効く腫瘍として知られています。すなわち、数少ない抗がん剤治療だけで治癒可能な悪性腫瘍の一つで、進行期でも十分に治癒可能です。
現在、ホジキンリンパ腫にはABVD療法(アドリアマイシン、ブレオマイシン、ビンブラスチン、ダカルバジン)・非ホジキンリンパ腫にはCHOP療法(シクロホスファミド、アドリアマイシン、オンコビン、プレドニゾロン)の抗がん剤多剤併用したものが標準治療で当院でも採用しています。一方、改良したレジメンも数多くエビデンスを証明されており、患者さんの年齢や臓器障害に応じて、治療強度を強めたり弱めたりし、最適な治療法を選択していきます。特に、非ホジキンリンパ腫の一つである濾胞性リンパ腫ではベンダムスチンという点滴薬が知られています。
支持療法としても、赤血球や血小板の輸血、抗菌薬、抗真菌薬、抗ウイルス薬、G-CSF製剤などの感染症やその他の内臓臓器合併症への対策がなされ、重い合併症を起こさず、十分量の薬が投与できるようになっています。
ホルモン(内分泌)薬
該当なし
分子標的薬
腫瘍細胞がCD20という抗原に陽性であれば(B細胞性)抗CD20抗体リツキシマブという抗体療法が併用され、濾胞性リンパ腫には加えて新しく開発されたオビヌツズマブという抗CD20抗体も有効です。その他、CD30陽性のホジキンリンパ腫や非ホジキンリンパ腫にはブレンツキシマブベドチンのような抗癌剤が結合した抗CD30抗体製剤が使えるようになり、従来の抗がん剤との併用が有効です。その他、ATLを含むT細胞性非ホジキンリンパ腫に対しては抗CCR4抗体であるモガムリズマブが有効です。B細胞リンパ腫に近年ポラツズマブベドチンも使用可能となりました。
難治性末梢性T細胞性リンパ腫には、ヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤であるロミデプシン、葉酸拮抗薬であるプララトレキサート、PNP阻害剤フォロデシンもあります。特にエプコリタマブなどの二重特異性抗体の有効性は期待されています。
これらの抗体療法をはじめとする分子標的薬は単独もしくは抗がん剤と併用して投与されます。このように、様々な抗がん剤と抗体療法の組み合わせがあり、初回治療を入院で行った後は、多くの方が外来で投与継続されています。
免疫チェックポイント阻害薬
再発・難治性ホジキンリンパ腫にニボルマブ・ペムブロリズマブなどの抗PD-1抗体が使用できます。ただし、若い方では移植後の拒絶反応を増悪させる傾向があり、使用は慎重となります。
造血幹細胞移植
通常、再発した場合悪性リンパ腫に対しては自家末梢血幹細胞移植が適応されます。悪性リンパ腫再発した場合、まずサルベージ療法と言われる強い抗がん剤治療で腫瘍をコントールします。腫瘍の制御に成功した後、患者自身の造血幹細胞(血液の元となる細胞)を末梢静脈血から採取し、凍結保存します。採取は血液内科には幹細胞専任のスタッフや移植認定医が従事しています。
採取できたら、患者には無菌室に入室して頂き、前処置と言われる複数の抗がん剤の大量療法がおこなわれ、悪性リンパ腫の根治を目指します。前処置後に、保存しておいた末梢血造血幹細胞が患者に戻されます。その後、血球が元に戻るまで、患者は無菌管理されます。ただし、これら強い抗がん剤治療が行われるため、神経系・循環系を含め内臓機能に重い負担となるので、年齢が若い内臓機能に問題がない方が対象となる治療法です。
放射線治療
根治的放射線治療
ホジキンリンパ腫
病変が限局している低-中リスクのホジキンリンパ腫では、化学療法を行った後にもともと腫瘍のあった場所や、化学療法後も残存している腫瘍に対して根治・再発予防を目的に放射線治療を行います。進行期の高リスクホジキンリンパ腫では、化学療法後を行った後に特に大きな腫瘍があった場所や残存している腫瘍に対して根治・再発予防を目的に放射線治療を追加します。
非ホジキンリンパ腫
ⅰ インドレント非ホジキンリンパ腫(濾胞性リンパ腫グレードI・IIなど)
濾胞性リンパ腫グレードI・IIを代表とする限局期のインドレント非ホジキンリンパ腫では、多くの場合は放射線治療のみで長期間の局所制御を得ることが可能です。しかし、放射線治療の範囲外からの再発や遅発性再発も少なくなく、場合によっては化学療法の追加も検討する必要があります。
ⅱ アグレッシブ非ホジキンリンパ腫(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫、濾胞性リンパ腫グレードⅢ、マントルリンパ腫、抹消性T細胞リンパ腫、未分化大細胞リンパ腫など)
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に代表される限局期のアグレッシブ非ホジキンリンパ腫では、化学療法後の地固め療法としてもともと腫瘍のあった場所や、あるいは化学療法後に残存してしまった腫瘍に対して、根治・再発予防を目的とした放射線治療を行います。進行期のアグレッシブリンパ腫に対しては化学療法後の残存病変や巨大病巣への救済治療として放射線治療を追加する場合があります。
上記リンパ腫は基本的に放射線治療の感受性良好で、高い確率で局所制御が期待できます。
ⅲ 成人T細胞白血病・リンパ腫
成人T細胞白血病・リンパ腫は局所の放射線感受性は高いものの、白血病化しやすいため難治性です。多くの場合、成人T細胞白血病・リンパ腫については後述の緩和的放射線治療が主体となります。
節外性リンパ腫
ⅰ 中枢神経系リンパ腫
60歳以上の患者さんの中枢神経系リンパ腫では、化学療法(メソトレキサート)と脳への放射線治療を併用することで、白質脳症と呼ばれる副作用を高率に生じるため、化学療法で寛解が得られている場合には放射線治療は行いません。若年の患者さんや、化学療法後に残存・再発を来した場合には脳全体に放射線を照射する全脳照射を行います。
ⅱ 乳房原発リンパ腫
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の場合は化学療法後に、乳房全体および残存腫瘍に根治・再発予防目的の放射線治療を>追加します。限局期のMALTリンパ腫の場合は乳房全体への放射線治療のみで治癒が可能です。
ⅲ 消化管原発リンパ腫
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の場合は化学療法後に、発生した消化管および残存腫瘍に根治・再発予防目的の放射線治療を追加します。胃に発生するMALTリンパ腫ではヘリコバクター・ピロリ菌感染を原因とすることが多く、除菌治療が第一選択となります。ピロリ菌の除菌後も腫瘍細胞が残存する場合は胃全体に放射線治療を行います。胃MALTリンパ腫の放射線治療による局所制御率は90%を超えます。
ⅳ 鼻腔原発NK/Tリンパ腫
鼻腔原発NK/Tリンパ腫は化学療法および放射線治療に抵抗性であり、限局期の根治治療では化学療法と放射線治療の同時併用が必要となります。放射線治療は原発腫瘍、両側鼻腔全体隣接する口蓋および副鼻腔を照射野に含む必要があり、照射線量も多くなります。副作用として、粘膜炎や唾液分泌障害、骨壊死などが生じる可能性があります。
全身照射
骨髄移植の前に行う全身照射は、全身の腫瘍細胞を減少させると同時に、免疫抑制状態とすることでドナーからの造血幹細胞を受け入れやすくする効果があります。移植前に行われる化学療法の補助的な位置づけで行われる治療です。全身照射は骨髄移植の直前に1-3日間かけて行います。
緩和的放射線治療
進行期や再発した悪性リンパ腫に対して、腫瘍に伴う疼痛の緩和、出血の止血、神経症状の改善といった症状緩和を目的とした緩和的放射線治療を行います。緩和的放射線治療で用いる放射線量は少なく、副作用は軽微です。悪性リンパ腫は放射線が効きやすいタイプの腫瘍であり、効果的な症状緩和を得られる場合が多いです。
温熱療法 (ハイパーサーミア)
当院では、難治性や再発性の悪性リンパ腫に対して、放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める目的で温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
放射線治療科外来では上記治療の内容を専門医からより詳しくご説明しています。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
当科では15名程度の血液内科の化学療法や移植を専門とする医師が常勤医として勤務しています。移植コーディネーターもいます。そのため、チーム医療や専門性の高い治療が外来・入院で可能となっています。
産業医科大学病院 血液内科
https://can-enter.sakura.ne.jp/kagakuryoho/%e8%a8%ba%e7%99%82
産業医科大学病院 放射線治療科