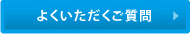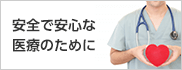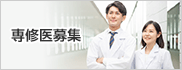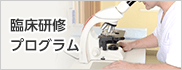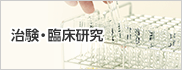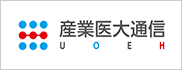肺がん
病気について(概要、疫学的なものも含めて)
日本では年間約99万人が「がん」と診断されていますが、中でも肺がんは、年間に約11万人もの人が診断され、約8万人がお亡くなりになる、がんの中で最も死亡者数が多い病気です(全国がん登録2014-2017年)。肺がんは、肺や気管支から発生する悪性(あくせい)腫瘍(しゅよう)で、男女ともに罹患率(りかんりつ)(発症する割合)が高く、治療が難しいがんの一つです。肺がんの原因として「喫煙」が挙げられますが、他にも受動喫煙、環境、食生活、放射線、薬品、粉じんや石綿などが挙げられます。タバコには発がん物質が含まれており、肺や気管支が繰り返し発がん物質に曝(さら)されることによって細胞に遺伝子変異(DNAに小さな損傷)が起こり、その遺伝子変異が積み重なってがんが発症します。
肺がんは、健診(検診)のレントゲンで見つかる場合や、せきやたんなどの呼吸器症状で医療機関を受診して見つかる場合などがあります。早期ではほとんどの場合が無症状ですが、進行期でも症状がでない場合もあります。症状を伴う場合は、肺がんの種類、発生部位、病状の進行によって、せき、たん、発熱、血たん、呼吸困難感、胸痛などの呼吸器症状や体重減少や全身倦怠感(体がだるい)などの症状が現れます。
肺がんの種類には大きく分けて①小細胞肺がん、②非小細胞肺がんがあり、非小細胞肺がんは、さらに、腺(せん)がん、扁平上皮(へんぺいじょうひ)がん、大細胞がんなどに細かく分類されます。肺がんの種類や進行度、患者さんの体力などを考慮し、手術、放射線療法、薬物療法、またはそれらを組み合わせた治療法を選択します。
診断について
レントゲンやCTなどの画像検査で肺がんが疑われた場合に診断するためには、肺癌が疑われる箇所から細胞や組織(細胞の塊)を採取する必要があります。診断する方法の中で、患者さんに負担の少ない検査として、喀痰細胞診(かくたんさいぼうしん)検査(たんのなかの「細胞」を調べる検査)がありますが、治療戦略を考える上では、細胞の塊である「組織」を採取することが重要となります。当院では、呼吸器内科、呼吸器・胸部外科、放射線科が協力し、気管支(きかんし)鏡(きょう)検査(けんさ)や外科的肺生検(げかてきはいせいけん)、CTガイド下肺生検などにより、治療法の選択に必要な十分な量の組織を採取し、適切な診断・治療方針の決定を行うことに努めています。
気管支鏡検査は、当院で診断のために最も行われる検査方法です。具体的にはレントゲンやCT検査で異常を指摘された病変に対して、検査前にナビゲーションシステムを使用しどこに病変があるのかを同定した後、検査中には透視(リアルタイムでのレントゲン画面)で病変の場所を確認しながら、気管支鏡や超音波気管支鏡を用いて組織を採取します。当院では鎮静(ちんせい)薬(やく)やせき止めなどを適切に使用することで、苦痛の少ない気管支鏡検査を心掛けています。また、胸水(きょうすい)貯留および胸膜(きょうまく)の病気に対しては、セミフレキシブル胸腔(きょうくう)鏡(きょう)を用いた局所麻酔下での胸腔鏡検査も可能です。患者さんに応じて、全身麻酔下の胸腔鏡検査や外科的肺生検をご提案することもあります。
外科的手術(手術療法)
外科的治療
肺がんのⅠ-II期は手術療法が主体であり、肺葉(はいよう)切除が標準手術となります。III期では、抗がん剤や放射線治療と手術を組み合わせた治療を行います。抗がん剤や放射線治療を行った後に手術療法で完全切除して根治を目指す手術(サルベージ手術)も行っています。IV期では手術療法が行われることは稀ですが、局所のコントロール目的に手術を行う事があります。
当院では、肺がんの種類や進行度を考慮して、低侵襲で、かつ根治することができる治療法を行うために、一人一人の患者さんに最適な手術の方法を選択しています。最近では、CTにしか映らない淡いすりガラス陰影をもつ肺がんが見つかるようになっています。この肺がんの問題点は淡く病変が触れないことや場所がわかりにくいことでした。当院ではこのような肺がんに対して、気管支鏡を用いて肺癌の近くの肺に複数箇所マーキングを行なったり、微小なICタグを留置することで腫瘍と切除する範囲を決める方法(マッピング法/マーキング法)を導入しており、確実に肺がんを切除することが可能となっています。また、最近では、すりガラス状結節などの早期肺がんに対しては肺機能の温存を目的とした区域切除も積極的に行われるようになってきています。
肺がんが隣接する臓器に浸潤している場合には、肺がんを根治するためには隣接する臓器も切除が必要な場合があります。隣接する臓器も一緒に合併切除(拡大手術)した場合には、元の状態に機能を戻す再建術も同時におこなっています。この手術は、肺がんの進行度や組織型や機能を考慮して慎重に手術の治療法を選択しており、また非常に高難度な手術が含まれていますが、これまでの数多くの経験と実績により、拡大手術を行うことが可能となっています。
鏡視下治療(ロボット支援下を含む)
当院では肺がんに対する手術のうち、約7割が胸腔鏡というカメラを用いて、小さな傷で手術を行なっています。
2018年4月からはロボット支援下手術が保険適応となり、当院でもロボット支援下に肺葉切除をおこなっており、小さな傷で手術を行うとともに、精密な手術が可能となっています。
内視鏡的治療
内視鏡的治療の多くは、肺がんによる症状を緩和する目的で行われます。例えば、肺がんの進行によって気道(空気の通り道)が狭くなってしまった場合、せきやたん、呼吸困難、喘鳴(ぜんめい)などが現れることがあります。これらの症状を緩和するために、患者さんの体力に応じて、バルーンやステントで気道を広げたり、腫瘍を焼灼(しょうしゃく)したりする治療をご提案させていただきます。
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
肺がんが太い気管支の入り口に存在する場合には、切除が困難な場合があります。そのような場合に、手術に代わる方法としてBAI(気管支動脈内注入)療法があります。この方法では太腿(だいたい)(ふともも)の付け根(鼠径(そけい)部)の動脈からカテーテルを挿入し、がんに栄養を供給している気管支動脈から抗がん剤を直接注入します。このBAI療法は、標準治療ではありませんが、症例によっては良好な治療効果を示すこともあり、ご提案させていただくことがあります。
薬物療法
抗がん剤
がん細胞は正常細胞よりも著しく速く分裂し、増殖しています。細胞の分裂を抑える薬が抗がん剤(細胞障害性抗がん剤)です。抗がん剤は、全身にくまなく行き渡ることで全身に広がるがん細胞を治療できるため、進行期の患者さんに有効な治療法です。患者さんの状態、治療歴、薬剤の副作用などを考え合わせて、薬剤を適宜選択します。副作用は人によっても異なり、病状や抗がん剤の種類や量などでも異なりますが、血液中の白血球や血小板の減少、貧血、吐き気や嘔吐(おうと)、脱毛、全身倦怠感などがもっともよくみられる副作用です。また、肺がんそのものやその治療にともなって現れる症状についても、鎮痛薬(痛みを和らげる薬)や制吐薬(せいとやく)(吐き気を抑える薬)も種類が増え、以前に比べて、症状をコントロールしやすくなりました。「治療を行いながらでも、なるべく通常通りの生活を送られる」ことを目標に治療を行っています。
分子標的薬(ぶんしひょうてきやく)
がんの増殖に関わっている分子を標的にしてその働きを阻害する薬です。肺がん患者さんから採取されたがん細胞を検査して、がん細胞の特定の分子に遺伝子変異が確認された場合が適応になります。具体的には、肺がんでは、「上皮成長因子受容体(EGFR)」「未分化リンパ腫キナーゼ(ALK)」、「ROS1」「BRAF」「KRAS」「NTRK」「MET」など、より多くの分子に対する遺伝子変異が特定され、それぞれに対応した分子標的薬が開発されています。また、一部の分子標的薬では化学療法との併用療法が確立され、より効果的な治療選択肢となっています。分子標的薬による治療では、がん細胞の中の特定の分子を攻撃するため、がん細胞が縮小したり死滅したりしますが、正常な細胞へのダメージが少ないのが特徴です。皮膚の障害、下痢、肝機能障害などがもっともよくみられる副作用です。
免疫チェックポイント阻害薬
がん細胞は自己の成長・増殖のために、生体側の免疫(異物を排除する力)から逃れる・免疫にブレーキをかけるような仕組み(免疫逃避(めんえきとうひ))を持っています。免疫チェックポイント阻害薬は、「がん細胞などによるブレーキをかける仕組みをブロックする(免疫にかけられたブレーキを外す)」ことで、自分自身の免疫細胞ががん細胞を攻撃する治療薬です。すべての患者さんに効果が出るわけではありませんが、患者さんによっては治療効果が長期間続く可能性があります。2018年からは免疫チェックポイント阻害薬と抗がん剤を同時に併用することで治療効果をさらに高める治療が行えるようになりました。現在では、PD-1/PD-L1阻害薬とCTLA-4阻害薬という異なる種類の免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせる「デュアル免疫療法」が確立され、単独使用と比べてより良好な治療成績が得られています。さらに最近では、早期がんの手術前後の補助療法(周術期免疫療法)としても使用され、再発リスクを低減する効果が示されています。このように、免疫チェックポイント阻害薬の使用は進行期がんから早期がんまで適応が広がっています。副作用の問題もあるため、すべての患者さんに勧められるわけではありませんが、当院も治療法の一つとして施行しています。
免疫チェックポイント阻害薬には、従来の抗がん剤や分子標的薬とは全く異なったタイプの副作用が見られる場合があります。当院では、それぞれの治療担当の診療科だけでなく、免疫チェックポイント阻害薬副作用管理委員会(IO委員会)を中心に複数の診療科および多職種と連携して、適切な管理を行っています。
ホルモン(内分泌)剤
該当なし
その他
該当なし
放射線療法
根治的放射線治療
I-II期の非小細胞肺がん
肺葉切除が可能な方は手術療法が第一選択となります。肺葉切除が困難な場合、縮小手術も困難な場合、また手術を希望されない場合などに、根治的放射線治療が適応となります。
特に末梢型のI期では腫瘍への放射線の線量集中性の高い定位放射線治療 (ピンポイント照射)を行うことで高い根治率が期待できます。当院では、最新の画像誘導照射技術を用いた精度の高い定位放射線治療が実施可能です。
III期の非小細胞肺がん
肺葉肺葉切除やリンパ節郭清などの手術療法が困難な場合に根治的放射線治療を行います。抗がん剤を同時に併用することで治療効果が高まります(化学放射線療法)。
当院の根治的放射線治療では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いて、腫瘍への線量集中性と正常肺や心臓の線量を低減する高精度な照射を実施しています。心臓の機能障害や放射線肺臓炎などの副作用リスクの軽減が期待できます。さらに当院では、放射線治療効果の改善を目的に温熱療法(後述)の併用が選択可能です。
化学放射線療法を終了後に免疫チェックポイント阻害薬を投与することで、根治率が上昇します。また、手術療法が実施可能となった場合には、遺残する腫瘍に対して救済切除を行う場合があります。
限局型の小細胞肺がん
根治的な放射線治療を行います。抗がん剤を同時に併用することで治療効果が高まります(化学放射線療法)。1日2回の放射線照射を約3週間行います。
化学放射線療法後に良好な腫瘍縮小が得られた場合には、脳転移の出現予防に脳への放射線治療の追加が有効です(予防的全脳照射)。当院では、認知機能低下リスクを軽減するために、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いて海馬を回避した予防的全脳照射を実施しています。
手術療法後の再発予防を目的とした放射線治療
手術で摘出した肺がんの遺残がある場合、周囲への浸潤が強い場合、またリンパ節転移が多発していた場合などに、再発予防を目的とした放射線治療を行います。再発や転移を生じるリスクが高い場合には、抗がん剤を併用することがあります。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
治療した肺やリンパ節(鎖骨上、縦隔や肺門)の再発、または少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加え救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、肺や肝臓の転移、骨転移などが対象となります。治療した腫瘍の高い制御効果が期待できます。
脳転移に対する放射線治療
脳転移を生じた場合に放射線治療が有効です。当院では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いた定位放射線治療(ピンポイント照射)が可能です。患者さんに負担の少ない短い治療時間で、脳転移の高い制御効果が期待できます。
緩和的放射線治療
他の臓器へ多数個の転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。肺がんによる血痰や疼痛、呼吸苦、また骨転移に伴う疼痛や神経症状といった症状の緩和に有効性が高いです。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。治療期間は2週間以内が多く、状況に応じて1回のみの治療も選択可能です。
温熱療法 (ハイパーサーミア)
当院では、肺がんに対して放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。パッ
ト内の液体を還流させ、皮膚表面の熱感や痛みを抑えます。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
当院の肺がん診療の特徴として、呼吸器内科、呼吸器・胸部外科、放射線科と協力して週1回の定期的なカンファレンスを行い、患者さんごとに最適な治療を提供できるように努めています。また当院では「がん相談支援センター」を院内に設置し、患者さんやご家族に安心して療養生活を送ってもらえるように、がんに関する不安や悩みをお受けしています。
産業医科大学 医学部 第2外科学 診療部門
http://www.kitakyusyu-gan.jp/homepage/sinryou.html
産業医科大学 医学部 呼吸器内科学
https://www.uoeh-u.ac.jp/hospital/gaiyo/bumon/houchi.html