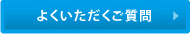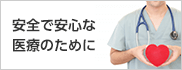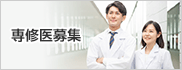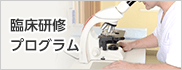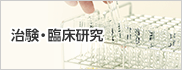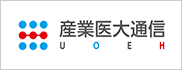咽頭・鼻のがん
耳鼻咽喉科、頭頸部外科ホームページはこちらへ
病気について
咽頭がんは、部位によって発症リスクが異なるがんです。上咽頭がんは、Epstein-Barrウイルス、中咽頭がんは、ヒトパピローマウイルスもしくは喫煙・飲酒、下咽頭がんは喫煙・飲酒が発症リスクに関わることが分かっています。最近、ヒトパピローマウイルスに関係した中咽頭がんが増加しています。鼻・副鼻腔がんで、最も多いのは上顎洞がんで、次いで篩骨洞がんの順です。稀に、悪性黒色腫や嗅神経芽細胞腫などの組織型が発生することもあります。
診断について
視診で、咽頭の病変を診断します。鼻腔を経由してファイバースコープで咽頭の病変の広がりを確認します。がんかどうかの診断は、病変の一部を切除して病理検査に提出します。ほとんどのがんは、扁平上皮癌というがんです。中咽頭がんの場合は、ヒトパピローマウイルス感染によるものかどうかの追加検査を行います。触診では、頸部リンパ節の腫れを確認して、リンパ節転移の有無を判断します。病変が確認された場合は、超音波・CTMRIPET-CT検査などを行い、がんの進行度を診断し、治療方針を検討します。
手術療法
中咽頭がん、下咽頭がん、鼻副鼻腔がんに対しては、外科的治療が根治治療の選択肢の一つとなります。切除範囲に応じて、再建術が必要となります。その場合は形成外科と外科(遊離空腸採取時)と合同手術を行います。術後は、切除範囲や再建の状態で、言葉や食事に障害をきたすため、各種リハビリテーションや栄養サポートなどが必要で、多職種でのチーム医療が重要となります。進行した下咽頭がんの場合は、下咽頭および喉頭の全摘出が必要となり、その場合は発声ができなくなり、身体障害者3級となります。希望者には、代替発声の外科治療(Provox2を用いた気管食道シャント術)を行うことが可能です。
頭頸部がん切除後に大きな欠損が生じた場合、術後の会話や嚥下機能の著しい低下が予想されることがあります。それらの場合、欠損部を修復し損なわれる機能を維持・回復するために再建手術が行われます。移植する組織は、欠損部位や範囲に応じて選択されます。また、多くの場合、顕微鏡を使用して血管吻合を行うマイクロサージャリー技術が用いられます。
内視鏡的治療
早期下咽頭癌の場合、全身麻酔下に内視鏡を用いて経口的にレーザー焼灼術や高周波メスを用いた切除術を行なっています。鼻腔内に限局した鼻腔がんの場合、全身麻酔下に内視鏡を用いて経鼻腔的な切除が可能です。
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
該当なし
薬物療法
喉頭温存希望の下咽頭がんに対しては、根治治療前の導入化学療法は標準治療の一つです。効果があれば放射線療法、効果がなければ外科的治療での根治治療を行います。進行上咽頭がんの場合、放射線療法の前に導入化学療法を行うと治療効果の向上が望める可能性があります。
切除不能な再発転移を有する咽頭がん・鼻副鼻腔がんに対しては、薬物療法が適応となります。標準的な治療は、抗がん剤(主にプラチナ製剤)と分子標的薬(セツキシマブ)を併用します。免疫チェックポイント阻害剤も、一定の条件を満たした場合には使用可能で、一般的に用いられています。ただし、薬物療法単独での根治は難しく、治療の目的は症状緩和/延命となります。1−2週間に1回の通院もしくは短期入院での抗がん剤の点滴が必要です。
放射線療法
根治的放射線治療
中・下咽頭がんの根治的放射線治療は、喉の摘出を行わないため発声や嚥下機能を温存できる大きなメリットがあります。高い制御率が望める早期の中・下咽頭癌では主たる治療法です。進行した大きな癌では、手術療法を希望されない場合に行います。その場合は、抗がん剤を同時に併用(化学放射線療法)することで腫瘍を制御できる確率を高めます。また、中咽頭癌の腫瘍組織がヒトパピローマウイルスと関連している場合は、進行した癌でも化学放射線療法が奏効しやすく高い根治率が期待できます。
上咽頭がんは根治的放射線治療が主たる治療法です。治療効果を高める目的で抗がん剤を併用します。
鼻副鼻腔がんは、手術療法と化学放射線療法を組み合わせて治療することが標準的です。抗がん剤の治療効果を高める目的で、がんを栄養する血管にカテーテルを直接挿入し、高濃度の抗がん剤を腫瘍に投与する投与法(動注)を行います。
当院では強度変調回転放射線治療(VMAT)と呼ばれる、高精度な放射線照射方法を採用しています。放射線治療後の唾液戦の分泌量低下などの副作用リスクを軽減することが可能です。さらに当院では、放射線治療の治療効果を高める目的で温熱療法(後述)の併用が可能です。
手術療法後の再発予防を目的とした放射線治療
手術療法を行った後に再発リスクが高い場合に、放射線治療の追加が必要です。腫瘍の周囲への浸潤が強い場合、リンパ節転移が大きい場合や多発していた場合などが相当します。放射線治療の追加により、再発を生じる確率が減少し予後が改善します。こちらでも高精度な強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いています。唾液腺の分泌量低下などの副作用の発症率を軽減できます。また、治療効果を高める目的で抗がん剤を併用する場合があります。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
咽頭、鼻副鼻腔や頸部リンパ節の再発、また少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加えて救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移は、肺の転移、縦隔などのリンパ節転移、骨転移などが対象となります。治療した腫瘍の高い制御効果が期待できます。特に5cm以下の少数個の肺転移に対しては、定位放射線治療(ピンポイント照射)が選択できます。
過去に放射線治療が行われた咽頭、鼻副鼻腔や頸部リンパ節の再発では、摘出術が第一選択となります。摘出が困難な場合、再度の放射線治療(再照射)が選択肢となります。通常、十分な量の放射線を投与できませんが、当院ではより腫瘍に対て高精度に放射線を集中させる強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いることや、温熱療法(後述)を併用することで、治療効果の改善を図っています。
緩和的放射線治療
他の臓器へ多数個の転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。腫瘍からの出血の止血、疼痛の鎮痛、嚥下の改善、また骨転移に伴う疼痛の鎮痛や神経症状の改善といった症状緩和に有効性が高いです。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。治療期間は2週間以内が多く、状況に応じて1~2日間の短期間の治療も選択可能です。
また、免疫チェックポイント阻害剤の治療効果を高める目的でも、放射線治療を追加することがあります。
温熱療法 (ハイパーサーミア)
当院では、咽頭がんや鼻副鼻腔がんに対して放射線治療の治療効果を高める温熱療法を取り入れています。主に進行癌や再発癌を対象としています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
頭頸部癌の治療に際しては、カンファレンスを行い、エビデンス(科学的根拠)に基づいた最適な治療を検討します。患者さんの価値観や全身状態、QOL(Quality
of
life:
生活の質)を重視した上で、最適な治療方針を決めています。患者さん及びご家族には、病状・治療選択肢について、分かりやすくかつ十分に説明し、納得できる治療を提供できるように努めています。根治可能な患者さんには、外科治療、術後補助化学放射線療法、導入化学療法、化学放射線療法などを、最適な組み合わせ・順序で行っています。治療に伴う有害事象に対しては、適切な支持療法を用いて治療が完遂出来るようにサポートします。一方、根治が難しい患者さんには、緩和的な放射線治療や化学療法を緩和ケアと並行して行い、QOS(Quality
of
survival)を目指した治療、すなわち現在の生活を出来るだけ長く過ごしてもらうことを目的とした治療を行っています。これらの頭頸部癌の治療は、専門的な知識と経験が特に必要となるため、頭頸部癌専門チームで対応しています。
産業医科大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 診療案内
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/jibika/examination.html
産業医科大学病院 形成外科 診療案内