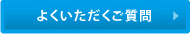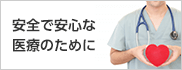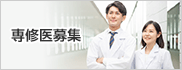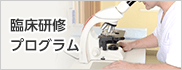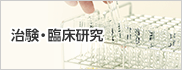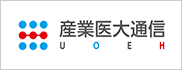消化管GIST
病気について
GISTとは、gastrointestinal stromal tumorの略で、消化管間質腫瘍といいます。消化管や腸間膜に発生する悪性腫瘍です。頻度は10万人に1~2人と稀な病気です。食道、胃、小腸、大腸と、どの消化管にでも発生することがありますが、わが国では特に胃に多い病気です。
悪性腫瘍は、「癌腫」と「肉腫」に分類されます。癌腫とは、体の表面を覆う上皮という部分から発生するもので、肺癌や胃癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌などです。それに対して、肉腫とは上皮の内側の筋肉や筋肉の間の結合組織などから発生するものです。GISTは肉腫であり、消化管の壁の筋肉の層の中にあるカハール介在細胞という細胞の前段階の細胞が増殖したものです。消化管の壁の中から発生するので、粘膜の下にある腫瘍(粘膜下腫瘍)の形態をとります。
診断について
内視鏡検査やバリウム検査、CTやMRIで粘膜下腫瘍として発見されます。特に我が国では検診が普及しているため、サイズが小さく自覚症状がないうちに発見されることも少なくありません。
確定診断のためには細胞検査が必要ですが、胃癌や大腸癌と違い粘膜の下にあるので通常の内視鏡検査で直接細胞を採取することが簡単にできません。このため、超音波内視鏡(エコーの機械が付いた内視鏡)で腫瘍を観察しながら針を刺し、細胞を採取します(超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診といいます)。そのうえでKITという蛋白が過剰にある場合、またはKIT陰性でも免疫染色でDOG1陽性であればGISTと診断されます。
手術療法
外科的治療
GISTは胃癌や大腸癌と比べ周囲の組織に及ぶことが少なく、リンパ節転移も非常に稀であり、多くの場合、切除臓器の機能温存を考慮した部分切除を行います。
腹腔鏡下手術
腫瘍径が比較的小さい場合(<5 cm)は腹腔鏡下手術を行います。また、胃のGISTに対しては、内視鏡医による内視鏡手術と、外科医による腹腔鏡下胃局所手術の合同手術(LECS: Laparoscopy-Endoscopy CooperativeSurgery)を積極的に行っています。
実際の手技としては、臍を切開し、腹腔内に炭酸ガスを入れて膨らませ、カメラ(腹腔鏡)を挿入します。次に、手術操作に用いる器具を挿入するために2~10mmの小さな傷を腹部に追加します。口から通常の胃カメラを挿入し、胃の中と胃の外側(腹腔内)の様子を同時に観察しながら手術を行います。胃のGISTは胃の中に出っ張っていたり、外に出っ張っていたりと様々であり、余分な胃壁を切除してしまうことがあります。できるだけ過剰な胃壁を切除しないように胃の内外から観察することで、より正確に腫瘍の範囲を見定めて切除することが可能になります。切除する範囲が最低限となることで、胃の変形が最小限で済み、胃の機能を可及的に温存することができます。また、胃の入り口(噴門)近傍に存在する場合は、腹壁から胃の内腔に手術器械を挿入する胃内手術を行う場合もあります。
これらの手術による侵襲は最小限で、術後1週間程度で退院が可能となります。
手術後に病理組織検査結果より再発しやすさに応じたリスク分類(完全切除した後の推定再発率)を行います。高リスクと判定された場合は、再発予防目的に内服(抗がん剤;イマチニブ等)治療を行います。
薬物療法
切除不能GISTの抗がん剤治療について
GISTの最も有効な治療は外科手術ですが、転移が広範囲で手術ができない場合は抗がん剤治療が行われます。GISTに対する抗がん剤は主に分子標的薬が用いられます。分子標的薬は悪性細胞の増殖に関わる分子を攻撃するため、正常の細胞に対する影響が少なく、従来の抗がん剤に比べて副作用が少ない、或いは副作用のタイプが異なっています。現在我が国で使用できる抗がん剤は、イマチニブ、スニチニブ、レゴラフェニブ、ピミテスピブの4剤があります。
第一選択薬としては、まずイマチニブの投与を行います。イマチニブが無効または一旦効いた後に効かなくなった(耐性といいます)場合はスニチニブの投与を行います。スニチニブ耐性であればレゴラフェニブの投与、レゴラフェニブ耐性であればピミテスピブの投与を行います。重要なことは、副作用をうまくコントロールしながら、これらの薬剤をできるだけ長く継続していくことが大切です。
また、腫瘍径が10cm以上の大きなものや、不完全切除の可能性が高いと判断されるGISTに対して、術前にイマチニブによる抗がん剤治療を行い、効果を認め他場合、手術へ移行することもあります。
放射線療法
GISTに対する初回治療は手術が優先され、手術前・手術後の補助的な放射線治療の役割は確立されたものはありません。再発・転移に対しては、下記のような治療適応があります。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
腹部や骨盤内リンパ節の再発、あるいは少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加え救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、肺や肝臓の転移、骨転移、鎖骨上・縦隔などのリンパ節転移などが対象となります。治療した腫瘍の制御効果が期待できます。
緩和的放射線治療
他の臓器へ多数個の転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。腫瘍からの出血の<止血や疼痛の鎮痛、また骨転移に伴う疼痛や神経症状の緩和に有効です。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。治療期間は2週間以内が多く、状況に応じて1回のみの治療も選択可能です。
脳転移に対する放射線治療
脳転移を生じた場合に放射線治療が有効です。当院では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いた定位放射線治療(ピンポイント照射)が可能です。患者さんに負担の少ない短い治療時間で、脳転移の高い制御効果が期待できます。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
GISTは希少がんのひとつであり、外科、内科、放射線科などで話し合いながら総合的に診療していくことが大切だと考えています。また、GISTに対する抗がん剤は皮膚障害や内分泌・代謝疾患など、特徴的な副作用がでることがあるので他分野の医師にも関わってもらうこともあります。
産業医科大学 医学部 第3内科学
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/3nai/homepage/m_kenkyu_syouka.html
産業医科大学 医学部 第1外科学
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/1geka/intro_j.html
産業医科大学病院 放射線治療科
https://www.radiationoncol.com/