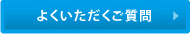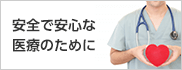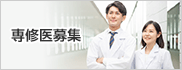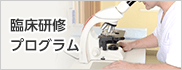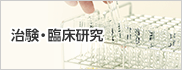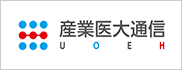膵がん
病気について
膵臓は胃の後ろにある20cm程度の左右に細長い臓器で、食物の消化を助ける膵液の産生(外分泌機能)と、血糖の調節などを行うホルモン(インスリンなど)を産生(内分泌機能)の2つの役割をつかさどっています。膵臓がんは約90%が膵管の細胞にできこれを膵管がん(腺がん)といい、通常膵臓がんはこの膵管がんを指します。このほかに膵腺房細胞がん、膵神経内分泌がん、膵管内乳頭粘液性腫瘍など様々な種類が存在します。
近年、大腸がんや乳がんとともに膵臓がんは増加傾向にあり、本邦の統計では、2023年の時点で男性では第4位、女性では第3位に死亡数の多いがんです。膵嚢胞や慢性膵炎、糖尿病からの膵臓がんの発生や家族性の膵臓がんも注目されていますが、年間の罹患数と死亡数はほぼ同数となっています。膵臓は体の深部に存在するため、がんが発生しても症状が出にくく、早期発見が困難ながんの一つとされています。
診断について
膵臓がんは診断が非常に困難な病気であり、他の病気との区別もつきにくいことが多いため、複数の検査を組み合わせて診断を行います。検査の手順や方法は施設間で多少の違いはありますが、日本膵臓学会「科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン」の診断手順に準じて検査を進めていきます。
まず、臨床症状(腹痛や背部痛、黄疸、体重減少など)や血液検査、腹部超音波検査などによる検査にて膵臓がんが疑われる場合に詳細な画像検査を行います。画像検査では造影コンピューター断層撮影(CT)や造影磁気共鳴画像(MRI)、磁気共鳴胆管膵管画像(MRCP)、超音波内視鏡(EUS)、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)、ポジトロン断層撮影(PET-CT)などが用いられることが一般的です。これらの検査結果より画像診断がなされ、さらにEUSやERCPを行い腫瘤から細胞や組織を採取することで、病理検査を行います。これらの検査の結果から、病期を決定し、治療方針をたてていきます。
当院では上記の全検査が可能であり、膵臓がん治療に関係する全診療科が連携して必要な検査を提案し、安全かつ的確に診断できるよう努めております。
手術療法
外科的治療
膵臓がんの標準治療には、手術による切除、化学療法(抗がん剤)、放射線治療がありますが、根治(完全に治癒すること)の可能性があるのは切除だけです。膵臓がんの患者さんのうち、次の条件を満たす場合に外科切除の適応となります。
・遠隔転移(肝臓など遠くの臓器への転移)がない。
・がんが重要な動脈(上腸間膜動脈および腹腔動脈)に浸潤していない。
・麻酔や手術に耐えられるだけの全身機能が保たれている(心臓や肺の機能が悪い患者さんでは手術ができないことがあります)。
一般的に、膵頭部のがんに対しては膵頭十二指腸切除術、膵体部~膵尾部のがんに対しては、膵体尾部切除術(尾側膵切除術)をおこないます。その他、頻度は少ないのですが、がんの部位によっては膵臓を全部切除する膵全摘術が行われることもあります。
膵頭十二指腸切除術
膵頭十二指腸切除術は、膵頭部(膵臓の右側)にがんが存在する場合の標準術式です。切除する範囲は、膵頭部、十二指腸、胆管、胆のう、胃の一部(あるいは、胃を出口(幽門輪)もふくめて全部残す場合もあります)です。
切除した後は、消化管の再建(つなぎなおし)をします。色々なつなぎ方があるのですが、一般的には残った膵臓と空腸(小腸の一部)、胆管と空腸、そして胃と空腸をつなぎます。
膵頭十二指腸切除術は、およそ消化器手術のなかでも大きな手術であり、死亡率や合併症が高いといわれています。
膵体尾部切除術
膵体尾部切除(尾側膵切除術)は、がんが膵臓の体部から尾部に存在する場合の標準的な手術です。膵臓の頭部だけを残し、脾臓(ひぞう)もふくめて膵臓の体部および尾部(左側)を切除します。
膵臓を切った端の部分は、以前は手で縫って閉じていましたが、最近では、ステイプラというホッチキスのような器械を使い、膵臓を切ると同時に端を自動的に縫い閉じることが多くなってきました。ただ、この器械による膵臓の閉鎖も完璧ではなく、端から膵液がもれる合併症がおこる可能性はあります。
病変の進行度(周囲臓器への浸潤、血管浸潤の有無、周囲炎症の強さなど)にもよりますが、状況によっては腹腔鏡下手術(傷の小さな体に負担が少ない手術)の適応になることもあります。
手術の合併症・後遺症
膵臓がんの手術は比較的からだへの負担(侵襲)が大きく、また術後の合併症も多いことで知られています。とくに、膵臓の切離した部位から膵液がもれる膵液瘻(すいえきろう)がおこりやすく(10~30%)、ときに出血や膿瘍(のうよう:うみが貯まった状態)などより重症の合併症の原因となります。
内視鏡的治療
膵臓がんが原因による黄疸や消化管の狭窄に対して、内視鏡を用いた胆管ステントや消化管ステントの留置を行っています。
膵臓がんによる胆管狭窄のために、黄疸・肝機能障害をきたした際には、内視鏡的逆行性胆管膵管造影にてプラスチックステントや金属ステントを留置して早急な減黄治療を行います。
十二指腸への狭窄をきたした場合には、内視鏡にて金属ステントを留置し狭窄部位の解除を行うなどの治療を行います。
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
該当なし
薬物療法
抗がん剤
膵臓がんは1990年代前半まで有効な治療法がなく、1990年代後半に登場した塩酸ゲムシタビン(商品名:ジェムザール)が登場して、膵臓がんに対して優れた治療効果を示し、化学療法は大きく進歩しました。本邦でも2001年に保険収載され、広く使用されています。その後胃がんなどで使用するS-1(商品名:TS-1)も膵臓がんに良好な治療成績が示され、2006年に保険収載されました。2010年代に入るまではしばらくこの2剤が主流で治療されてきましたが、2013年には4種類の抗がん剤を併用するFOLFIRINOX療法が、2014年には塩酸ゲムシタビンにアルブミン結合型パクリタキセル(商品名:アブラキサン)の併用療法が認可され、化学療法の分野で大きく進歩してきています。2次治療においても2020年にイリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤(商品名:オニバイド)にフルオロウラシルとレボホリナートを併用する化学療法が認可されました。
初回の化学療法は基本として入院で行います。副作用の程度をみながら患者さん毎に投与量・投与方法の調整を行います。調整がつくと外来での治療継続が可能となりますが、副作用のリスクが高い薬剤のため、適宜血液検査等での確認が必要です。
塩酸ゲムシタビン単独療法
代謝拮抗剤に分類される薬剤で、1週間に1回の点滴を3週続けて投与し、4週目は休薬します。この4週間を1コースとして繰り返し治療を行います。投与量は身長と体重から算出された体表面積から計算し、点滴にかかる時間は30分程度です。先行して吐き気止めの点滴等を行うことがあり、1回の点滴で要する時間は全体でおおよそ1時間程度です。
S-1単独療法
S-1は内服薬の抗がん剤で、体表面積や採血での腎機能の評価などから投与量が決定されます。朝夕の2回に分けて食後に服用します。通常は28日間(4週間)内服し、その後の14日間(2週間)はお休みとなります。6週間を1コースとして繰り返していきますが、患者さんの状態によっては14日間(2週間)連日内服を行った後、7日間(1週間)お休みする方法での3週間を1コースとして繰り返し治療することもあります。
FOLFIRINOX療法(オキサリプラチン、レボホリナート、イリノテカン、フルオロウラシル)
FOLFIRINOX療法は、オキサリプラチン、レボホリナート、イリノテカン、フルオロウラシルの4種類の抗がん剤を組み合わせた治療法です。オキサリプラチン、レボホリナート、イリノテカン、フルオロウラシルの点滴を1日目に行い、その後2日間フルオロウラシルを持続点滴します。投与には48時間かかるため、事前に中心静脈カテーテルを挿入し、ポートを皮下に埋め込む処置が必要となります。投与後4日目から14日目までは休薬で、2週間を1コースとして治療を繰り返します。塩酸ゲムシタビン単剤と比較して優位に生存期間の延長が報告されていますが、副作用のリスクが高いことが知られています。特にUGT1A1という遺伝子型によっては、重篤な副作用をきたすことがあるため、事前に血液検査を行い、遺伝子型を調べた上で投与を開始することが一般的です。
また、副作用のリスクから高齢の患者さんには基本的に不適とされています。そこで、副作用を軽くするためにイリノテカンの減量や急速静注を省略したmodified
FOLFIRINOX(mFOLFIRINOX療法)という投与法で行うこともあります。
塩酸ゲムシタビン+ナノ粒子アルブミン結合パクリタキセル(nab-PTX、商品名:アブラキサン)併用療法
パクリタキセルという抗がん剤に人血清アルブミンを結合させた薬剤と塩酸ゲムシタビンを併用する治療法です。1週間に1回の点滴を3週続けて投与し、4週目は休薬です。点滴時間は塩酸ゲムシタビンの投与期間よりやや長くなります。
イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤(商品名:オニバイド)+フルオロウラシル・レボホリナート療法
塩酸ゲムシタビンを含む化学療法後に増悪した遠隔転移を有する膵臓がん患者さんを対象とした海外第3相試験(NAPOLI-1試験)、国内第2相試験(331501試験)において、イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤+フルオロウラシル・レボホリナート療法の有用性と安全性が確認されました。イリノテカン塩酸塩水和物リポソーム製剤とレボホリナートを1日目に投与し、その後2日間かけてフルオロウラシルを持続点滴します。FOLFIRINOX療法と同様に事前に中心静脈カテーテルを挿入し、ポートを皮下に埋め込む処置が必要となり、UGT1A1という遺伝子型を調べることで副作用発現リスクを確認します。2週間間隔で治療を繰り返します。
上記の治療が現在行っている化学療法になりますが、どの治療法を用いるかは患者さんの年齢や全身状態、持病、腫瘍の状態など様々な要因で異なります。担当医と相談した上で治療を決めていくことが重要となります。
副作用は個人差がありますが、代表的なものは下記のとおりです。
すべての薬剤に共通する副作用としては、嘔気・嘔吐、便秘、下痢などの消化器症状、食欲不振や倦怠感、皮疹、一過性の発熱などです。程度が強い場合には抗がん剤の減量や中止などを検討します。
自覚できない副作用としては、血液成分を造る骨髄機能が抑制される骨髄抑制(白血球減少、貧血、血小板減少など)や腎機能障害、肝機能障害があります。これら副作用がないか定期的な血液検査が必要となります。投与量の調整や休薬などの対応が一般的ですが、骨髄抑制では、必要に応じて赤血球輸血や血小板輸血、白血球を増やす注射を使用します。併用薬剤が多いものでは特に副作用が強く出ることがあり、十分な注意が必要です。また薬剤により肺炎やアレルギーが出ることもあり、注意が必要です。
ホルモン(内分泌)薬
該当なし
分子標的薬
BRCA遺伝子変異を有する進行膵がんに対するPARP阻害剤のオラパリブ(商品名:リムパーザ)維持療法が海外第3相試験(POLO試験)において有用性と安全性が確認され、本邦でも2020年12月にBRCA遺伝子変異陽性の治癒切除不能な膵がんにおける白金系抗悪性腫瘍剤を含む化学療法後の維持療法として承認されました。DNAは様々な刺激によって損傷を受けていますが、DNA損傷のタイプが一本鎖切断の場合にはPARPの作用により修復が行われます。DNA損傷のタイプが二本鎖切断の場合にはBRCAなどによって修復が行われます。BRCA遺伝子異常が存在すると二本鎖切断の修復が十分に行えません。白金系高悪性腫瘍剤を含む化学療法後のBRCA遺伝子変異陽性膵がんにおいて、PARP阻害剤のオラパリブは一本鎖切断の修復を阻害し、さらには二本鎖切断の修復も妨げることで、細胞死を誘導し抗腫瘍効果を発揮します。オラパリブは飲み薬で、1回300mgを1日2回服用します。
免疫チェックポイント阻害薬
体内にある免疫系細胞に対して働きを抑えるようにシグナルを伝える仕組みがありますが、がん細胞では免疫系細胞に攻撃されないように食い止める仕組みがあることが明らかになってきました。この作用に対して調整し、免疫系細胞ががん細胞の攻撃を再開するように開発されたのが免疫チェックポイント阻害薬です。がん細胞にはいくつかのタイプがありますが、MSI-HighないしTMB-Highの固形がん(高頻度マイクロサテライト不安定性固形がん)は他のがんと比べて免疫細胞のT細胞の認識を受けやすく、もともと免疫機能が活発に働いていた可能性が考えられています。このため、これらの固形がんでは免疫チェックポイント阻害薬による効果発現が期待されています。
MSIとTMB検査は採取した組織を使用し、組織内のDNAを調べますが、膵臓がん患者におけるHSI-Highの発現頻度は1%前後と報告されています。
放射線療法
根治的放射線治療
切除可能な場合の膵臓がんは手術療法が第一選択となりますが、化学放射線療法による手術可能となることが想定される場合、又手術を希望されない場合などに根治的な放射線治療を行います。病変局所への高い治療効果が期待でき、また疼痛の緩和にも優れます。
当科では、強度変調回転放射線治療 (VMAT)を用いて、腫瘍への線量集中性と周囲の正常臓器 (胃, 十二指腸, 肝臓や腎臓) の線量を低減する高精度照射を実施しています。
抗がん剤(塩酸ゲムシタビン, S-1など)を放射線治療期間中に同時併用すると有効性が高いです(化学放射線療法)。治療期間は、概ね5〜6週間程度です。さらに当院では放射線治療の治療効果を高める目的で温熱療法(後述)の併用が可能です。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
手術した局所や腹部のリンパ節の再発、あるいは少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加え救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、肺や肝臓の転移、骨転移などが対象となります。治療した腫瘍の高い制御効果が期待できます。
緩和的放射線治療
他の臓器へ多数個の転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。腹部の腫瘍に伴う疼痛、黄疸や肝機能障害の改善、出血の止血、また骨転移に伴う疼痛や神経症状の緩和を目的に行います。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。治療期間は3週間以内が多く、状況に応じて1回のみの治療も選択可能です。
温熱療法 (ハイパーサーミア)
当院では、膵臓がんに対して放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める目的で温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。パット内の液体を還流させ、皮膚表面の熱感や痛みを抑えます。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
がんの疑いがあるといわれた時点から、患者さんやその家族は症状だけでなく心の面や、経済面等、様々なつらさを抱えられると思います。がんセンターでは医師、看護師をはじめ多職種が連携して検査・治療にあたってまいります。気になる点などありましたら、どんな些細なことでも気軽にご相談ください。
産業医科大学 医学部 第3内科学 胆膵グループ
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/3nai/homepage/m_kenkyu_tansui.html
産業医科大学 医学部 第1外科学 肝胆膵グループ
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/1geka/m_group2.html
産業医科大学病院 放射線治療科
https://www.radiationoncol.com/