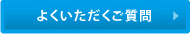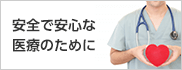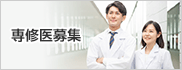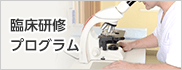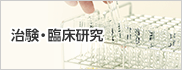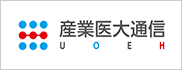胆のう・胆管がん
病気について
肝臓で作られた胆汁(消化液)は胆嚢という臓器で濃縮され、十二指腸に流出します。この通り道を胆道といい、この胆嚢を含めた胆道に生じるがんを胆道がんと呼びます。胆道がんは、胆嚢がん、胆管がん、十二指腸乳頭部がんと部位によって名前が変わります。胆道がんの日本における罹患率は人口10万人あたり17.0人と推定されています。年間死亡者数は約1.7万人、全がんの約5%にあたり頻度は少ないですが、早期発見が難しく予後が悪いことが特徴です。胆嚢がんはやや女性に多く、胆管がん、十二指腸乳頭部がんは男性に多い傾向があります。治療は外科手術が第一選択ですが、早期の診断が難しく切除不能となることが少なくありません。また、膵・胆管合流異常、原発性硬化性胆管炎などが胆道がんのリスクファクターとして知られており、各種検査で診断が確定した場合には、厳重な経過観察や予防的手術が必要になることもあります。
当院での胆道がんに対する治療は最新版の胆道がん診療ガイドラインに基づいて行っています。胆道がんにおいて、治癒が望める唯一の治療法は外科的切除ですが、切除での治癒が見込めない(切除不能)胆道がんに対しては抗がん剤治療(全身化学療法)が標準治療となり、黄疸の治療と並行して行います。
診断について
胆道がんの診断のきっかけとなる症状は、黄疸、腹痛が約80%を占めます。黄疸とは、眼や皮膚が黄色くなること、尿の色が濃くなること、便の色が白くなること、皮膚のかゆみが出ることなどの症状を指します。無症状でも血液検査でAST、ALT、ビリルビン、アルカリフォスファターゼ、γGTPなどの上昇、CEA、CA19-9などの腫瘍マーカーの上昇を認めた場合は、腹部エコー、CT、MRIや超音波内視鏡(EUS)を行い、必要に応じて内視鏡的逆行性膵胆道造影(ERCP)、経皮経肝胆管造影(PTC)などを追加し診断を確定します。さらに詳細な検査として管腔内超音波(IDUS)、経口胆道鏡(POCS)を併用した診断を行うこともあります。リンパ節転移や遠隔転移の検出にはPET 検査(FDG-PET)も有用です。各種の胆道がんは、上記検査でほぼ診断が可能ですが診断が難しい場合もあります。
胆嚢がん
胆嚢がんは検診などの腹部エコーで発見されることが多く、造影CTにより深達度や遠隔転移、脈管・周辺臓器への浸潤などの評価を行います。最近ではマルチスライスCT(MDCT)の発達でより正確な診断が可能です。EUSも深達度診断に有用です。ERCPでは、胆汁を採取することにより細胞診を行うことができます。
胆管がん
胆管がんは黄疸や血液検査での肝障害を契機に発見されることが多く、腹部エコーによって拡張した胆管や狭窄部位を同定できることもあります。腹部エコーで描出が難しい場合は、磁気共鳴胆管膵管撮影法(MRCP)を用いることで、非侵襲的に胆管拡張・狭窄の描出が可能です。ERCPやPTCによる胆道造影では、がんの部位や範囲の評価に加え、経口胆道鏡、IDUSを用いてがんの進展範囲、深達度のさらなる詳細な評価が可能です。さらに病理診断のために細胞診・生検を行うことができます。
十二指腸乳頭部がん
十二指腸乳頭部がんの初発症状は黄疸が最も多く、上部消化管内視鏡で観察、生検を行い診断します。超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)を用いて病理診断を行う場合もあります。転移の有無の評価にはCT、MRI、深達度の評価にはEUSが有用です。
手術療法
外科的治療
胆嚢がん
胆嚢がんでは手術が唯一根治(治癒)の期待ができる治療です。
胆嚢がんの手術療法は小さな手術から大きな手術まで幅広くあります。その理由は、がんが胆嚢壁のどこまで進行しているか、また胆嚢の壁を越えて、肝臓や胆管をはじめとした周囲臓器や血管、リンパ節やリンパ管に、どの程度まで及んでいるかによって、根治切除(がんを取りきる手術)の方法が決定されるためです。がんの進展範囲によって、胆嚢だけの切除から、肝臓の半分以上に及ぶ切除まで、術式が大きく異なることが、胆嚢がんに対する外科治療の特徴といえます。
大きな手術が必要とされる場合、がんの広がりと切除臓器範囲、全身状態などを十分に検討したうえで手術適応を決める必要があります。遠隔転移がある場合などは手術適応にはなりません。
切除可能な場合、どこまでがんが浸潤しているかにより、術式が決められます。
①胆嚢摘出術
がんが胆のうの内側、粘膜や固有筋層にとどまっている場合に行います。胆嚢ポリープと診断されて胆嚢摘出術が行われ、病理組織検査の結果、がんが判明した場合、I期であれば一般的にはそれ以上の追加切除は行われません。
②拡大胆嚢摘出術
がんの広がりによって、胆嚢の周りも一緒に切除します。
漿膜(しょうまく)下層以上の浸潤が認められた場合は、必要に応じて肝切除やリンパ節郭清を行います。がんが胆のうの漿膜下層または肝臓と接している結合組織に浸潤している場合、がんを露出させないように胆嚢床(たんのうしょう)を含んで摘出します (胆嚢床切除)。
肝臓への直接浸潤がある場合は、肝切除および肝外胆管切除を行います。必要に応じてリンパ節郭清、膵臓と十二指腸の一部を切除する膵頭(すいとう)十二指腸切除術、大腸切除などの他臓器合併切除術を行います。合併手術によって胆管、膵管や十二指腸、大腸が切り離された場合、その中を通っていた胆汁や膵液、腸液の流れる道を作るため、縫い合わせる再建手術が行われます。肝臓への浸潤範囲が広い場合や、肝臓に栄養を送る血管への浸潤がある場合には、広範囲に肝臓を切除することもあります。
手術の合併症・後遺症
進行胆嚢がんに対する手術の場合、胆嚢だけでなく周りの組織や臓器を合併切除しなければならないため、比較的大きな手術になることが多く、その分からだへの負担(侵襲)も大きいことが知られています。主な合併症としては、胆管と小腸の縫合不全(うまくつながらず)に伴う胆汁漏(胆管は胆汁を消化管に流すための管であり、そのつなぎ目胆汁が漏れてしまう合併症)や胆管と小腸の吻合自体が原因で、また吻合部の狭窄や閉塞に伴う胆管炎が挙げられます。胆汁漏はときに膿瘍(のうよう:うみが貯まった状態)といった、重症の合併症の原因となります。
胆管がん
病期診断で手術できる時期と診断された場合、手術は唯一治癒が期待できる治療方法です。
胆管がんの手術適応は非常に複雑であり、特に肝門部領域(肝臓の中心部、肝臓に流入する脈管が集まっている部分)にできた胆管がんは、外科切除は技術的に非常に難しいため、ある施設では手術可能な場合が別の施設では手術の対象とならないとされることも珍しくありません。
胆管がんでは決まった手術術式といったものがなく、がんの場所、広がりに応じた、安全でできるだけ根治的な術式が選択されます。一般的には肝門部領域胆管がんの場合は肝切除と肝外胆管切除を伴う術式が選択され、遠位胆管(胆管の下流部分)がんの場合は膵頭十二指腸切除術が選択されます。いずれも難易度の高い手術です。
①肝切除+肝外胆管切除
肝門部領域胆管がんでは、多くの場合左右の胆管のいずれかに偏って広がっているため、左右どちらかの肝臓を切除(肝左葉あるいは右葉切除)します。また、近傍の門脈、動脈に容易に浸潤するため、がんの進展範囲により肝左葉あるいは右葉切除が選択されます。
胆管がんは胆管に沿うようにがんが広がることが多々ありますので、肝臓から出ている胆管も同時に切除しなければなりません。胆管は胆汁を消化管に流すための管であり、肝切除+肝外胆管切除を行った場合は胆管と消化管を吻合する再建手術も同時に行います。
②膵頭十二指腸切除
遠位胆管がんの場合は、膵臓への浸潤や膵臓の周囲へのリンパ節への転移を起こすため、膵頭部(膵臓の右側)と十二指腸を一緒に切除しなければなりません。
③肝切除+肝外胆管切除+膵頭十二指腸切除
胆管に沿ってがんが広範囲に広がっている場合、上記の2つの手術を組み合わせないと切除できない場合があります。この手術は非常に侵襲(しんしゅう;からだへの負担)が大きく、合併症が多いとされる術式です。この術式が選択されるということは、残念ながらがんが進行していることでもあり、この術式を選択する場合は、その適応を十分に考える必要があります。
手術の合併症・後遺症
肝門部領域胆管がんでは大量肝切除に伴う術後肝不全と胆管と小腸の縫合不全(うまくつかず、胆汁が漏れてしまう合併症)が挙げられます。遠位胆管がんでは膵頭十二指腸切除後の膵液瘻(膵臓と消化管の吻合がうまくつかず膵液が漏れてしまう合併症)が挙げられます。胆汁や膵液がお腹の中に漏れ出ると、そこに膿瘍(のうよう:うみが貯まった状態)を形成し、高熱の原因となります。またこの膿瘍が血管(主に動脈)に接していると、血管の壁が徐々に弱くなり、仮性動脈瘤(血管のこぶ)を形成し、大量出血の原因となり緊急処置が必要な場合があります。
胆管がんの手術は非常に大きな手術であり、侵襲がかなり大きいこと、さらに肝臓といった生命に極めて重要な臓器を直接扱うため、術後合併症や周術期手術死亡率は他のがんの手術と比べて高いのが現状です。また、術後再発率も高く、術前にはその手術でどのような利点があり、どの程度の危険度があるのかをよく理解しておく必要があります。
鏡視下治療
胆嚢がん
術前診断で胆嚢がんが疑われるポリープや胆のうの粘膜にとどまっている初期のがんが疑われた場合、診断的意味合いも含めて腹腔(ふくくう)鏡下手術を行う場合があります。
内視鏡的治療
内視鏡を用いて胆道がんを治療することは現時点では困難です。しかし、胆道がんの多くは放置すると黄疸が増悪し、胆管炎を発症して全身状態を悪化させます。そのため、全身化学療法を行うかどうかにかかわらず黄疸に対する治療が必要です。可能であれば、ERCPを行い十二指腸乳頭部からプラスチックや金属の胆管ステントを留置することになります。また、ERCPでの処置が困難な際には次のPTBD(経皮経肝胆管ドレナージ)や、EUS-BD(超音波内視鏡下胆道ドレナージ)が検討されます。黄疸の内視鏡的治療は複数回必要となる場合がほとんどです。
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
局所的治療で胆道がんを治療することは現時点では困難です。しかし黄疸に対して内視鏡的治療が難しい場合にはPTBDが選択されます。これは、体の表面から肝臓を経由して胆管や胆嚢を刺し、チューブを体の外に出して胆汁を排出させる治療です。チューブの通り道から金属の胆管ステントを留置することも可能です。胆管ステントがうまく機能すれば、チューブは1か月程度で抜去可能ですが、抜去が難しくなる場合もあります。
薬物療法
抗がん剤
現在、切除不能胆道がんにおける初回全身化学療法の標準療法は塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+免疫チェックポイント阻害薬の3剤併用療法、あるいは塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+S-1(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)の3剤併用療法です。他に塩酸ゲムシタビン単独療法、S-1単独療法、塩酸ゲムシタビン+シスプラチン併用療法、塩酸ゲムシタビン+S-1併用療法が保険治療として認められています。年齢や全身状態、併存疾患、腎機能などを考慮して初回治療として用いることや、初回化学療法の効果が不十分になった際の二次治療などに用いられます。
塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+免疫チェックポイント阻害薬併用療法
・塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+デュルバルマブ(GCD療法)
・塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+ペムブロリズマブ(GCP療法)
胆道がんで使用される免疫チェックポイント阻害薬には、抗PD-L1抗体であるデュルバルマブと抗PD-1抗体であるペムブロリズマブがあり、いずれかの薬剤を塩酸ゲムシタビン+シスプラチンとともに投与します。以前は、塩酸ゲムシタビン+シスプラチン併用療法が胆道がんの初回治療として用いられていましたが、国際共同第Ⅲ相試験により、免疫チェックポイント阻害薬との併用療法の有効性と安全性が証明されました。それを受けて、2022年12月にGCD療法が、2024年5月にはGCP療法が本邦で使用可能となりました。GCD療法とGCP療法の有効性と安全性を直接比較した臨床試験はありませんが、両者の治療効果には差がないと考えられています。GCD療法とGCP療法の違いとしては、投与スケジュール、投与時間、副作用が挙げられます。投与時間はGCP療法で30分短く、免疫チェックポイント阻害薬に由来する副作用がGCP療法で多く見られています。
GCD療法とGCP療法の投与スケジュールについて述べます。GCD療法は3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。1日目に吐き気止めの点滴を15〜30分で行った後に、塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+デュルバルマブを投与します。8日目は吐き気止めの点滴後に、塩酸ゲムシタビン+シスプラチンのみ投与し、15日目はお休みです。22日目から2コースが始まります。8コース目まではこのスケジュールで投与しますが、9コース目からはデュルバルマブのみ4週おきに投与します。GCP療法も3週間(21日間)を1コースとして繰り返します。GCD療法と同様に8コース目までは3つの薬を投与しますが、9コース目からはGCD療法と投与方法が異なります。9コース目以降は、1日目に吐き気止めの点滴後に塩酸ゲムシタビン+ペムブロリズマブ、8日目に吐き気止めの点滴後に塩酸ゲムシタビンのみ投与し、15日目はお休みです。22日目から次のコースが始まります。つまり、GCD療法においては、9コース目以降は免疫チェックポイント阻害薬だけを投与しますが、GCP療法では9コース目以降も塩酸ゲムシタビンと免疫チェックポイント阻害薬を併用して継続することになります。塩酸ゲムシタビン、シスプラチンは1回に投与する量を身長と体重から算出した体表面積をもとに決定します。一方、デュルバルマブは体型に関係なく、1回1500mgを投与します。ペムブロリズマブは、3週おきの投与の場合は200mg、6週おきの投与の場合は400mgとなり、投与間隔によって異なります。副作用の程度によって、吐き気止めをさらに追加したり、1回の薬の量や治療スケジュールを調節することで、患者さんに負担にならないように可能な限り継続していきます。当院では初回の導入時には入院していただきますが、投与方法が安定すれば基本的には外来での治療継続となります。外来治療は投薬日に来院し、採血、担当医の診察を受けていただきます。検査、診察の結果投与可能と判断されたら外来化学療法室で投与を行います。
塩酸ゲムシタビン+シスプラチン+S-1併用療法(GCS療法)
2018年にGCS療法とGC療法の有効性を比較したKHBO1401-MITSUBA試験の結果が本邦より報告され、GCS療法がGC療法と比較して生存期間を延長することが示されました。それを受け、切除不能胆道がんに対する化学療法の新たな選択肢の一つとなりました。塩酸ゲムシタビンとシスプラチンを2週間ごとに1回投与すると同時に、最初の7日間にS-1を内服する治療です(1投1休)。この2週間を1コースとして継続していきます。副作用としては、下痢、口内炎、皮疹が他の治療法と比較して多く発現しますが、その他の副作用については差がないとされています。当院での外来治療は、塩酸ゲムシタビンとシスプラチンの投与日に来院していただき、採血、担当医の診察後に投与可能なら外来化学療法室で2つの薬剤を投与します。S-1は担当医の指示通りにご自宅で内服していただきます。
塩酸ゲムシタビン+S-1併用療法(GS療法)
切除不能胆道がんに対する化学療法の臨床試験として、本邦でJCOG1113試験(GC療法とGS療法の比較試験:国内第Ⅲ相試験)が行われ、GC療法に対するGS療法の非劣性が証明され、GS療法も1次治療のひとつとして日常診療で実施可能となりました。前に述べた塩酸ゲムシタビンに加えS-1という飲み薬を同時併用します。塩酸ゲムシタビンは週に1回2週間続けて投与(通常コース1日目と8日目)、S-1は2週間連日内服し、次の1週間は塩酸ゲムシタビン、S-1ともにお休みです(2投1休)。この3週間を1コースとして継続していきます。当院での外来治療は塩酸ゲムシタビン投与日に来院していただき、採血、担当医の診察後に投与可能なら外来化学療法室で塩酸ゲムシタビンの点滴を行います。S-1は担当医の指示通りにご自宅で内服していただきます。
塩酸ゲムシタビン単独療法
塩酸ゲムシタビンのみの、1週間に1回の点滴治療です。まず予防的に吐き気止めの点滴を15〜30分で行います。続いて塩酸ゲムシタビンの点滴を30分で投与し、最後に生理食塩水を点滴します。1回の治療に要する時間は約1時間前後です。これを3週間続けて投与し、次の1週間はお休みです(3投1休)。この4週間を1コースとして繰り返していきます。当院での外来治療は投薬日に来院していただき、採血、担当医の診察後に投与可能なら外来化学療法室で行います。
S-1単独療法
S-1は体表面積や腎機能から投与量が決まり、朝夕2回に分けて食後に内服します。通常はこれを28日間(4週間)連日内服し、その後14日間(2週間)はお休みとなります(4投2休)。この6週間を1コースとして繰り返していきます。患者さんによっては、2投1休を1コースとして繰り返すこともあります。
全身化学療法の副作用
副作用は個人によって差がありますが、代表的なものを以下に示します。すべての薬に共通する副作用としては嘔気、嘔吐、便秘、下痢などの消化器症状、倦怠感、食欲不振、一時的な発熱、皮疹等が代表的です。これらに対しては多くの場合、内服薬や注射薬での対症療法で対応が可能ですが、程度が強い場合には抗がん剤の減量(白血球減少、貧血、血小板減少など)や肝障害、腎障害があります。塩酸ゲムシタビンに特徴的で注意するべき副作用として、頻度は多くありませんが、間質性肺炎があります。間質性肺炎が起こると命に関わることもあり、投薬中止、酸素投与やステロイド治療を考慮しなければなりません。息切れや空咳が続く場合には担当医にご連絡ください。他の抗がん剤で多く見られる脱毛はこれらの薬剤では頻度はそれほど高くなく、起こっても軽いと言われています。その他、S-1に特徴的な副作用として、口の粘膜が荒れる口内炎、爪や皮膚が黒ずんでくる色素沈着などが挙げられます。口内炎に対しては外用薬の塗布や痛み止めを含んだうがい薬などで対応します。色素沈着に対しては、それ自体で体調に悪影響を及ぼすことはないので特に対処はしませんが、特に気になる場合は担当医にご相談ください。また、シスプラチンに特徴的な副作用としては、嘔気・嘔吐、高度な骨髄抑制、腎障害が挙げられます。腎障害を予防するために大量の点滴を投与する必要があります。副作用に対しては、早期発見・治療、抗がん剤の休薬・中止で対応します。ここに挙げていない予測できない副作用が現れることもありますので、気になる症状がありましたら、遠慮なく担当医にご相談ください。
免疫チェックポイント阻害薬を投与した場合は、その他の抗がん剤とは異なる副作用があります。免疫関連有害事象と呼ばれており、正常組織に対する過剰な免疫反応が原因とされています。内分泌異常(甲状腺、副腎、下垂体など)、糖尿病、腸炎、肝障害、筋炎、皮膚障害、肺炎、腎炎などが代表的なものです。投与後早期に出現するものから、数ヶ月後に出現するものまで様々であり、問診や血液検査などで随時副作用の有無を評価します。ここに挙げていない予測できない副作用が現れる場合もありますので、気になる症状がありましたら、遠慮なく担当医にご相談ください。
ホルモン(内分泌)薬
該当なし
分子標的薬
化学療法後に増悪したFGFR2融合遺伝子/再構成陽性の切除不能な胆道がんの治療薬としFGFR阻害薬があります。FGFR2融合遺伝子/再構成は、がんの原因となる異常な遺伝子であり、FGFR遺伝子が他の遺伝子と融合して発生します。FGFR2融合遺伝子/再構成が存在すると、腫瘍細胞の増殖につながります。その働きを抑えるのが、FGFR阻害薬です。現在使用可能なFGFR阻害薬としては、ペミガチニブ、フチバチニブ、タスルグラチニブの3剤で、いずれの薬剤も飲み薬です。FGFR2融合遺伝子/再構成は、採取したがん組織を用いて調べます。FGFR2融合遺伝子/再構成は、日本人の肝内胆管がん患者で7.4%、肝門部胆管がん患者で3.6%の頻度で認められます。ペミガチニブは、14日間服用した後、7日間休薬します(2投1休)。この3週間を1コースとして繰り返していきます。フチバチニブとタスルグラチニブは連日服用します。副作用としては、爪の障害、眼の障害、腎障害などがあります。
免疫チェックポイント阻害剤
「薬物療法 抗がん剤 (1)」 をご参照ください。
放射線療法
根治的放射線治療
切除可能な胆のう・胆管がんは手術療法が第一選択となりますが、手術が難しい場合、高齢や合併症がある場合、又手術を希望されない場合などに根治的放射線治療を選択することが可能です。治療効果の改善を期待し、抗がん剤(S-1, シスプラチンまたは塩酸ゲムシタビンなど)を放射線治療期間中に併用することがあります(化学放射線療法)。治療期間は、概ね5〜6週間程度です。
特に胆管がんでは、体の外から放射線を照射する通常の外照射に加えて、小さな放射線の線源を胆管内に短時間挿入する小線源治療を併用する場合があります。
さらに当院では放射線治療の治療効果を高める目的で温熱療法(後述)の併用が可能です。
手術療法後の再発予防を目的とした放射線治療
手術の後にがん細胞が残っている可能性が高い際に、放射線治療を追加することがあります。治療効果の改善を期待し、抗がん剤を放射線治療期間中に併用する場合があります。治療期間は、概ね5〜6週間程度です。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
胆道内や腹部リンパ節の再発、あるいは少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加え救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、鎖骨上・縦隔・骨盤などのリンパ節転移、肺や肝臓の転移、骨転移などが対象となります。治療した腫瘍の高い制御効果が期待できます。
緩和的放射線治療
他の臓器へ多数個の転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。胆道閉塞に伴う黄疸や肝機能障害の改善、出血の止血や疼痛の鎮痛、また骨転移に伴う疼痛や神経症状の緩和を目的に行います。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。治療期間は3週間以内が多く、状況に応じて1回のみの治療も選択可能です。
脳転移に対する放射線治療
脳転移を生じた場合に放射線治療が有効です。当院では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いた定位放射線治療(ピンポイント照射)が可能です。患者さんに負担の少ない短い治療時間で、脳転移の高い制御効果が期待できます。
温熱療法 (ハイパーサーミア)
当院では、胆のう・胆管がんに対して放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める目的で温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。パット内の液体を還流させ、皮膚表面の熱感や痛みを抑えます。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
胆道がんは早期発見、早期治療が最も予後を左右します。外科、内科共に協力して最善の治療を患者さんが受けられるように努力致します。いつでも気軽にご相談ください。
産業医科大学 医学部 第3内科学
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/3nai/homepage/m_kenkyu_tansui.html
産業医科大学 医学部 第1外科学教室 肝胆膵グループ
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/1geka/m_group2.html
産業医科大学病院 放射線治療科
https://www.radiationoncol.com/