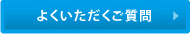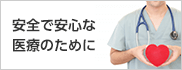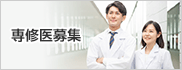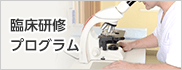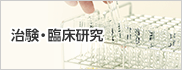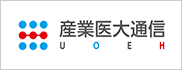食道がん
病気について
国立がん研究センターがん対策情報センターのがん統計によると、2020年に食道がんと診断された患者さんは24,558人 (がん全体の2.6%)で、男性20,128人、女性4,430人で、男性が女性に比べ約4.5倍の罹患数でした。食道がんは全体では11番目に多い罹患数でありましたが、 男性に限ってみると胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、肝臓がんに次いで6番目に多い罹患数でした。発症年齢は男女ともに60歳代後半に多い状況でした。
食道がんの特徴として、喫煙と飲酒が明らかな危険因子であること、胃・大腸がんに比べて比較的進行が早い傾向を示すこと、などが挙げられます。すなわち、食道がんは胃・大腸がんと比較して命に影響を及ぼす可能性がより高い消化管がんであり、早い段階での発見と治療が望まれます。
診断について
食道がんの診断は、内視鏡検査やX線造影検査による食道がんの広がりや深さの評価と、CT検査などによるリンパ節や遠隔臓器への転移の評価により行います。これらの検査データを詳細に評価し、総合的に判断することで、個々の食道がんに対する適切な治療法を選択します。
病変の広がり・深さについて
上部消化管内視鏡検査
内視鏡検査は食道がんの発見においても重要で、なかでも壁深達度が粘膜および粘膜下層までにとどまる食道表在がんでは、約8~9割の症例で内視鏡検査が発見の契機となっています。しかも、これらの食道がん患者の半数以上は発見時に何ら症状を有していないことから、定期的な内視鏡検査が食道がんの早期発見に如何に重要であるかを裏付ける結果と言えます。検査では、通常の観察方法に加え、粘膜表面の毛細血管や微細模様を強調表示する狭帯域光観察(以下NBI)やルゴール液撒布(ヨード・グリコーゲン呈色反応を応用したもので、正常食道粘膜とは異なりグリコーゲンを有さない食道がんの部分は不染帯として認識されます)による色素内視鏡観察を行い、癌の広がりや壁深達度の評価を行います。上記の検査で癌の深さが分かりにくい場合は、超音波内視鏡検査(以下EUS)を行い、より正確な壁深達度評価を行います。
食道X線造影検査
本検査は造影剤(通常はバリウム)を飲んで、食道に存在する病変の形状を評価する方法です。近年の内視鏡機器 の進歩により、食道表在がんの発見契機におけるX線造影検査の占める割合は11%程度と内視鏡検査のそれには遠 く及びません。しかし、食道がんの広がりや壁深達度を評価する上では、X線検査は内視鏡検査に比べて客観的評価が 可能で、食道進行がんのみならず表在癌においても有用な検査で、内視鏡検査のみでは診断が困難な場合にX線検査を併用して行います。
病変の転移について
リンパ節や遠隔臓器への転移の有無については、CT検査をまず行い、必要に応じてFDG-PET検査を行います。FDG-PET検査は、ブドウ糖に近い成分の検査薬(FDG)を血管に注射した後に、PETカメラで全身へのFDGの分布を撮影する検査法です。これは、がん細胞が正常な細胞の3〜8倍のブドウ糖を取り込むほど活動が活発であるという特徴を利用したもので、がんが全身にどの程度広がっているかを一度に判定することができます。また場合によっては、超音波内視鏡検査や骨シンチグラフィーを追加して、リンパ節転移や骨転移などの詳細な評価を行います。
手術療法
手術は最も一般的な治療法であり、がんを含めた食道を切除します。同時にリンパ節郭清(リンパ節を含む周囲の組織を切除)を行います。食道を切除した後には新しい通り道を再建します。
食道はがんの発生部位(頸部、胸部、腹部)や、がんの進行状況によって選択される術式が異なる場合があります。標準的な術式は、頸部・胸部・腹部の3領域に及ぶリンパ節郭清を行い、食道を切除する方法です。
従来は開胸(大きく胸を開く)し、癌を切除、開腹(大きくお腹を開く)し、胃を用いて再建(胃管作成)する手術が多く行われてきました。現在は内視鏡下手術(胸腔鏡下食道切除術・腹腔鏡下再建術)にて、小さい傷での手術が可能となりました。
当院では、2008年から腹臥位(うつぶせ)での完全鏡視下食道切除術(胸部操作)を、2009年から腹腔鏡下での胃管作成と腹腔内リンパ節郭清(腹部操作)を導入しています。現在は、ほぼ全ての食道癌患者に対して完全鏡視下手術を施行しております。内視鏡下手術は、小さい傷により術後の痛みが少なく、早期回復が可能であり、整容性にすぐれています。さらに出血量が少ない、大きな画面(拡大視効果)でより精度の高い手術が可能、術後の癒着が少ないなどの利点があります。
手術後は、出来るだけ早く元の生活に戻ることができるようするために、積極的なリハビリ、感染への予防対策、栄養管理、退院後の生活指導など、多岐にわたる支援と介入を行っています。
内視鏡的治療
食道がんは他の消化器癌に比べ早期でもリンパ節転移を起こしてくるため、早期がんの定義は粘膜(食道の壁の最も浅い層)内にとどまるがんとされています。粘膜層は、上皮、粘膜固有層、粘膜筋板(粘膜層の深い所にある細い筋肉の層)に分かれますが、がんが上皮や粘膜固有層にとどまるものはリンパ節転移が極めて稀であるため、内視鏡的切除のよい適応となります。がんが粘膜筋板に及ぶものやわずかに粘膜下層(粘膜層の下にある層)に入ったものは、10-20%の確率でリンパ節転移を認めるため、一般的には内視鏡治療の適応ではありません。術前検査でリンパ節転移を認めないものに対して、全身状態を考慮した結果、侵襲がより少ない内視鏡的治療が行われる場合もあります。
早期食道がんに対する内視鏡治療は患者さんへの侵襲度、入院期間、コストの面からも外科治療と比較して利点があり、通常は約1週間程度の入院治療となります。内視鏡治療は大きく2つに分類されます。内視鏡的粘膜切除術(EMR)と内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)です。従来法であるEMRは、病変の下の粘膜下層に生理食塩水やヒアルロン酸ナトリウムなどの液体を打ち込んで病変を挙上し、スネア(針金でできた輪っかのようなもの)で縛って、電気をかけて切りとる方法です。この方法の欠点としては病変が大きくなると分割切除(病変をいくつかの組織片に分割して切除すること)となり、不完全切除(がんを取り残す)の可能性があります。その結果、治療後に局所再発(切除した近くに癌が再発すること)を起こしやすいというデータがあります。一方ESDは、病変を含めた組織を電気メスを用いて切開・剥離していく方法で、大きさにかかわらず、病変を一括切除(病気を1つの塊で切除すること)が可能となり、一括切除した組織を顕微鏡検査により詳細に調べることにより、病気の深達度(深さ)や転移のしやすさを正確に診断することができるようになりました。当院では、食道癌に対する内視鏡治療では、ESDを選択することがほとんどです。
局所的治療(経皮的治療、カテーテル治療など)
該当なし
薬物療法
抗がん剤
切除可能食道がんに対して(術前化学療法、術前化学放射線療法)
食道がんの広がりがステージⅡ期やⅢ期で切除術を行う場合には、手術の前に5-FUとシスプラチン、ドセタキセルの3剤併用化学療法を2−3コース実施することで治療成績が改善することが知られており、標準治療となっています。5-FUとシスプラチンの併用化学療法を2コース実施することでも治療成績が改善することが知られており、放射線療法を併用した化学放射線療法を含め、年齢や体力に応じて治療をおこなっています。
食道がんの広がりが食道だけである場合や近くのリンパ節転移のみに限られている場合は、手術などによる切除術が一般的です。しかし、がんが周囲の臓器に浸潤している場合や、食道がん以外の合併症がある場合など切除術が選択できない際には、代わりの方法として化学放射線療法が選択されます。病巣部に対する放射線照射に加え5-FUとシスプラチンを同時に投与する方法が多く行われています。
比較的早期であるが内視鏡的切除の対象でないステージⅠ期の食道がんに対しては、化学放射線療法も切除術と同等の治療成績が期待できます。また、食道がんの広がりが比較的狭い範囲であるステージⅡ期や食道がんが隣接する臓器までは浸潤していないステージⅢ期(T4を除くⅢ期)の場合には、化学放射線療法は手術療法に次ぐ治療効果が得られると考えられており、当院でも手術困難あるいは手術を希望されない方への治療としてお勧めしています。
切除不能食道がんに対して(化学療法・免疫療法)
食道がんが、食道以外の離れた臓器にも転移している場合などはステージⅣ期となります。この場合には、がんを全て取り除く外科的切除術は難しく、放射線照射も広範囲に行うことが困難なため、抗がん剤を用いた全身化学療法を行うことが一般的です。主に5-FUとシスプラチンを用いた治療が基本ですが、近年では免疫チェックポイント阻害薬を併用することで、体の免疫力を高め、がん細胞を効果的に攻撃できるようになりました。さらに、免疫チェックポイント阻害薬を2剤併用することや、5-FUとシスプラチンにドセタキセルを追加した3剤併用療法、パクリタキセル、S-1などの抗がん剤を用いることもあります。免疫チェックポイント阻害薬の選択については、患者さんの食道がんの診断や治療の際に得たがん組織を用いてPD-L1という蛋白を調べたり、患者さんの病状、腫瘍の量、全身状態などを考慮し選択します。免疫チェックポイント阻害薬の登場以前は、がんの進行を抑える効果が限定的で、新たな治療法が求められていました。しかし、これらの新しい治療法により、延命効果や腫瘍縮小効果がより期待され、進行したがんの一部では手術が可能になるケースも経験するようになっています。
放射線療法
根治的放射線治療
早期食道がん: ステ-ジ0-I
内視鏡的治療が難しい場合に根治的放射線治療を行います。ステージIでは、抗がん剤を同時に併用する化学放射線療法が有効です。この化学放射線療法は手術と同等の成績が得られます。食道の嚥下機能を温存できる大きなメリットがあります。
切除可能進行食道がん: ステ-ジII-III(T4を除く)
抗がん剤を先に行い、腫瘍を縮小させた後に手術を行うことが多いステージですが、根治的な化学放射線療法も選択可能です。手術を希望されない場合や、全身の状態が手術に適さない場合に行います。化学放射線療法では、完全奏効した場合に食道の嚥下機能を温存できるメリットがあります。当院では、放射線治療の治療効果の改善を目的に、温熱療法(後述)の併用を選択可能です。
進行食道がん: ステ-ジIII (T4)およびIVa(遠隔リンパ節転移)
根治的な化学放射線療法を行います。T4(隣接する臓器浸潤)が疑われる場合に、手術を前提として抗がん剤を先に行うこともあります。
当院では上記の根治的放射線治療において肺や心臓などの隣接する正常臓器への放射線の照射線量を低減する高精度な照射手法”強度変調回転放射線治療
(VMAT)”を採用しています。心臓の機能障害や放射線肺臓炎などの副作用リスクの軽減が期待できます。
手術療法後の再発予防を目的とした放射線治療
内視鏡的治療や手術で摘出した食道がんの遺残がある場合や周囲への浸潤が強い場合などに、再発予防を目的とした放射線治療を行います。再発や転移を生じるリスクが高い場合には、抗がん剤を併用することがあります。
少数個の再発・転移に対する救済的放射線治療
食道やリンパ節(鎖骨上、縦隔や腹部)の再発、または少数個(1~3個程度)の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加え救済的な放射線治療を選択することが可能です。遠隔転移の部位は、肺や肝臓の転移、骨転移などが対象となります。治療した腫瘍の高い制御効果が期待できます。
脳転移に対する放射線治療
脳転移を生じた場合に放射線治療が有効です。当院では、強度変調回転放射線治療(VMAT)を用いた定位放射線治療(ピンポイント照射)が可能です。患者さんに負担の少ない短い治療時間で、脳転移の高い制御効果が期待できます。
緩和的放射線治療
他の臓器へ多数個の転移を生じている状況では、緩和的な放射線治療が適応となり得ます。食道がんによる嚥下困難の改善、出血の止血や疼痛の鎮痛、また骨転移に伴う疼痛の鎮痛、神経症状の改善といった症状緩和に有効性が高いです。緩和的放射線治療に必要となる放射線量は少ないため、治療に伴う副作用は軽微です。治療期間は3週間以内が多く、状況に応じて1回のみの治療も選択可能です。
温熱療法(ハイパーサーミア)
当院では、食道がんに対して放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。パッ ト内の液体を還流させ、皮膚表面の熱感や痛みを抑えます。1回の加温時間は40~60分程度で、週に1~2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。
セカンドオピニオンの受け入れ
( 可 )
患者さんにメッセージ
食道がんの治療は病気の進み具合とからだの状態とによって選択されます。上記の治療は単独で行われることもありますが、組み合わせて行なわれることもあります。私たちは消化器内科、消化器外科、放射線科などで密に連携を取り、患者さんのご希望も聞きながら最もよいと思われる治療をお勧めしていくことを常に心がけています。
産業医科大学 医学部 第3内科学 消化管グループ
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/3nai/homepage/m_kenkyu_syouka.html
産業医科大学 医学部 第1外科学 上部消化管(食道・胃)グループ
https://www.uoeh-u.ac.jp/kouza/1geka/m_group1.html
産業医科大学病院 形成外科 診療案内
産業医科大学病院 放射線治療科