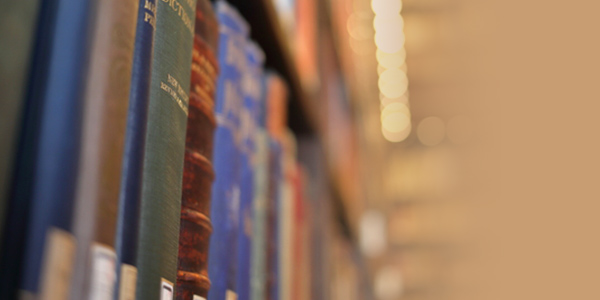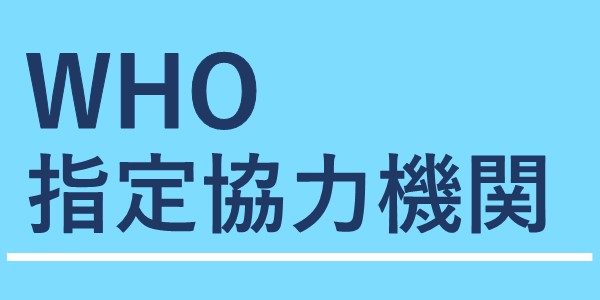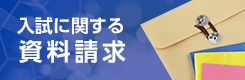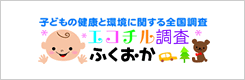2016 第14号 <No.73>(10月31日配信)、第15号 <No.74>(10月31日配信)、第16号 <No.75>(11月21日配信)、第17号 <No.76>(12月21日配信)
2016年第14号 <No.73> 平成28年度コシン大学との交換医学教育を実施(10月31日配信)
2016年第15号 <No.74> 平成28年度 JICA国際研修「食品安全行政コース」の受入(10月31日配信)
<平成28年度 JICA国際研修「食品安全行政コース」の受入>
平成28年10月27日(木)午前、JICA国際研修「食品安全行政コース」に参加している全12ヶ国から計13名の研修員を本学にて受入れました。産業生態科学研究所 職業性中毒学の上野 晋 教授が講義「Toxicity of Chemical Contaminants in Food」を行いました。
講義の様子 1 講義の様子 2
2016年 第16号 <No.75> JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン)の実施(11月21日配信)
<JST日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン)の実施>
国際交流センターは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が主催する「日本・アジア青少年サイエンス交流事業(さくらサイエンスプラン)」に採択され、11月6~12日の期間、中国の山東省医学科学院より大学院生9名、引率者1名の計10名を迎え、平成26年度に引き続き、2回目の実施となりました。
「災害医学と産業保健の接点を探る日中交流」をテーマにした今回のプログラムでは、本学教員の他、救急救命九州研修所 郡山教授、熊本大学医学部附属病院 谷口先生、国立水俣病総合研究センターの先生方にご講義いただきました。日本国内の災害経験に基づく講義に、熱心に聞き入る院生達の積極的な姿勢が印象的でした。また、本学の留学生との交流会や北九州市内文化施設の視察も実施し、日本への理解、興味がより一層深まった様子でした。この機会が、個人としての日本への興味、関心だけに留まらず、機関や国レベルでの相互理解、協力関係の礎になることを願っています。
最後に、このような機会を与えていただいた国立研究開発法人科学技術振興機構、ご講義を引き受けていただいた先生方、関係者の皆様に深く御礼申し上げます。
福岡空港到着 東学長を表敬訪問 本学主催の国際遠隔講義に参加
山東省医学科学院の紹介 講義中の様子 市内視察
小倉城にて プログラム修了
2016年第17号 <No.76> 平成28年度 国際遠隔講義の実施(12月21日配信)
<平成28年度 国際遠隔講義を実施しました>
今年度は、9月13日~12月20日の毎週火曜日、全15回の国際遠隔講義を実施しました。国立台湾大学を中心にインターネット回線にてブルネイ大学、コンケン大学(タイ)、アテネオデマニラ大学(フィリピン)を繋ぎ、リアルタイムに講義を提供または受講するというものです。各講師からは、産業医学を主に幅広い分野からの講義が提供され、講師、受講者間では活発な質疑応答、意見交換がみられました。
本学からは下記の4名が講義を提供しました。
<9月13日>
「弁膜症の心エコー診断について」 第2内科学 尾辻 豊 教授
コーディネーター: 中田 光紀 教授
<10月18日>
「鉱物油暴露と自己免疫疾患」 成人・老年看護学 佐藤 実 教授
コーディネーター: 中田 光紀 教授
<11月15日>
「アスベスト関連疾患のグローバルな状況」 環境疫学 チメドオチル オドゲレル 助教
コーディネーター: チメドオチル オドゲレル 助教
<12月13日>
「日本におけるアスベスト関連疾患の労災補償の法規制-肺がんを中心に-」 呼吸病態学 森本 泰夫 教授
コーディネーター: チメドオチル オドゲレル 助教