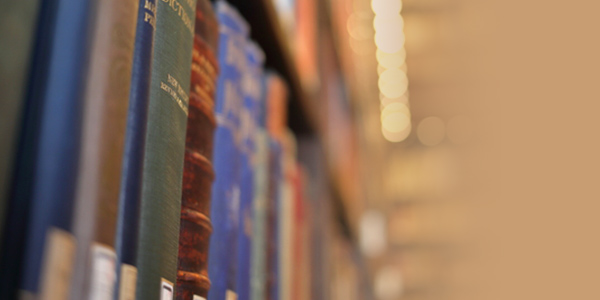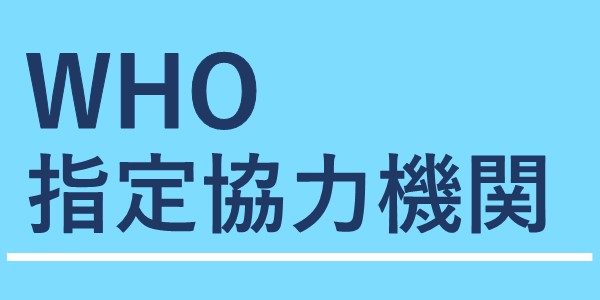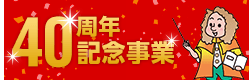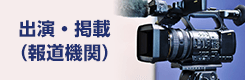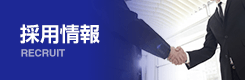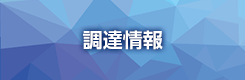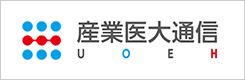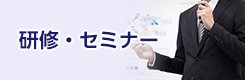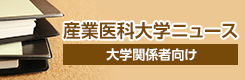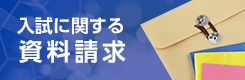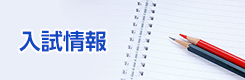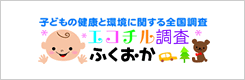学校法人 産業医科大学 第4次中期目標・中期計画
本学の第4次中期目標・中期計画となります。
数値目標の一部を見直しました。(令和5年3月17日理事会承認)
期間:令和4年4月1日から令和10年3月31日
| 1 教育 | |||
|
長 |
産業医学・産業保健を通して社会の成長発展に寄与できる人材、また、人間愛に徹し、生涯にわたって哲学する豊かな人間性と高い倫理観、行動力を備え、多様性を尊重する人間力のある人材を育成する。 |
||
|
◆第4次中期期間中の 教育 に係る主な数値目標
|
|||
| (1) 産業医学・産業保健を通じて社会に貢献するプロフェッショナル人材の育成 | |||
|
①
豊かな人間性と高い倫理観、行動力を備えた人間力のある人材を育成する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
目標 | 計画 | |
| 記述 | 変更後 数値 | ||
|
両学部の教育においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、高い倫理観及びコミュニケーション能力を備えた人間性豊かな産業医・産業保健専門職を養成する。 |
医学部
進級率 |
低学年時に、幅広い教養、高い倫理観及びコミュニケーション能力を身に付けさせる教育を行う。中学年次から高学年次にかけて、専門的知識、科学的能力、想像力及び実践力を身に付けさせる教育を行う。全学年を通じて課題解決型教育を推進し、学生が主体的に学習するアクティブラーニングを行う。 |
|
|
両学部の入試においては、本学の設置目的及びアドミッション・ポリシーを理解し、産業医学・産業保健を通じて社会に貢献する人材を輩出するため、優秀な学生を確保する。 |
(再掲) |
本学の魅力(医師免許と産業医資格の同時取得、医学部卒業後の多彩なキャリア設定、看護学科の国家試験の高い合格率、産業衛生科学科の高い就職率等)を伝える広報活動を充実し、求める学生像を明確にし、入学者選抜方法等について、選抜の複数化や試験日程の見直しを図るなど、入試環境の変化に即応した入試制度改革を実施する。
|
|
|
大学院教育においては、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づき、高度な研究能力と豊かな学識、国際的に通用するグローバルな能力を有する人材を養成するとともに、医学、産業医学、産業衛生学及び看護学の発展に貢献する。 |
(再掲) |
学術研究の進歩や高度化、社会の変化に対応するため、大学院の教育・研究のあり方について必要な検討を加え、その充実を図る。 |
|
|
大学院は、各専攻のアドミッション・ポリシーを理解し、自らが主体的かつ積極的に課題に取り組み、解決する能力を有する学生を受け入れる。 |
(再掲) |
18時以降の授業の設定、オンライン講義の実施など社会人大学院生が受講しやすい環境を整え、専門医資格を取りながら、大学院の履修が可能であることを強調した効果的な大学院生募集を展開し、入学者を増加させる。 |
|
| 長期ビジョン | (2) 医学、看護学、産業衛生学を基に人材教育のベースとなる専門分野の卒前、卒後教育の強化 | ||
|
①
学生が自ら主体的に学べるようICTを活用した支援を行う。 |
|||
|
第4次中期目標 ・中期計画 |
両学部ともにICTを活用した学習支援を行う。 |
学習評価システムの利用率
100% 毎年度 |
学生が主体的に学べるよう学習評価システム等のICT(病院実習用eポートフォリオ、eラーニング)を活用した支援を行う。 |
|
医学部は、基本的な教養と、基礎医学と連携させた臨床医学を学ばせ、更に6年間を通じ系統的な産業医学教育を実施し、優れた産業医を養成するための質の高い教育を行う。 |
授業評価 3以上/4段階評価 毎年度 |
医学教育をベースとして、医学的総合力を身に付けさせるとともに、産業医学教育については、1年次から6年次まで系統的に産業医学関連科目を履修することにより産業医志向を育む。優秀な産業医を育成するための教育内容について検証し、改善を継続的に行う。 |
|
|
医学部の課題探求、解決能力を向上させる教育方法を整備するとともに、厳格な成績評価を引き続き実施する。
|
研究室配属時の研究目標達成度 |
医学部の研究室配属や臨床実習等において、引き続き少人数対話型教育を推進する。 |
|
|
共用試験の合格率 95%以上 毎年度 |
臨床実習に臨む学生の質を担保するため、臨床実習開始前の学生に行う共用試験(CBT・OSCE)を厳正に利用する。また、卒業後の臨床研修に臨む学生の質を担保するため、臨床実習終了後の学生に行う共用試験(Post-CC OSCE)を厳正に利用する。 |
||
|
時代の要求に応える医学教育課程の策定、改善計画の立案を行い、教育環境を整備する。 |
医学教育分野別評価の認証 |
医学部の教育課程、教育方法の改善を行い、医学教育分野別評価を受審する。その結果に基づき教育課程、教育方法の更なる改善を検討する。また、新カリキュラムが進行後、多角的な評価を行い、次期のカリキュラム改定について検討を開始する。併せて、クリニカル・シミュレーション・ラボの運営を通じ臨床教育の促進に寄与する。 |
|
|
看護学科は、看護基礎教育をベースとし、看護実践能力があり、産業保健マインドを持った看護師、保健師を養成するための質の高い教育を行う。 |
授業評価 平均4.2以上 毎年度 |
看護実践の基盤となる知識、理論、技術を学ばせ、病院等との連携により看護実践能力を身に付けさせる。産業保健看護学の特色ある専門教育を実施し、産業保健師としての実践能力を持った人材を養成する。併せて、臨地実習に臨む学生の質を担保するため、自己の看護実践能力の修得状況及び課題を把握する。 |
|
|
産業衛生科学科は、労働安全衛生の専門職として活躍できる人材を養成するための質の高い教育を行う。 |
授業評価 平均4.2以上 毎年度 |
作業環境管理、作業管理、健康管理の三つの柱を体系的に教育し、労働安全衛生の専門職として活躍できる人材を養成する。 また、自律的化学物質管理における高度な産業衛生技術者を養成する。 |
|
|
両学部における教育内容や方法の組織的改善と教員の教育能力の向上を図る。 |
授業評価回答率
80%以上
毎年度 |
質の高い教育を行うため、授業評価を行い、その評価に基づいたPDCAを実施するとともに、教員FDを計画的に実施する。 |
|
|
国家試験の合格率について、高い水準を維持し、卒業生全員が国家資格を有する。
|
(再掲)医師国家試験全国順位 |
医師国家試験結果の分析、国家試験の情報をすべての教員に周知し、授業、試験等を通して通常教育に加え、5年次生以下の学年も含め、大手予備校の模擬試験や医師国家試験対策講義等により、学生指導を強化する。 |
|
|
(再掲)看護師・保健師国家試験全国平均合格率を5ポイント以上上回る |
看護師・保健師国家試験結果の分析、試験の情報をすべての教員に周知し、授業、試験等を通して学生指導を強化する。 |
||
|
大学院における外国人留学生の教育活動に取り組む。 |
外国人留学生の受入れ 2名以上/年 |
外国人留学生を積極的に受け入れ、大学院教育の充実と国際化を図る。 |
|
|
卒業後も含めた産業医等の研修プログラムの充実を図る。
|
産業医学基本講座 本学卒業生修了者150名以上/6か年 |
本学の卒業生を対象に産業医学に関する教育(講義と実習)を体系的かつ集中的に行い、産業医として保持すべき知識と能力を付与する。 |
|
|
他学卒業生を含む産業医学実務講座の受講者 100名以上/年 |
産業医学実務講座の高次専門職教育に、本学卒業生に加え他学卒業生を積極的に受け入れ、専門的実務能力の高い産業医の養成を図る。 |
||
|
産業保健コアカリキュラムの評価 4.0以上 毎年度 |
産業医学卒後修練課程を修了した医学部卒業生を対象に、「産業保健コアカリキュラム」を実施し、マネジメント能力の向上を図る。 |
||
|
産業看護実務研修の満足度
80%以上 |
産業保健学部看護学科卒業生を対象に、「産業看護実務研修」を実施し、産業保健師としての実務能力の向上を図る。 |
||
|
受講者による評価満足度
80%以上 |
急性期診療棟の産業医学臨床センター(仮称)及び両立支援室(仮称)において、産業医として必要な実践的な能力を向上させるため、作業環境管理、作業管理及び健康管理への理解を深める教育等を行う。 |
||
|
専攻医新規登録者数
70名以上/年
|
社会医学系及び臨床領域ごとの専門医の資格取得の促進を行う。 |
||
| 長期ビジョン | (3) 日本を代表し世界をリードする産業医学、産業保健教育の拠点の確立 | ||
|
①
産業医学・産業保健マインドを醸成し、産業医学分野を開拓・牽引できる人材を輩出する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
専門性及び実践能力に優れた産業医を養成する。
|
(再掲) |
産業医学教育を1年次から6年次まで各学年に亘り系統的に実施し、指導的立場になる産業医、産業保健の中核となる産業医を数多く養成する。6年間で420名以上の常勤の産業医の輩出を目指す。 |
|
メンター制度活用率 90%以上/年 |
離脱者防止対策を積極的に実施し、各講座等においてPDCAを回し、メンター制度を活用してマンツーマンでのきめ細かい指導を行うとともに、産業医の魅力の発信を積極的に行う。 |
||
|
前期課程から後期課程移行時の離脱者数 180名以内/6か年
|
産業医学卒後修練課程について、離脱者防止対策に積極的に取り組み、実践力・指導力に富む産業医を多数輩出する。また、キャリア形成プログラムの取組等、卒業生の多様なキャリア形成を支援する。 |
||
|
(再掲)教育(2) |
(再掲)教育(2)専門医 |
||
|
医学部の進路指導の充実を図り、産業医学に従事する者の増加を図る。
|
求人企業
80社以上/年、 |
産業保健情報提供サイトの充実を図り、最新の求人情報を提供する。また、卒業生の希望に沿った求人先の開拓に努め、産業医への就職支援の充実を図る。 |
|
|
産業保健情報提供サイトへの新規登録 40名以上/年
|
産業保健情報提供サイトに産業医学に関する情報及び相談の場を提供するなど、卒業生の関係業務への就労に向けた支援を行う。 |
||
|
学生の事業所訪問等プログラム 評価満足度 90%以上/年 |
大学と企業との連携を更に充実し、キャリア形成の支援を行うとともに、本学の設立使命である「優れた産業医の養成」に寄与する。 |
||
|
産業保健学部は、産業保健専門職として活躍できる人材を養成する。
|
(再掲) |
本学の設置目的に沿った教育により更に多くの優秀な産業保健専門職を養成し、進路指導の充実により6年間で460名以上の産業保健関連職場への就職を目指す。 |
|
|
(再掲)教育(2) |
(再掲)教育(2)産業保健人材の育成 |
||
|
産業保健学部の進路指導の充実を図り、産業保健関連業務に従事する者の増加を図る。
|
求人企業
50社以上/年、 |
産業保健情報提供サイトの充実を図り、産業保健関連業務の求人情報の提供を行う。 |
|
|
180名以上/6か年
|
看護学科卒業生の本学病院への就職を推進する。 |
||
|
産業衛生科学科
就職率
100% 毎年度 |
産業衛生科学科卒業生の就職率100%を目指すために進路指導の充実を図る。 |
||
|
卒業生研修会満足度
90%以上 毎年度 |
学科の垣根を超えた産業保健学部卒業生研修会を開催し、産業保健活動への知識と理解を深める。 |
||
| 卒業生受講率 100% 毎年度 |
令和5年度から産業衛生科学科卒業生に対して、衛生工学衛生管理者資格取得のための講習会を卒業直後に実施する。 |
||
|
他学卒業生も含め、社会の要請に応じ、幅広く産業医を養成する。
|
他学卒業医師の産業医養成数 |
産業医学基礎研修会集中講座を実施し、第4次中期計画期間中(6か年)に他学卒業生医師5,000名を産業医として養成する。 |
|
|
他学卒業医師の産業医学基本講座修了者 100名以上/6か年 |
産業医学基本講座等の高次専門職教育を本学及び首都圏で実施し、他学卒業生を広い地域において積極的に受け入れ、幅広く専門的実務能力の高い産業医を養成する。 |
||
|
他学卒の産業医学基本講座、またはインターンシップ事業の修了者の産業医就職 12名以上/6か年 |
他学卒の産業医学基本講座、またはインターンシップ事業の修了者の産業医への就労促進に努め、幅広い産業医の輩出を図る。 |
||
|
首都圏プレミアムセミナー受講者 |
本学が蓄積してきた産業医養成に関する知識を、産業保健専門職を志望する者や技術向上を目指す者に還元する事業として首都圏プレミアムセミナーを実施する。 |
||
| 長期ビジョン | (4)新たな教育シテスムの整備 | ||
|
①
ICTを活用した産業医学分野の卒前教育環境を整備する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
学生が必要とする支援・指導体制を強化することにより、学生が安心して修学できる環境を整備する。 |
Wi-Fiカバーエリア
100%
学生が主に教育を受ける施設(1・2・6号館) |
情報化社会にあってIT技術を用いた情報通信システムをより発展させ、教育システムの充実と学生支援情報の提供に努める。 |
|
在校生の個人面談実施率
100% |
学生支援体制の強化として、指導教員制度、留年生への里親制度、休学中の学生への支援、メンタルヘルス対策としての学生相談室の体制等を充実させる。 |
||
|
(再掲) |
(再掲)教育(3) |
(再掲)教育(3)他学卒業生を含めた産業医の養成 |
|
|
(再掲)
|
交換医学教育派遣学生数 15人以上/年 |
国際的な視野をもった学生を育成するため、海外の医科大学と交流協定に基づく交換医学教育を行う。 |
|
|
産業保健学部学生の海外学術交流 |
海外の産業保健関連学部・学科学生との学術交流を組み込んだカリキュラムを導入し、国際社会で活躍する素養を身に付けさせる。 |
||
|
自己点検評価、第3者評価及びその他評価を実施し、その結果を大学運営の改善に反映させる |
支援件数 5件以上/年 (データ支援、データ分析) |
IR推進センターは教育研究質保証推進委員会等と連携し、自己点検・評価活動等を支援し、教育研究活動の改善を促進する。 |
|
| 2 研究 | |||
| 長期ビジョン |
医学及び看護学その他の医療保健分野において、高い科学性及び倫理観に立脚した、世界をリードする新たな知を創造し、医学・医療に貢献できる研究はもとより、産業医学とそれらの融合的研究を推進する。 |
||
|
◆第4次中期期間中の 研究 に係る主な数値目標 |
|||
| (1)産業医学と他の研究分野との融合発展の推進 | |||
|
①
産業医学と臨床医学を含むその他のライフサイエンスとの融合的な研究を推進する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
医学部、産業保健学部、産業生態科学研究所等の各組織の垣根を超え、各組織の特色を融合した研究を推進する。 |
(再掲) |
産業医学・産業保健重点研究を通じて、研究費配分を行い、産業医学と他の研究分野との融合的に遂行する仕組みを構築する。 |
| 長期ビジョン | (2) 世界をリードする新たな知の創造と産業医学分野の中心拠点形成 | ||
|
①
最先端かつ独創的で国際的にも評価の高い優れた研究を通じ、新たな知の創造とその実践を推進する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
国際水準の研究、国際交流等をより一層推進し、大学評価の上位を目指す。 |
国際交流に係る研修事業等参加者 |
国際的活動の中核組織として設置された国際センターを中心に、本学の国際的地位の向上並びに研究者交流、グループ研修事業及び外国人留学生の招聘等の促進・充実に努める。 |
|
研究機関としての基盤を確立し、産業保健における研究を国内外へ拡大させる。 |
産業保健研究事業への新規参加企業 |
参加企業及び健康保険組合を拡大し、産業保健研究の仕組みのデファクトスタンダードとなり、研究成果を積み上げ、産業医への研究支援を強化していく。 |
|
|
医学・保健分野の研究に加え、産業医学を牽引し、新たな知の創出を国内外に発信する。 |
(再掲)専門誌等執筆及び論文投稿数 120件以上/年(産業医学関連の研究内容に限る) |
研究業績評価に応じた研究費配分を行うとともに、産業医学・産業保健研究の活動を支援する。 |
|
| 長期ビジョン | (3) 産業・社会構造の変化に対応した研究の推進 | ||
|
①
産業・社会構造の変化あるいは自然災害や感染症の流行などに伴い新たに発生した産業医学上の問題に対する研究を推進する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
産業医学及び産業保健の中心として、社会が直面する課題の解決に役立つ成果の創出に努め、研究を推進し、社会への普及を目指す。 |
(再掲) |
本学の特色ある研究を推進し、社会や産業界のニーズに応じた研究に積極的に取り組む。 |
|
産学官連携の推進により、知的創造活動を活性化し、研究の促進を図る。 |
本学の知的財産を基にした公的研究費、共同研究・受託研究の獲得件数 50件以上/6か年 |
産業界、他大学及び行政等の外部機関との連携・協力を促進し、発明をブラッシュアップするための共同研究・受託研究の受入れや社会実装を支援する公的研究費の公募申請を積極的に行うとともに、知的財産の技術移転を推進することにより社会に貢献する。 |
|
|
高年齢労働者の労働災害の予防、産業構造の変化による新たな課題に対応するための研究を推進する。 |
高年齢労働者の健康等に関する学会発表及び論文投稿数 30件以上/6か年 |
高年齢労働者の健康の確保に関係する学内の各部署と横断的に研究調整を行い、高年齢労働者の職業適性及び新たな課題に対応するための研究を行う。その研究成果を活用し社会実装につなげる。 |
|
|
自然災害、新たな感染症の流行など産業保健上の問題に対する研究を推進する。 |
災害産業保健に関する講演・学会発表等
30回以上/6か年 |
災害対応の知見を有する各研究室と協力して集約した研究成果の活用及び災害産業保健の人材育成を行い、災害対策及び災害時に迅速に臨床・産業保健の両面から対応する。 |
|
|
産業医学教育を履修し感染制御の専門的知識を有する医療従事者の認定取得 12名以上/6か年、感染症対策新プログラム受講者 600名以上/6か年 |
あらゆる職域において活躍できる感染症対策及び感染管理教育ができる人材を養成するため、本学独自の産業医学の視点から、新たなプログラムを構築するとともに、卒前・卒後教育における感染管理教育に対応する。 |
||
| 3 診療 | |||
| 長期ビジョン |
産業医学・産業保健を推進する教育機関であり、高度で先進的な医療を行う特定機能病院である大学病院と若松病院が共同して、地域社会における基幹病院としてあり続ける。そして、今後の社会経済構造・疾病構造・就業構造の変化に対応した診療体制を構築する。 |
||
|
◆第4次中期期間中の 診療 に係る主な数値目標 |
|||
| (1) 職業関連疾患専門医療機関としての先進的医療の提供 | |||
|
①
職業関連疾患に関する最先端の診断・治療を行うとともに予防策を策定し、就業・就学との両立も含めた全人的医療を提供する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
職業関連疾患を含め、治療と就業・就学の両立を支援する。 |
両立支援相談件数 |
大学病院内の治療と就業・就学の両立支援を推進し、職業関連疾患を含め、国内で最多の診療実績を目指す。 |
|
がん患者の生活、就労等の支援を実施する。 |
がん相談支援件数 |
がん相談支援センターの周知を積極的に行い、がん患者及びその家族の相談に対応し、適切な支援を行う。勤労世代やAYA世代に対しては、就学・就労支援センターと連携し、就労・就学に対する相談対応及び両立支援も実施する。 |
|
| 長期ビジョン | (2) 特定機能病院としてふさわしい高度で最先端かつ安全な全人的医療の提供 | ||
|
①
北九州市で唯一の特定機能病院、そして「医療の最後の砦」として、先進的医療及び地域のニーズに柔軟に対応した全人的医療を提供する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
特定機能病院及び高度急性期病院としての機能を更に充実させ、地域における高度急性期医療の中核としての役割を着実に果たす。 |
DPC支援システムから抽出したがん入院件数
6,200件以上/年 |
北九州医療圏におけるがん診療のトップを堅持する。更に脳卒中、心筋梗塞、糖尿病等、高齢化により増加する疾病における高度急性期医療の提供機能の強化を図る。 |
|
最先端のがん診療の実施体制を構築する。 |
遺伝カウンセリング加算 |
地域がん診療連携拠点病院及びがんゲノム医療連携病院として、積極的に最先端の診断・治療の実施体制及び遺伝カウンセリングや遺伝子検査を活用できる運用体制を整備するなど、北九州医療圏のがん医療を牽引すべく、機能の充実を図る。 |
|
|
患者第一を基本に科学的根拠に基づく安全かつ質の高い医療を提供するとともに、患者に選ばれる魅力ある病院を目指す。
|
IC新規登録・見直しを行う |
患者への適切なインフォームドコンセントや治療経過に関する十分な説明を行い、患者が納得し、患者の意思を尊重した医療を提供し、ICの説明に対する患者満足度調査を実施する。また、医療安全対策の充実・強化を図るため、医療の質・安全管理委員会及び病院感染防止委員会を月1回開催するとともに、医療安全研修を年2回実施する。 |
|
|
患者満足度調査 外来平均
82.5点以上 入院平均
86.5点以上 |
患者へ調査を実施し、患者サービスの見直しを継続して実施する。 |
||
|
病院収益の継続的見直しを徹底し、安定した病院収益を確保する。
|
(再掲)
|
病院収支を改善するため各診療科及び各部門において目標値を設定し、状況を毎月確認しPDCAを回すとともに経営を意識した運営を促す。 |
|
|
病院長のマネジメントにより、必要な指導を行うとともに、各診療科の状況を把握し、効果的な病院運営を図る。 |
|||
|
急性期診療棟開院を契機とした手術室増による手術件数増、個室配備による効率的な病床利用から、稼働率の更なる向上等、増収実現に向け確実な取組を行う。 |
|||
|
医療制度改革等、外部環境の変化に対応した機能的かつ効率的な病院運営を行う。
|
関係法令の改正に合わせて組織の新設・統廃合等を2件以上検討/年 |
組織運営の見直しを継続して行う。 |
|
|
令和5年度の急性期診療棟の開院に向けた体制の整備 |
急性期診療棟の効率的な高度急性期医療を推進するために、体制を整備する。 |
||
|
パス適用率
47%以上 |
医療の標準化を図るためクリニカルパス有効活用を推進する。 |
||
|
本館
令和4年1月稼働 |
効率的な医療情報システムの運用を図り、継続的な診療及びシステムの安定的稼働を実現するため、システム状況の把握及び定期的なメンテナンスを実施する。 |
||
|
臨床研究を推進する。 |
新規治験件数
32件以上/年 |
治験受託件数の安定した獲得を目指すとともに、臨床研究全般の推進を図り、新たな医療の創出に努める。 |
|
| 長期ビジョン | (3) 地域の人々が安心できる地域基幹病院としての医療体制構築 | ||
|
①
感染症を含む未曾有の災害に備え、必要な先進的医療を過不足なく提供する体制を、福岡県、北九州市及び周辺の医療機関と協力して構築する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
新興感染症の流行に対応すると同時に、地域へ医療の提供を行う。 |
行政等からの要請には可能な限り対応する |
両病院共に、新興感染症への対策をはじめとした院内感染対策の強化を図るとともに、地域の基幹病院として必要な医療の提供に努める。また、行政等からの協力要請にも可能な限り対応する。 |
|
大学病院は、地域全体で支える医療を目指す。
|
紹介患者
19,000件以上/年 |
地域医療機関との緊密な連携を図り、信頼に基づく紹介患者数の増加を目指すとともに、逆紹介の促進により地域の医療機関との機能分化を図る。更に、大学病院の専門的診療の周知を行うとともに、北九州医療圏以外の医療機関等への訪問を促進し、広域医療圏の連携構築による紹介患者及び逆紹介の増加を図る。 |
|
|
対象入院患者入院前支援率
87%以上 |
入院から退院までの一貫した患者支援を効果的に行うため、医療体制を整備し、入院時からの介入を積極的に行う。 |
||
|
若松病院は、地域における急性期病院としての機能を果たすとともに、在宅療養支援に取り組む。
|
紹介患者
3,300件以上/年 |
若松区唯一の総合的な病院として、地元医療機関等への訪問を促進するとともに情報提供などの連携を強化し、紹介患者及び逆紹介の増加を図る等、地域の中核病院として急性期医療を推進する。 |
|
|
組織新設・廃止等 |
円滑な病院運営を図るため、必要な組織・人員の見直しを行う。 |
||
|
若松病院の特徴を活かした収益を確保する。
|
年間累計の経常収支差額の黒字化 |
特色ある診療を実施し、診療単価及び患者数の増加を図るとともに、経費を節減し収益改善を図る。 |
|
|
病院長を中心としてヒアリングを実施し、各診療部門、看護部及び事務部が連携し、PDCAを回し経営改善を図る。 |
|||
|
経営改善プロジェクトの検討結果を踏まえ、各部門からの経費削減策を実践し、経営改善に向けた取組を行う。 |
|||
|
入院・外来における患者数、平均在院日数及び病床稼働率等の指標について目標値を設定し、管理と評価を行う。 |
|||
|
各診療科の診療実績・データに基づき、各診療科における増収のための計画を立てるとともに、その実現に真に必要な医療機器の整備等を行う。 |
|||
|
訪問看護利用数
5,000件以上/年 |
訪問看護事業及び居宅介護支援事業を継続し、在宅療養支援を強化する。 |
||
|
大学病院からの紹介患者受入数 |
両院それぞれの機能、特性を最大限に発揮し高効率の医療を行うことで収支改善を図るため、時々の地域の医療需要等に応じた機能分化及び連携を推し進める。 |
||
|
無料バス利用者数
500人以上/月 |
若松病院は、外来患者の確保対策として、大学病院と連携し、より効果的な患者移送方法等を検討する。 |
||
|
若松病院は、安全かつ質の高い医療を提供し、信頼される病院、魅力ある病院を目指す。
|
医療安全研修の受講率 100% 毎年度 |
患者への適切なインフォームドコンセントや治療経過に関する十分な説明を行い、患者の意思を尊重した医療を提供する。 |
|
|
令和5年1月に新システム稼働 |
大学病院との調整を行い、最適な医療情報システムの運用を図る。 |
||
|
患者意見箱 回答率100% 毎年度 |
医療相談や退院支援を充実させるとともに、患者サービスの向上及び患者アメニティの改善を図る。 |
||
| 長期ビジョン | (4) 人間愛に満ちた医療人の育成 | ||
|
①
大学病院及び若松病院の存在意義を認識し、高い倫理観を持った人間性豊かな医療人を育成する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
大学病院は、教育・研修・研究の着実な実施により特定機能病院にふさわしい高度な知識と技術を備えた専門職を養成する。
|
マッチング率:100% |
初期臨床研修医の増加を目指すため、積極的な採用活動を実施するとともに、初期臨床研修の受入環境及び魅力的なカリキュラムの整備を行う。 |
|
基本領域別専門研修プログラムのシーリング対応可能な連携施設を確保した診療科 100% |
専門研修プログラム基幹施設として高度な専門研修プログラムを実施するとともに、先進医療に対応できる医師の育成に必要な環境整備を図り、福岡県内外の連携施設を確保する。 |
||
|
医療制度改革に対応すべくタスクシフティングを視野に入れた医療人材の育成を図る。
|
特定行為看護師
50名以上/6カ年 |
両病院共に、看護職及び医療技術職について、
人材育成を目指して、高度かつ専門的な医療知識・技術が取得できる研修体制を整備する。 |
|
|
急性期看護補助加算 |
大学病院は、診療に専念できる環境の整備を図るため、医師・看護師から他職種へのタスクシフティングを推進する。 |
||
|
両病院共に、教育病院として、医学部学生の臨床実習における効果的かつ円滑な実施に努める。 |
(再掲)教育(2) |
医師を目指す学生が、実際の患者の診察・治療を体験し、医師として不可欠な知識・技能・態度を修得するための環境整備等を図る。 |
|
|
両病院共に、事務部門の医療人材の育成を図る。 |
大学病院
査定率
0.45%以下/年 |
診療報酬算定の精度を高めるため、優れた診療報酬請求能力を持つ人材及び病院の診療・経営状況を分析できる人材を育成するため、病院経営・診療報酬請求等に関する関係団体等が行う研修を受講させ、段階的に育成する。 |
|
| 4 社会貢献 | |||
| 長期ビジョン |
世界中の働く人々がより良い生存を享受できる福祉社会の実現を目指し、優れた産業医・産業保健専門職を養成する。 |
||
|
◆第4次中期期間中の 社会貢献 に係る主な数値目標 |
|||
| (1)我が国における産業保健の推進 | |||
|
①
優れた産業医・産業保健専門職を輩出する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
(再掲)
|
(再掲)教育(3) |
(再掲)教育(3)産業医・産業保健専門職の輩出 |
|
(再掲)教育(3) |
(再掲)教育(3)産業医・産業保健専門職の輩出 |
||
|
大学が蓄積した産業保健に関する知見を広く社会に提供する。
|
産業保健関連報道件数 |
産業保健関連情報の発信及び普及を進める。 |
|
|
過労死等防止対策セミナー受講者数 |
産業医をはじめとする産業保健スタッフ等の人材育成等について充実、強化を図るため、長年蓄積してきた過労死等防止対策などに係る研究・教育の成果、ノウハウを活用し、より実践的な内容による研修を実施し、学外に本学の知見を広く提供する。 |
||
|
産業医学実践研修の満足度
90%以上 |
本学で蓄えられた教育・研究成果を活用し、全国各地で産業保健専門職への専門的研修「産業医学実践研修」を実施し、学外に本学の知見を広く提供する。 |
||
|
認定事業の満足度 90%以上 毎年度 |
産業保健に関する知見を基に、企業、事業所等における産業保健活動を支援し、産業保健サービスの充実を図る。 |
||
|
(再掲) |
会員新規登録者数 20名以上/年 |
首都圏プレミアム会員制度やメールマガジン等を活用して、研修会の受講者相互及び講師を含めた人的ネットワークの構築を図り、学外に本学の知見を広く提供する。 |
|
|
(再掲) |
(再掲) |
日本医師会等の認定産業医に係る研修会等に講師を派遣し、産業医学の振興を支援する。 |
|
| 長期ビジョン | (2)学術団体及び国際的な産業保健活動への協力 | ||
|
①
産業医学関連学会活動を推進する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
産業医学関連学会活動を支援する。 |
学会活動支援 2回以上/年 |
産業医科大学学会等、本学と関係の深い学会活動を支援する。 |
|
学術団体及び国際的な産業保健活動への協力を通じて、社会に貢献する。
|
海外機関との学術交流 3回以上/年 |
海外学術機関及びWHO等国際機関との学術交流を推進する。 |
|
|
WHOCCの連続した更新 |
WHO指定協力機関(WHOCC)としての活動を推進するとともに、これら国際機関等からの国際協力事業に対する協力・支援の要請に応える。 |
||
|
国、地方自治体への派遣等 |
国、地方自治体が実施する事業等に対する協力・支援の要請に応える。 |
||
| 長期ビジョン | (3) 地域及び全国における保健医療活動の支援 | ||
|
①
北九州医療圏の医療機関との連携を強力に推進する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
北九州医療圏の医療機関との連携を行う。
|
(再掲)大学病院 診療(3) |
コア・ネットワーク病院を含む近隣医療機関等との緊密な連絡、支援等を行うなど、相互支援体制の構築及び連携強化を図る。 |
|
(再掲)若松病院 診療(3) |
若松区唯一の総合的な病院として、医師会及び近隣の医療機関等と緊密に連携し、患者紹介・逆紹介を促進する。 |
||
|
新興感染症の感染拡大時における医療に対応し、公益に寄与する。
|
(再掲)
|
改正医療法に対応し、新興感染症の感染拡大に対応するため、職員の派遣を含め、可能な限り医療支援を行う。 |
|
|
行政からの要請に協力し、働く人の健康確保を支援する。 |
|||
|
高等教育機関として、生涯学習の機会を提供し、地域社会に貢献する。
|
大学市民公開講座開催回数 |
大学学会市民公開講座を一般市民を対象に実施し、地域社会の貢献を図る。 |
|
|
地域住民からの公開講座要望対応 |
病院の知名度向上や、新規患者の獲得を目指し、ホームページの充実や公開講座の開催を図り、両病院の魅力を積極的に情報発信する。 |
||
|
本学の知見や研究成果を社会に還元し、公益に寄与する。
|
(再掲) |
産学官連携により、社会的な活用を踏まえた知的財産の権利化を積極的に推進するとともに、研究者とのコミュニケーションを図り、質の高い特許等の創出を目指す。 |
|
|
(再掲) |
福島第一原発事故対応の労働者への医療支援を継続する。 |
||
|
大規模災害対応講習会 |
自然災害、NBCテロなど、災害現場で初期対応者となる行政等を対象に講習会を実施し、地域及び全国に対して社会貢献を図る。 |
||
|
SDGsを推進する。 |
(再掲)教育(3)常勤の産業医輩出数
420名以上/6か年 |
産業医学の推進、産業医養成等を通じて、目標8「働きがいも経済成長も」のディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の取組を行うほか、多くのSDGsの項目に貢献する。 |
|
| 5 大学運営 | |||
| 長期ビジョン |
本学の永続的な発展に向けて、本学の進むべき方向性を大学構成員全員が共有する。 |
||
|
◆第4次中期期間中の 大学運営 に係る主な数値目標 |
|||
| (1)大学の発展を支える教職員の育成と活力ある組織づくり | |||
|
①
教職員の育成と活躍を促進し、個々が高いパフォーマンスを発揮する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
全学的に機能的かつ効率的な組織とする。
|
(再掲)
|
「教員組織の編制方針」に基づき、教授の定年あるいは退職及び講座等新設に伴う「講座等のあり方検討会」を実施し、社会や時代が求める教育・研究や産学連携ニーズに柔軟かつ機動的に対応できるようスリムで効率的な教員組織を編制する。 |
|
社会の変化や要請への対応や働き方改革関連法を考慮したうえで、組織の業務を精査し、体制を整備する。 |
|||
|
多様な人材を確保する。
|
定年延長を段階的に実施 |
改正高年齢者雇用安定法の施行を踏まえ、また、国家公務員法の改正を参考に、70歳までの高年齢者就業確保措置や医療技術職、看護職、事務職員の段階的な定年延長について検討し実施する。 |
|
|
年齢構成の均等化(30代、40代、50代の人数差を±5名の範囲とする。)達成年度:令和8年度 |
中長期的な観点に立った適正な職員の配置を行うとともに、経験値を持ち即戦力となる中途採用を含めた短期・中長期の戦略的な採用を行う。 |
||
|
ダイバーシティを推進する |
基本方針に従って、障がい者雇用、管理者における女性労働者の割合を高める。 |
ダイバーシティに関する基本方針を策定し、ダイバーシティ推進室の設置を行う。 |
|
|
職員の能力向上を行う。 |
研修後の行動変容(学びの実践) |
人事考課制度に基づく適正な人事評価を実施するとともに、職員の能力・資質向上のために階層別等の職員研修を複数回実施する。 |
|
|
魅力ある働きやすい職場環境を整える。
|
(再掲)提案件数
50件以上/年 |
職員の意見・要望を聴取する仕組み(提案制度、ランチミーティング等)を活用し、職員が積極的に仕事に取り組めるよう具体的な取組を図る。 |
|
|
医療技術職、看護職、事務職 超過勤務実績 10%減/6か年 |
会議体における対策の検討を月1回以上行い、超過勤務を削減する。 |
||
|
(再掲)平均10日以上の年次有給休暇取得/年 |
職員の健康面やワーク・ライフ・バランスに配慮し、男女共同参画推進のための方策の計画及び実施に係る支援を図る。 |
||
|
(再掲)DXによる業務効率化を2件以上/年 |
DXによる業務改善を推進する。 |
||
|
テレワーク実施率 10%/年 |
柔軟な働き方に対応し、テレワークを推進する。 |
||
|
医師の働き方改革に対応し、労働時間管理の適正化を行う。 |
「医師の労働時間短縮計画」に定める超過勤務時間の削減率 |
医師の健康を担保し、労働時間短縮に向けた医師の働き方改革を推進する。 |
|
|
学生及び職員の保健指導をきめ細やかに実施し、心身の健康保持増進を図る。 |
職員・学生健康診断受診率 100% |
学生と職員の生活を健康面から支援する。 |
|
|
自己点検評価及び第三者評価を実施し、その結果を大学運営の改善に反映させる。
|
改善項目に100%対応する。 |
大学基準協会の認証評価の組織的な対応を社会環境の変化を踏まえ、効果的に実施し、第3期の評価で是正勧告を受けた大学院における研究指導方法及びスケジュールの策定等必要な改善を行い、次期受審の準備を行う。 |
|
|
令和元年度受審時の改善項目に |
病院機能評価の令和元年度受審の指摘事項を踏まえ、改善に取り組み、令和6年度次回受審の準備を行う。 |
||
|
(再掲) 教育(2) |
(再掲) 教育(2)医学教育認証評価 |
||
|
大学の社会的責任を果たすため、コンプライアンスの確立に向けて、継続的な推進を図る。
|
講習会後の行動変容 70%以上/回 毎年度
|
職員のコンプライアンス意識の定着を図り、法令及び学内規則等を遵守するとともに、高い倫理観と良識をもって行動するよう遵守への取組を行う。 |
|
|
個人情報に関して適用される法令等を遵守するとともに、本学の個人情報保護に関する規程に基づき、情報の適正な取得・管理・利用に努める。 |
|||
|
情報セキュリティの維持及び向上を図るため、情報セキュリティ講習会の実施や実施(運用)マニュアル等の充実を図り、情報機器及びツールの適切な利用について、教職員への啓発に努める。 |
|||
|
研究不正発生件数0件 毎年度 |
研究活動における不正行為の防止のため、研究活動、公的研究費の不正使用防止に係る教育を行う研修会の開催等、組織的な取組を実施する。 |
||
|
本学卒業生をも含む産業医・産業保健専門職と相互発展しうる連携体制を構築する。 |
2週間以内の卒業生への回答率 |
産業保健現場からの臨床分野に関する疑問や悩みに、臨床の本学医師が回答する病産連携窓口を活用し、産業医学推進研究会等、大学と卒業生との連携体制を強化する。 |
|
| 長期ビジョン | (2)大学発展のための強固な財政基盤の確立 | ||
|
①
継続的な大学運営を支える揺るぎない経営基盤を確立する。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
財政基盤の安定化を図る。
|
管理経費の前年度比
0.5%削減 |
中期財政計画に基づく適正な予算編成を行うとともに、管理経費等の支出を抑制した予算執行を実施する。 |
|
実現した新規要求件数 |
大学運営費補助金は、必要な新規事業の予算要求を行う。 |
||
|
(再掲) |
会計処理を適正に実施し、経営状況の把握と分析による経営管理を行い、現状を認識するとともに、原因把握や具体的な改善を行う。 |
||
|
入札実施率前年度比
3%以上 |
物品購入・委託契約等の契約相手方との取引は、競争を原則とし、本学会計規則に基づき、常に合法性・経済性を踏まえた公正な契約手続きを行うとともに、継続的な委託契約等について契約方法等の見直しにより、競争性を高めることで経費抑制を進める。 |
||
|
資金運用計画において定める年間目標利回りの達成 |
運用資金は、本学資金運用規程に基づき、外部有識者による意見も聞きつつ資金運用計画を決定し、安全かつ有利に運用する。 |
||
|
自己収入の増加を図る。 |
寄付金収入目標 10億円/6か年 |
開学40周年記念事業等の寄付金収入の獲得を図るとともに、急性期診療棟に係る募金を実行する。また、必要に応じてクラウドファンディングを活用した募金等を企画する。 |
|
|
科学研究費等外部研究資金の獲得に努め、収入の拡大を図る。
|
科学研究費助成事業の新規採択件数40件以上/年(新規採択率20%以上及び新規申請率45%以上) 毎年度 |
文部科学省及び(独)日本学術振興会が公募する科学研究費助成事業等の募集情報を、研究者に遅滞なく周知するとともに、外部資金の一層の獲得を図るための支援体制・環境整備に努める。 |
|
|
共同研究・受託研究・奨学寄附金の獲得件数
合計500件以上/年 |
企業との業務提携を活用し、更に共同研究・受託研究・奨学寄附金の獲得を推進する。 |
||
| 長期ビジョン | (3) 産業医学・産業保健の教育研究拠点及び特定機能病院としてふさわしい施設環境の実現 | ||
|
①
大学運営を支えるための施設整備を着実に進める。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
教育研究拠点として高度な教育・研究活動を促進するための研究環境を整備する。 |
教育研究支援施設整備計画に、設備・機器更新の内容を定め、実行する。 |
教育研究支援施設を計画的に整備し、教育・研究の推進を支援する。 |
|
特定機能病院及び高度急性期病院としての施設、設備の整備を行う。
|
令和5年4月の竣工及び8月の開院
|
大学病院の施設の拡充である急性期診療棟について工期、予算を順守し、設備を整備する。令和4年度工事完成率を99.3%、令和5年度工事完成率を100%とし計画する。 |
|
|
急性期診療棟竣工後の大学病院内の跡地活用について、大学全体で検討し、実施する。 |
|||
|
令和5年度以降の大学病院中央診療部門の機器更新計画の策定 |
医療設備・機器の整備を継続的かつ計画的に行う。 |
||
|
Wi-Fi整備計画に基づき、当該計画を100%達成する。 |
大学病院において、Wi-Fi整備計画を策定し、当該計画に基づき、Wi-Fiカバーエリアの拡充を進める。 |
||
|
急性期病院としての機能強化のため、若松病院における施設、設備の整備を行う。
|
若松病院機器整備計画の策定と計画に基づく財源の確保 |
老朽化した医療機器の計画的な更新を引き続き実施するとともに、必要な基幹設備の更新に係る財源確保について検討する。 |
|
|
Wi-Fi整備計画に基づき、当該計画を100%達成 |
若松病院において、Wi-Fi整備計画を策定し、当該計画に基づき、Wi-Fiカバーエリアの拡充を進める。 |
||
|
大学全体の施設整備を着実に進める。
|
令和5年5月理事会報告 |
建物の建替え及び改修時期を想定し、統一感のある施設整備計画の全体像について検討を行う。 |
|
|
保全計画 100%の実施/各年度 |
大学施設の耐震補強及び設備更新工事について、施設整備保全計画に基づき実施する。 |
||
|
労働安全衛生マネジメントシステムを確実に実施する。 |
労働災害(不休災害を含む)総件数5%以上減/6か年(対第3次中期期間中) |
労働安全衛生法等に基づく必要な見直しを図る。 |
|
|
学内における環境マネジメントシステムにより、環境保全活動の推進を図る。 |
実験廃液違反0件/年 |
実験廃液等排出責任者等を対象とした講習会をeラーニング等も活用し、毎年1回開催する。 |
|
|
効率的な業務運営、事業継続のために、情報セキュリティの十分な確保をはじめとし、必要な情報システムの整備を図る。 |
システム1時間以上の停止を伴うシステム障害 3件以下/年 |
大学内における各情報システムの環境整備を行うとともに情報資産の保全を図る。 |
|
| 長期ビジョン | (4) 本学の魅力や強みを発信する積極的広報 | ||
|
①
本学の存在意義を余すことなく、分かりやすく発信し、社会に対する説明責任を果たす。 |
|||
|
第 4 次 中 期 目 標 ・ 中 期 計 画 |
積極的な広報を実践する。
|
プレスリリース後、報道された件数
|
本学の教育・研究・診療の状況や成果に関し、積極的に情報公開・発信を行い、本学の社会的責任を果たすとともに、認知度の向上を図る。 |
|
大学を取り巻くステークホルダーとの信頼関係の構築のため、迅速かつ適切で公平な情報開示により、大学運営の透明性を図る。 |
|||
|
大学病院
ホームページ閲覧件数 |
UOEH病院戦略(広報)を積極的に推進し、両病院共に、地域の中核病院として地域住民に対し、ホームページ、SNS等を活用し、高度な最新医療をはじめとした医療に関する情報提供の充実を図る。 |
||